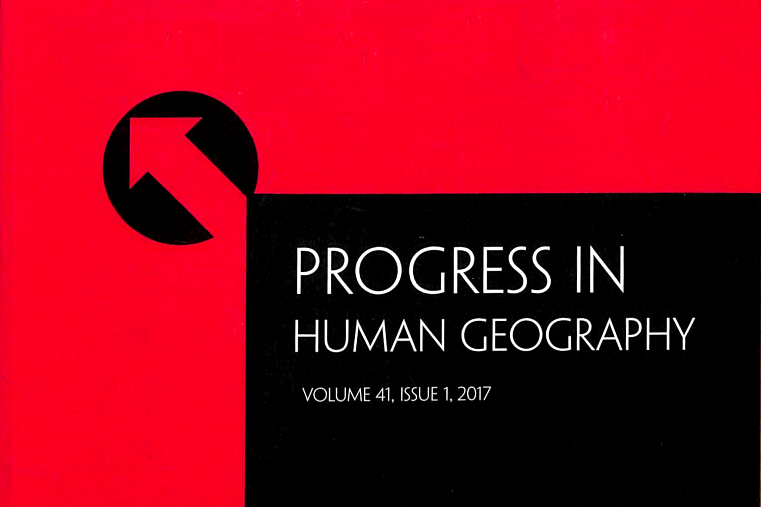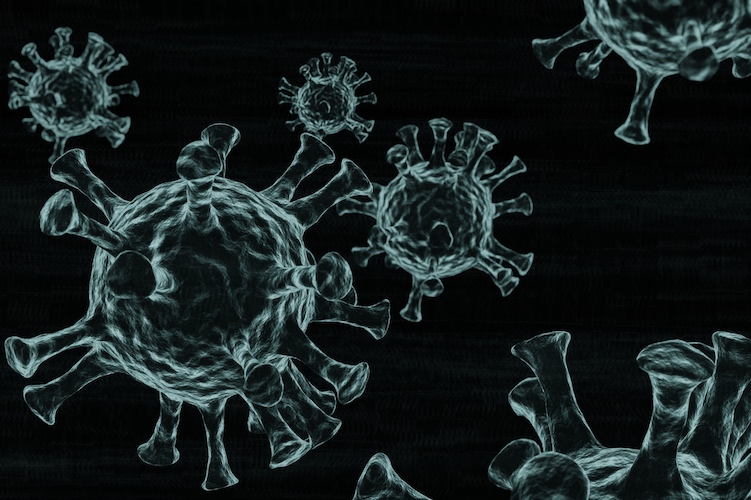「例外状態」と「剝き出しの生」
アガンベン『人権の彼方に』の余白に
西谷修
編集部より
このほど、長らく品切れ状態が続いていたジョルジョ・アガンベン『人権の彼方に――政治哲学ノート』の訳を一新し、書名も原書により忠実なものに直した改訂新版となる『目的のない手段――政治についての覚え書き』を、小社より刊行した。翻訳は、旧版同様、高桑和巳氏によるものである。本書は、アガンベンがのちに『ホモ・サケル――主権権力と剝き出しの生』(以文社)で展開する思索のエッセンスが散りばめられており、時評を踏まえたエッセイ集ながら、「ホモ・サケル」シリーズの最良の副読本としても位置づけられるだろう。旧版『人権の彼方に』刊行時には、まだアガンベンは日本でもそこまで知られた哲学者ではなかった。そのため、旧版に掲載された西谷修氏による「解題」は、日本へのアガンベン思想の導入・紹介として、重要な位置づけをもつ論考である。「例外状態」や「剝き出しの生」といった、「ホモ・サケル」シリーズで展開されるアガンベンの鍵概念を、バタイユやルジャンドル、レヴィナス、フーコーらの思考と照らし合わせながら論ずる西谷氏の「解題」は、これから新たにアガンベンの作品と出会う読者の助けとなるだろう。こうした意義から、本稿を小社HPに再録することとしたい。掲載にあたり、快く承諾いただいた著者の西谷修氏に改めて感謝を申し上げる。(以文社編集部)


凡庸さをおそれず繰り返せば、20世紀は「戦争と革命」の時代だった。古来くり返されてきた「戦争」がこの100年間にとりわけ際立つのは、戦争が世界化し、人類が同じひとつの戦争に巻き込まれることで、人間世界の全体化が「戦争」という状態において達成されたからである。「世界戦争」と規定しうるこの出来事によって、クラウゼヴィッツ以来の古典的な戦争概念、あるいは国際法による法的状態としての戦争は窒息状態に陥り、それが変質した結果今では、国際的な「警察行動」を装った圧倒的な武力行使か、文字どおり無法状態としてのジェノサイドしかなくなってしまった。「戦争」は腐乱している、とでもいおうか。
世界戦争の条件を作り出したのは産業主義的社会組成と国民国家システムであり、それが総動員と総力戦を可能にし、また不可避にもしたのだが、その産業の発展を支えたテクノロジーはまた、兵器の破壊力を極限にまで――つまり生活世界の無化にまで――高めて、「破壊」そのものの質を変えることになった。また、理念としてしかありえない国民国家に人びとを統合するため、国民の歴史という共同の物語が作り出されて世俗国家の神話として機能し、その一方で科学のイデオロギーが新たな盲信を生んで、とりわけ生物学的人種主義が潜在的な「敵」のイメージを作るため政治的に活用される。そのうえ人びとは大量の情報に溺れて、直接的な経験や判断よりも、媒介され処理され匿名で供給されるメディアのほうを信じるのだ。
「革命」はある意味では、このようにして万人を駆り立てる戦争のメカニズムに抵抗し、階級を対立軸に世界を別様に再編しようという試みだったが、結局は産業主義的要請と国家の時代の戦争の論理に呑み込まれ、そのモチーフを偏狭で抑圧的な教条へと硬化させて、やがて吹き出す矛盾の沼の中に沈没してしまった。後に残ったのは、経済効率とテクノロジー、そして単純化された欲望の賭博場としての「市場」原理の優位であり、そこに投影された「自由」の幻影が、疑われることのない自明の理として跋扈している。
この戦争の世紀のただなかに出現したのが「強制収容所」だった。強制収容所が歴史上類のないものとして強調されるのは、収容所を支配した冷酷な暴力とそこでの生存の悲惨さのためばかりではない。それが同じ一つの「内部」と化した世界で、国家の権力によって「存在しないもの」として生み出された「外部」であり、擬似的にであれ生物学的理論にもとづいて「人間」に境界線が引かれ、生きるべき者たちと抹消すべき者たちが截然と区別されて、なおかつその抹消のプロセスが、「無」の生産とでも言いうるような産業システムの手順そのままに現実化されたからである。だからこそこの「事業」は、たんに特定の一民族の受難にとどまるのではなく、現代世界に生きるあらゆる人びとを潜在的に巻き込む出来事だったのである。
強制収容所がどのようなものであり、そこに収容されるということがどのような体験なのかを少しでも知るためには、通常の意識の枠を超えた「例外状態」に対する想像力がいる。「例外状態」とはカール・シュミットの規定によれば、あらゆる法秩序が停止され、「決定」の権力があらゆる法権利に拘束されずに行使される状況である。「主権」はそこにしか根拠をもたないとシュミットは言う。その「主権」とは、古典的な定義によれば、生殺与奪の権利、つまりある人びとに死を与え、他の人びとを生に放置する権限である。強制収容所は純粋な「例外状態」にある。そこでは法的な根拠を必要としない剝き出しの権力が、その恣意的な決定を、いっさいの法権利の外に置かれた人びとの上に及ぼす。一方、収容された人びとは、たんに自由や権利を奪われただけでなく、人格さえ剝脱され、もはやいかなる意味でも「主体」ではなくなり、「私」と表明する権能さえ失って、ただ単に生きている――そして死を約束されている――という、「剝き出しの生」の状態に陥れられる。「強制収容所」とは、そのように剝き出しの権力が剝き出しの生に向き合う、法秩序の「外部」である。もちろんそこには、もはや公共性も個人の内面もなく、私的なものと公的なものとの区別もない。
そのように法権利の外に置かれるという状況は、程度の差こそあれ、地表のあらゆる広がりが国境線によって分断され国民国家に囲い込まれることによって締め出され、生存の場を失ったあらゆる「難民」たちの運命でもある。現在に億単位で存在すると言われる「難民」もまたこの20世紀世界の生みだした「不可能な生」の形態なのである。
戒厳令のように、法が設定する法秩序の中断、しかし法秩序に依拠するのではなく、逆に「主権」を露呈させてあらゆる法の設定を可能にするこの「例外状態」は、法的考察とは別のところで早くから考察されてきた。一部の文学的思考やある種の哲学的思考は、今世紀のさまざまな体験を潜るなかから、それを「外」とか「外部」とかいうタームで扱ってきたのだ。その二つが、つまり主体性の失効の経験と法や政治の思考とが、いまようやく結びつくようになったのだ。
たとえばジョルジュ・バタイユは、ローマ神話に登場するネミの森の神官ディアヌスの形象をみずからの「エクスターズ(脱存)」の体験の体験のエンブレムのように用いている。ディアヌスとは、前任者を殺すことによってのみ森の王の地位を引き継ぎ、ひとたび王となるや、今度は自分が誰とも知れぬ殺害者の手にかかって殺されるまでその地位にとどまるという、奇妙な掟に捉えられた「主権者=至高者」だ。かれの「主権」とはいつ襲い来るとも知れぬ死の刃に怯えながら永遠に眠れぬ夜を過ごす、その目覚めの緊張以外のものではない。あらゆる法権利の庇護の外に置かれ、剝き出しのまま森に蔓延する死の脅威にさらされるのがこの森の王の栄光なのである。
ディアヌスを捉える掟は、人を「例外状態」に運命づける法である。その「例外状態」はまた、死の権能の不在、言いかえれば「死の不可能性」とも規定できるが、それはまた「剝き出しの生」の刻印のひとつでもある(拙著『不死のワンダーランド』講談社学術文庫を参照されたい)。みずからの「忘我」の体験を、世界が我を失い全般的例外状態に突入する「戦争」と同調させ、「私自身が戦争だ」とも語ったバタイユは、主体と理性の秩序の外に身を置く体験から、「例外状態」の両義性にそのまま身をさらしながら、ヨーロッパ的秩序と主権や主体性の構成の秘密にも触れている。
ナチズムは武力によって破壊されはしたが、論議によって論破された訳ではない、と明言したのはフランスの法制史家ピエール・ルジャンドルである。ナチズムは「例外状態」のなかで、「剝き出しの生」に権力の焼き鏝を押したが(名前さえ奪われた収容所の人びとの腕に彫り込まれた意味のない数字としての番号)、その事態に象徴されるように生物学的な人間の規定を政治に導入し、人間を処理されるべき「肉」の原理によって制度的秩序に組み込んだ。第三帝国はたしかに戦争で崩壊しはしたが、人間が「剝き出しの生」として、あるいは「生きた資材」として政治や知のシステムや社会的実践に組み込まれる状況は、消滅するよりもむしろ「勝者の法権利」に正当化されることで世界化し恒常化していると言ってよいだろう。
忘れてはならないのは、現代生理学の基礎を作ったクロード・ベルナールが、生物学はバイオロジーというその名に反して、「生命」などという概念にはこだわらないと明言していることだ。それは有機体としての生き物の組織や機能の研究であって、現実に生きる人間の生を扱うことでは決してない。いまや優秀な人種を産み育てるのに、オリンピック選手とノーベル賞学者を交配する必要はない。医学の実験に生きた人間を使う必要はない。物議を醸す「人格」や「人間の尊厳」への抵触を掠めて、あらゆるバイオテクノロジーが「市場原理」に委ねられてしのぎを削っている。そしてその「市場」は人間の欲望によって方向付けられ促されるというが、そこで想定されるあるいはせき立てられる「欲望」の、何と、あまりに「人間的」なことか。人はいまや自分自身をその「剝き出しの生」のレベルで捉えることに慣れきっている。
近代の人間の公準は、「私」と自己表明する主体であり、自由と権利の出発点であり担い手だった。だが「例外状態」にあってはその条件のいっさいは剝ぎ取られる。あるいは機能しない。そのとき人は「剝き出しの生」に還元されるが、その「例外状態」は通例の事態がそれなしに構成されるものではなく、まさに通例の事態を可能にする条件なのである。ちょうどもう一人の戦争の思想家エマニュエル・レヴィナスが、あらゆる主体の意識を闇に呑み込む「夜」としての「イリヤ」を想定し(意識の「例外状況」)、主体はそこからしか、それを背負ってしか再構成されないと考えたように。「ポストモダン」ということが言われたが、それは他でもない「モダン」の公準がその出自を露呈させて失効し、この「例外状態」が密かに遍在化する現代の謂いでないとしたら何の意味があるだろうか。 ジョルジョ・アガンベンはおそらく、この錯誤と混迷の時代に、これまでの哲学的思考や美学的思考、言語の思考や政治の思考の絡み合う地点を明示し、何をどのように思考すべきかを提示しえた数少ない思想家である。かれはヨーロッパの源流ギリシアの言語に、二つの生の概念があったことを示している。ひとつはただ生きているというたんなる事実を指す「ゾーエー」、もうひとつはポリスの生である「ビオス」。ところが「ビオス」を語源とするバイオロジーは他でもない「ゾーエー」としての生しか扱わず、そこでは個も生死も単一性や有限性も視野にはない。「ビオス」と「ゾーエー」との懸隔を埋めてそれを不可分で単一の「生」に編み上げるのは、「世界戦争」に集約される多面的な分離のプロセスに抵抗し、それを解体しようとする思考である。「ビオス」がポリスの生であるならば、その思考は当然ながら政治的思考となる。そのようにして「政治」をもう一度根本的なカテゴリーたらしめるのは、政治がその自覚もなしに、フーコーの言う「ビオ・ポリティック」として、人間社会のさまざまな活動のレベルを貫いて「剝き出しの生」に届いている現在、何より重要な思考への要請である。アガンベンがこの本で提供しているのはそのためのいくつかの貴重な糸口である。
著者紹介
西谷修(にしたに・おさむ)
フランス思想、 とくにバタイユ、ブランショ、レヴィナス、ルジャンドルらを研究。明治学院大学教授、東京外国語大学大学院教授、立教大学大学院特任教授を経て、東京外国語大学名誉教授、神戸市外国語大学客員教授。