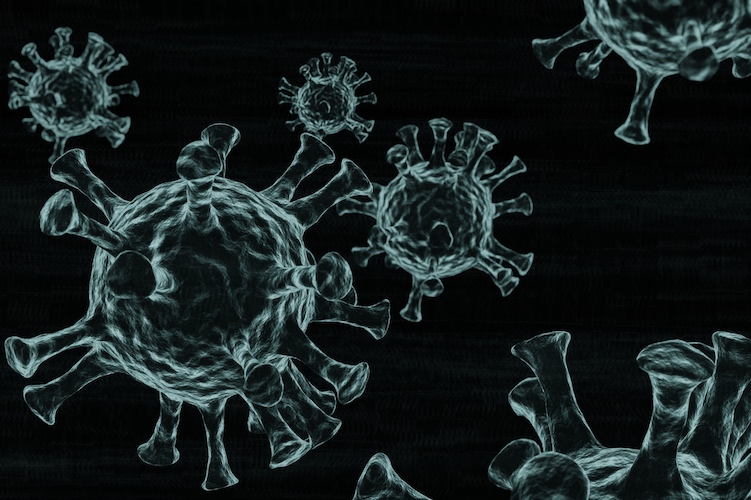「世の中の裂け目」はいつだって開く──小沢健二が帰ってきた
片岡大右

『So kakkoii 宇宙』についての付記
2019年11月13日、小沢健二のほんとうに久しぶりのアルバム、『So kakkoii 宇宙』がわたしたちに届けられた。
「そして時は2020」と歌いだされた新しい年の訪れに合わせ、『図書新聞』2018年4月14日・3347号へのわたしの寄稿、「「世の中の裂け目」はいつだって開く」を以下に転載する。宇野維正『小沢健二の帰還』(岩波書店、2017年11月)刊行を受けて書かれた本稿は、同書の論述に促されつつ、わたしなりの観点からこの類まれな「ミュージシャン、作文家」を論じたものだ。この必読の導入の書を著された宇野氏、適切極まりない著者を適切極まりないタイミングで説得し出版への道筋をつけた岩波書店の渡部朝香氏、そして1万1千字を超えるわたしの原稿を当時豪胆に受け入れ、今回転載を快く許可してくださった『図書新聞』の須藤巧氏に、改めて敬意と感謝の意を表したい。
転載に先立ち、以下に新アルバムの印象を簡単に記すことにする。
**********
13年ぶりの全国ツアーとして2010年5・6月に行われ、「帰還」への第一歩となった「ひふみよ」では、アンコールで歌われた「愛し愛されて生きるのさ」の英語詞部分が「我ら時をゆく」と言い換えられていた。ライヴ音源に新旧の文章作品(「ドゥワッチャライク 1994-1997」、「うさぎ! 2010-2011」)他を併せた作品集が『我ら、時』(2012年)と名付けられたことからも、ここに重要なテーマがあることは明らかだ。じっさい、突然の渡米と活動の極端な縮小ないし方向転換を経て日本のポップミュージック・シーンに帰ってくる過程で、小沢健二が直面したのは自分が、そして自分を含む人びと――「我ら」――が、どのような時間を生きているのか、どのような時間をともに生きていけるのかという問題だったのだと思う。
極東の列島で紛れもないスターとして生きた1990年代の過去を、まずは「NYC男子」として、ついで「南米男子」として過ごした21世紀の現在とどのように結びつけ、かつての聴き手と新たな聴き手とともに、どのような未来を展望していくのか。英語タイトル So Kakkoii Pluriverse に即してミュージシャン自身が明らかにしているように、今回のアルバムで歌われる「宇宙」は根本的な多元性を特徴としているのだけれど、こうして強調される多元性は、この時間の意識に関わっている。
『So kakkoii 宇宙』の冒頭に置かれた「彗星」では、2020年を目前に控えた2019年冬の現在が、1995年という過去からの時の流れのなかに置かれる。「笑い声と音楽の青春の日々」を経た今。わたしたちの現在は、過去の経験と記憶によって二重化されている。もっとも、この最初の曲では大体のところ、過去と現在の連続性が肯定され祝福されているように見える(「はるか遠い昔 湧き出した美しさは ここに」/「グラス高くかかげ 思いっきり祝いたいよね」)。
けれど2曲目の「流動体について」では、わたしたちが生きている現在が、過去にはらまれていたいくつもの可能性のひとつにすぎないことが強調される。この現在は、別のものでもありえた。例えば、1曲目で言及されていた「今遠くにいるあのひと」との関係が続いていたら、「子どもたちも違う子たち」だったはずだ(愛する長男の写真をジャケットに掲げたアルバムでこういうことを歌っているのがすごい)。わたしたちの現在は、過去との関係でばかりではなく、つねに「並行する世界」と隣り合っているという理由でも、二重のものになっている。
4曲目の「失敗がいっぱい」で言われるように「失敗のはじまりを反省する時」はもちろんのこと、「流動体について」で回想されるように、この今が「間違いに気がつくこと」の結果として選び取られたものだった場合にさえ、わたしたちは取り替えの効かない現在を生きながらも、並行世界のもうひとつの現在を時に思わずにはいない。そんなわたしたちは、決してたどり着くことができないこのもうひとつの現在を押しのけるようにして、やがて訪れるはずの未来を思い描き、それによって今ここを二重化することで自分を励ましている。
この未来という次元は、1曲目(「高まる波 近づいてる」)でも2曲目(「確かな約束」)でも決定的な意味を持っていたけれども、3曲目の「フクロウの声が聞こえる」で繰り返される「いつか」によって改めて主題化されて、以後、「失敗がいっぱい」以外の全曲の展開のなかで、多少とも中心的な役割を果たしていく。
「フクロウ」で展望されたのよりもずっと間近なものとしての未来が、「今もう少しで」訪れることを待ち望む5曲目の「いちごが染まる」。「汚れた僕ら」が「魔法のトンネルの先」で再生されることを歌う6曲目の「アルペジオ」。「願い」が成就する「確かな時」に捧げられた祈りのような7曲目の「神秘的」。8曲目の「高い塔」の歌い手は、まさにその「神秘」と連れ立って「0から無限大のほうへ」と旅立つ。9曲目の「シナモン」では、「ゆっくりと進む 海賊船」が「君と僕の約束を乗せ」て「夜の終わり」へと向かう。その時が来れば、「涙は乾く」のだ。
そして10曲目の「薫る」。「フクロウの声が聞こえる」の「いつか」、「いちごが染まる」の「今もう少しで」と呼び交わすようにして、この最後の曲では世界が「もう少しで」その表情を変えることが何度も予告される。わたしたちの現在は、来たるべき時の予感をはらみ、「未来の虹」と「未来の神秘」に照らされている。
けれども、「薫る」で歌われるのは何より、この未来が現在の「労働と学業」によってこそ生み出されるということ、「毎日の技」が、日々に発揮される「好奇心」が、「偉大な宇宙」を薫らせ、「新しいもの」を「生み出していく」ということだ。わたしたちの毎日は決して、来たるべき時の訪れを待つだけの空虚な時間なのではない。
取り戻すことができない過去を抱え、別のものでありえた現在を並行世界として傍らに置き、未来の輝きを思うことで支えられているわたしたちの現在。『So kakkoii 宇宙』は、これら3つの次元によって多元化された現在を、それでも力強く肯定するためにつくられている。「今ここ」に生きることの「奇跡」を歌う「彗星」が冒頭に置かれているのは、まさにそのためだ。
もちろん、これまで見てきたことから明らかなように、小沢健二はこの「奇跡」によって現在から多元性を追放してしまうのではない。というかむしろ、そんなことは決してできないということを繰り返し表現する。だからこそ、「今ここにある この暮らしこそが/宇宙だよ」という最初の曲の言葉を覆すようにして、続く「流動体について」では並行世界が導入されるのだし、「アルペジオ」では今を未来へと生き抜くための「僕」や「君」の弱さが強調され、「高い塔」では唐突に、ほとんど途方に暮れたようなつぶやきが口にされる。「生きることはいつの月日も難しくて/複雑で 不可解で/君の中で消えた炎とか/僕が失くしてしまったものとか/全部 答えがないけど」……。
こうした難しさそれ自体を主題にしたのが、4曲目の「失敗がいっぱい」だ。そしてそこでは、この難しさを克服するための処方箋も提示されている。「魂を救う」のは、日々の暮らしそれ自体なのだ。2006年のインストゥルメンタル・アルバムのタイトルを借りて「毎日の環境学」と名付けることもできそうなこの曲は、「毎日には なおす力がある」のだと繰り返し言い聞かせる。
続く「いちごが染まる」で歌われるように、こうしてわたしたちは日々のたゆみない歩みのなかで失敗を癒やし、「一つの夜ごと/未来の方へ弾む」ことができる……のだろうか。この5曲目は、「今もう少しで」訪れる充実した未来への確信を美しく歌い上げているけれども、ほんとうのところはわからない。じっさい前曲では、「そんな日がくるような気はしないけど」として、「訪れる幸せ」の確実さが疑われていた。
そう、「確かな約束」と「確かな時」が歌われながらも、このアルバムには不安と弱さと迷いの率直な表現があちこちに散りばめられている。『So kakkoii 宇宙』が感動的なのは、これら2つの側面がお互いを打ち消すのではなく、むしろこの作品にしっかりとした現実の手応えを与え、時に――ミュージシャン本人に言わせれば、特に最後の2曲、「シナモン」と「薫る」(『AERA』2019.11.18)で――「へなちょこ」感を醸し出しつつも、というかまさにそのことによって、全体として力強い励ましに満ちた音楽を響かせていることだ。
「へなちょこ」という形容がしっくりくるかどうかは別として、1994年の『LIFE』もまた、同じような二面性に貫かれたアルバムだった。ひたすら陽性の作品として振り返られがちだけれど、実際には作中のそこここに、喪失と痛みが刻まれている。「彗星」で言及される1995年に出た一連のシングル収録曲についても同じことだ(特に、主題的な目配せが明らかな――10年前の「ひふみよ」でも冒頭で歌われた――「流星ビバップ」)。男女の愛にすべてを求めるような歌をつくることはなくなっても、わたしたちを「悩める時にも未来の世界に連れてく」(「愛し愛されて生きるのさ」)ような何かを、悩み迷う時間の切実さを大切にしながら、小沢健二は昔も今も歌っている。
それでは、2020年と1995年のあいだの時期、とりわけ『Eclectic』(2002年2月)と「うさぎ!」(2005年秋~)によって代表される時期の小沢健二は何をしていたのか。以下の文章はそのことを主題にしている。一読されるなら、「やっぱり小沢健二さんなんだよなー」と、うさぎ少年ならずともつぶやかずにはいられないはずだと思う。
2020年1月1日 片岡大右
「額縁に飾られた美文」対「強い意思」
「絵本の国には基地帝国の基地が八十八ヶ所もあって、絵本の国じたいの軍事費の額も数十年間、世界で三位から六位くらいで、世界屈指じゃない? さらに国内に山と積まれた基地帝国の武器を加えたら、かなり軍事力ギンギンの国だよね。その国が「平和憲法を持った世界唯一の国だ」と言われても、困ってしまうよ」――「うさぎ!」第31話(『子どもと昔話』55号、2013年4月)の後半部で、登場人物のひとり、きららは語る。15歳の少女はそこで、「友人たちもする言い方だから、嫌なことは言いたくないんだけど」と一応は配慮しつつも、「「我が国の宝、世界に誇る平和憲法」みたいな言い方」への違和感をあらわに表明する。
なぜだろうか。ひとつには、最初に引いた一節で示唆されているように、そうした言葉を口にする人びとが、軍事大国としての日本の実態に必ずしも敏感ではなく、現状を変えるための努力を行っているようには見えないことへのいら立ちがある。「欲しいのは平和憲法なのか、平和そのものなのか〔…〕。平和そのものが欲しいなら、憲法がどうでも、やるべきことはたくさんある。」

そして、このこととも関わるけれど、きららの反発のもっと大きな理由は、そうした人びとが、自分たちの主張の根拠を誰かが昔つくった条文に求めるばかりで、自分たちの力、新しい社会にかたちを与えていくための自分たち自身の意思の力を、十分に自覚し信じているようには思われないという点にあるようだ。「どうにかしたいから、鍋でも釜でも、怪しげな美文の入った額縁でも投げつける」ということなら、わからなくもない。そんな風に譲歩しつつもやはり、きららは、トゥラルパンは、うさぎは、そしておそらくこの奇妙な童話の作者自身も、現実を変えていく意思の力よりも「額縁に飾られた美文」の保守に根拠を置いた「絵本の国」の人びとの戦いぶりを、多少とも残念なものに感じている(なお、小沢健二が戦後日本の再建を「平和憲法」に象徴させるたぐいの物語を決定的に相対化する観点に立っていることは、それを「戦前の「大東亜共栄圏」に近いもの」の米国主導下での構築として捉え直す第34話~第36話を読むとよくわかる)。
対比的に、いくぶんかの挑発を込めて引き合いに出されるのが、「基地帝国」の権力者たちの確信に満ちた振舞いだ。「権力者たちは戦う〔…〕。憲法の言葉なんか、気にしないで。現実は意思が、強い意思がつくっていくものだと、知っているから。」この第31話の前半部は、その実例の提示に割かれている。きららはそこで、一か月を過ごした「南国市」ことマイアミでの経験を語る。彼女が滞在したのは、海辺から「有料の橋」を渡った先にある「X島」だという。広告がいっさいなく、だから「一つ一つの存在の美しさがきわ立って見える」この島は、「基地帝国でも一番のお金持ちの人たちが住む地域の一つ」だ。
「普通なら規制に文句をつける側」の、彼ら「ビジネス界の権力者たち」は、自分たちの住む場所を「視界汚染」から守るためなら、言論の自由に抵触し憲法違反となるレベルの広告規制を決然と推し進める。「X島の協議会の委員は選挙で選ばれるんだけど、プロの政治家は一人もいない。委員には給料も、経費も出ない。住民がおこづかいで集まって政治をする。権力者で大金持ちである住民たちは、小さな島を独立した自治体にして、アマチュア政治家として、誰に借りもなしで、本音で怒ったり泣いたりしながら、自分たちの生活環境を決めていくわけ。」彼らは「世の中の自然な流れ」など信じないし、だから「普通の人」の物わかりのよい断念とは無縁だ。「権力者たち、例えばX島の住人たちは、「仕方がない」なんて風に諦めることは、絶対にないの。彼らはガンガン戦って、意思を押し通すんだよ。現実とは、仕組みだろうが法律だろうが乗り越えて、意思でつくっていくものだと、知ってるから。「広告規制は憲法違反? だから何? うちの周りに看板立つの、嫌だもん」くらいのことなんだよ。」
2018年の今、この一節に立ち返ることで想起されるのは、たとえば、米国の著名投資家カール・アイカーン――マイアミのビスケーン湾内に浮かぶ「ゲイティッド・コミュニティ」、米国の最富裕地域のひとつインディアン・クリーク島の住人である――の、トランプ政権入りのエピソードだ。当初財務長官就任を打診された彼は結局、規制改革担当の顧問役を、無報酬で引き受けた(利益相反の批判を前にやがて辞任したけれど)。よく知られているように、トランプ自身も大統領給与の受け取りを拒否している。自分たちの望む社会を自分たちでデザインし実現していく、アマチュア政治家となってそうした意思にかたちを与えられるなら報酬などいらないというX島の流儀は、かなりの程度、トランプ政権の流儀でもあるわけだ。そして最近でも共和党と民主党の選択をペプシとコカ・コーラの選択に喩え続けている小沢健二は(『Poppin’ Flag』、2018年2月21日)、それを以前からの米国政治全般の流儀に通じるものと考えている。
きららの発言に戻るなら、ここでの主旨はもちろん、意思を現実のものにしていく力は政財界の「権力者」だけではなく、「普通の人」にだって備わっていることの強調にある。「あたしたちも、権力者たちに比べると力が極小なだけで、やっぱり同じ力は持ってるんだよ。だし、世の中も少しずつ変えてるの」……。そのことを自覚し誇りに思うなら、自分たちの意思よりも前に「額縁に飾られた美文」を置くような発想には、やはり不満が残るのである。
『小沢健二の帰還』が教えてくれること
それにしても、富裕層の豪邸が立ち並ぶこうしたコミュニティには、気安く立ち入れないものもあるはずだ。じっさい、日本語でウェブ検索してみると、歌手のビヨンセが上記のアイカーンと同じインディアン・クリークに保有していた豪邸(2010年に売却)に関連して、ヘリコプター・ツアーに参加すれば見学できるという情報が出てくる。遊覧クルーズやヘリコプター・ツアーで外から眺めることしかできないこうした島であれば、きららは――そしてこの少女の報告に素材を提供したはずの作者自身は――、どうやって島内をのんびりと散策する日々を過ごし、氾濫する広告から身を守る必要から解放されて、「ずーっと長い時間、感じる能力を開いたまま」にする「快感」を味わうことができたのだろう。
そんな風に自問する「うさぎ!」の読者は、もしその人が2010年の「ひふみよ」ツアーに参加していたか、そうでなくても『我ら、時』(2012年)に収められたその記録に耳を傾けたことがあるなら、そこで朗読されたモノローグのひとつを思い出すことができた。「歌は同じ」と題されたこのモノローグでは、「スニーカーなんか、二回履いたら捨てるものだ、と言う」大金持ちのニューヨークの友人のことが語られている。「彼から見ると、毎日箱から出したてのフレッシュなスニーカーを履けない貧乏人なんか、かっこ悪い、かわいそうな存在だというのだ」、等々。なるほど、こうした富裕層の友人との交流が、第31話のエピソードを生み出したのかもしれない。わたしたちは、そんな風にぼんやりと想い描くことができた。2016年までは。
というのも、この年の初夏のツアー「魔法的」は、問題の島について、もはや憶測の余地を残さないだけの情報をもたらしてくれたからだ。このツアーで販売された書籍には、「愉しい広告」四部作と題して、「うさぎ!」第30話~第33話が収められた。そして全七曲の新曲のうちのひとつは、X島のエピソードに目配せするかのように、「冬のマイアミ」を舞台としていた。
冒頭の歌詞はこうだ――「リッケンバッカー橋を渡ると街はピンク色/着飾った友人たち お祝いのボトルをPOPしてくれる/本当に誕生するのはパパとママのほうで/少年と少女の存在はベイビーたちが続けていくよ」(「涙は透明な血なのか?(サメが来ないうちに)」)。リッケンバッカー・コーズウェイの先にあるキー・ビスケーン島は、独立した自治体となっている。「うさぎ!」第31話で引かれる看板規制の文言は、ウェブで公開されているこの村の条例(30節191項)の文言と一致する。となると、X島とはキー・ビスケーン島のことで間違いない。
さらにこの歌は、滞在の理由も教えてくれる。ここにあるのはウェディングの情景だ。出産を控えているらしい女性との結婚が、夫婦となる二人の「パパとママ」としての生まれ直しとして歌われている。思えば、小沢健二は、2012年のクリスマスに「妻の話」を公式ウェブサイト「ひふみよ」で公開し、結婚と妻の妊娠について明らかにしていた。だからつまりは、「冬のマイアミ」、より正確にはキー・ビスケーン島で挙式し、間もなくそのことをウェブサイトで報告する一方、この富裕層の住む島の印象とそれに促されての考察を、翌年春に雑誌掲載された物語で登場人物に託して語らせた、そして数年後のツアーで、それらすべてに立ち返ってみたというわけなのだろう。いずれにせよ、高級リゾート地として知られるこの島は、インディアン・クリークのように閉ざされた土地ではないのだから、ビヨンセの豪邸や小沢健二自身の大金持ちの友人のことをあれこれ考えてみたのは、わたしたちの無駄な思い込みにすぎなかったということになりそうだ。

しかし宇野維正『小沢健二の帰還』(岩波書店、2017年11月)の読書は、こうした漠たる想像が、まるっきり無意味でもなかったことを教えてくれる。本書によるなら(第三章)、2002年2月に5年4か月ぶりのアルバム『Eclectic』を発売したものの、いくつかの媒体を通してニューヨークから言葉少なに近況を伝えるにとどまったミュージシャンは、同年5月にはジェイ・Zの来日公演に同行し、ひそかに「日本滞在のアテンド」役を務めていたのだという。そして著者は、「一部の人々の間でまるで都市伝説のように語り継がれていくだけだった」この一時帰国のエピソードを、今では消滅した公式ブログを含む当時の発言と照らし合わせることで、「Jay-Zがいるような場所に出入り」していたパーティー・ライフの日々を浮びあがらせる。「史上最も成功したラッパー」にしてやがて実業家としても頂点を極めることになるこの「東海岸のヒップホップ界の顔役」は、当時から交際していたビヨンセと2008年に結婚するのだが、『フォーブス』誌が毎年発表する「最も稼いだセレブカップル」ランキングで何度も一位を獲得しているこの二人は、先ほど触れたように、インディアン・クリークに豪邸を構えたこともあった。小沢健二が「うさぎ!」の登場人物たちを通して展開する考察の背景には、結局のところ、近年の「基地帝国」での最大の成功者のひとりに数えられるジェイ・Zを含めた富裕層の生活実感に多少とも間近で触れることができた経験が、多少なりとも存在しているのだ。
しかもそれだけではない。『小沢健二の帰還』はまた、ジェイ・Zの来日公演に同行した2002年5月の直前、4月の小沢健二が、アルゼンチン――前年の経済危機以後の混乱のさなかにあった――とブラジルへの滞在について、今ではアクセスできない当時のブログに書き記していたことを教えてくれる。「ブエノスアイレスにいます。〔…〕何を考えているかというと、一つの国の経済状態がその国の人々の心理に及ぼす影響はすごいなあ、とかいう当たり前のことです。でもそれが本当に一個人の、全く個人的な感情とかに直結するのを目の当たりにすると、経済とか社会とかいう化け物のようなものをもろに感じるというか」(第四章に引用)……。他の情報と総合して著者が推測するところによれば、まさにこの頃から、ニューヨークを拠点とした間欠的な放浪の日々――中南米、アフリカ、アジアの諸国への――が始まったらしい。
おそらく当初から旅を共にしていたのだろう現在の妻、エリザベス・コールは――先ほど触れた小沢健二自身の紹介文に従うと――、プレップ・スクールからアイビー・リーグへという紛れもない米国エスタブリッシュメントの経歴を持ちつつ、有力メキシコ紙『ラ・ホルナダ』と契約した写真家・ジャーナリストとして、あるいはメキシコと国境を接するアリゾナ州の強硬な移民政策を告発し、あるいは、メキシコ麻薬戦争の凄惨な犠牲を訴える「平和のキャラバン」の米国入りを報じて、犠牲者の親族らがハーレムのアフリカ系・ラテン系コミュニティと警察の不当な暴力への憤りを共有するとともに、ウォール街での資金洗浄に抗議したのちズコッティ公園を訪問し、「人間マイク」による通訳を介してウォール街占拠の活動家らと交流する様子を、印象深く伝えてきた人だ(「妻の話」)。『ラ・ホルナダ』は、ウォール街占拠の運動が盛り上がった2011年秋の一連の報道で(たとえばナオミ・クラインの寄稿「世界で最も重要な出来事」、10月16日)、エリザベス・コールの写真を用いている。また彼女は『子どもと昔話』の連載では、写真に自分自身の言葉を添えて、「体で投票をしに来た」彼ら占拠者たちの動向を伝えている(50号、2012年)。
遠目には突然の動きのように見えたこの「オキュパイ」の運動の背景には、「うさぎ!」第40話と第41話(2015・2016年)で紹介される「ゼロ年代のDIYアクティヴィズム」があった。『装苑』2012年8月号掲載の「うさぎ!」番外編に登場する「アナキストの女の子」アナも、この流れに属するひとりだ。15歳のうさぎ少年と同様、小沢健二とエリザベス・コールの二人もおそらく、自ら本格的にコミットすることはないままに、この動きに与する多くの友人を持っているのだと思う。
ではこのコミュニティとその周辺の人間関係は、「Jay-Zがいるような場所に出入り」する人びとの世界と、どの程度重なりあっているのだろう。これらは、ただ小沢健二ひとりの存在によって偶然つながっただけの二つの独立した宇宙なのか、それとも、もう少し相互に浸透しあうところがあるのか。それはわからない。けれどもこうして、少なくとも、「うさぎ!」の連載や「ひふみよ」掲載の文章を熱心に読み、そこで得たものを『小沢健二の帰還』の読書によって補完するならば、わたしたちはわたしたちの音楽家が、1997年暮れから翌年初めにかけての時期にニューヨーク住まいを始めてわずか数年のあいだに、この大都市をいかに濃密に、複雑に、重層的に生きることができたのかを、たしかな手触りをもって感じ取ることができる。
「ミュージシャン、作文家」に立ち向かう音楽ジャーナリスト
言うまでもないことだが、地上波キー局へのテレビ出演によって事柄の軽重を判断するたぐいの文化的感性と無縁な人びとの少なからずは、19年ぶりのニューシングル『流動体についてc/w神秘的』の発売が告知されただちに店頭に並び、畳みかけるようにメディア露出が展開された2017年2月以前にあっても、21世紀における小沢健二の存在と活動を、持続的ないし断続的に意識に浮上させながら日々を過ごしてきた。しかし『小沢健二の帰還』は、20年近い「空白期」における小沢健二の現前を、最も切実に感じてきた人びとのうち2人によって生み出された書物だ。本書を縁取る「はじめに」と「おわりに」の両方に登場する渡部朝香は――最近は「WEBRONZA」で書評家としての才能を発揮してもいるこの編集者が、担当書のひとつの帯に「眩い筆致で綴られた、魔法的な街の記憶」(福嶋伸洋『リオデジャネイロに降る雪』、強調引用者)との文言を踊らせているのを見るだけでも、傾倒の深さは推察されるけれど――、「今回は小沢健二の活動全体に関する知見と理解が、他の編集者とまったく違っていた」(はじめに)という感嘆を引き出すことで、他の出版社からの打診には応じなかった著者を執筆へと導いた。そして本書の著者、宇野維正はと言えば、「音楽業界でも仕事をしながら、自分で自分に呆れるくらいただの「小沢健二ファン」となっていったこの十数年間」(おわりに)を過ごした結果、「少なくとも文章を書くことを仕事にしている人間で、自分ほど熱心に、継続的に、小沢健二の言動を追いかけ続けてきた人間は他にいないはずだ」(はじめに)と断言できるだけの知見を得るに至った音楽ジャーナリストだ。
「音楽家であるだけでなく、卓越した言葉の表現者」でもある存在(はじめに)、あの素晴らしい『アイスクリームが溶けてしまう前に』(小沢健二と日米恐怖学会、福音館書店、2017年9月)刊行後は「ミュージシャン、作文家」と称し、書くことが自らの活動の不可欠の一側面であることを強く打ち出すようになった小沢健二について本を書くこと。これはなかなかに覚悟を要する企てであるにちがいない。「僕はその、例えば東大文学部卒とか、そういうプロフィールとか必ず出てるんだけど、それは別物で「いやぁ東大なんか関係ないよ」っていうのでやってないんですね。もうメッチャメチャ東大文学部卒のそのまんまでやってんですよ」(『TK MUSIC CLAMP』、1995年5月17日)――かつての彼はこのように語ったものだが、ここに読み取るべきはもちろん学歴自慢ではない。ここでは「東大」にもまして「文学部」が重要なのであって、つまりこの発言から窺えるのは、この傑出した音楽家にとっての「文学」の価値の重みだ(なお大学時代の充実した勉強ぶりについては、『レ・スペック』1992年11月号掲載の柴田元幸との対談を参照のこと)。じっさい小沢健二は、久しぶりのテレビ出演のひとつで初期の音楽活動について、「そもそも文学が好きでそれの出し口が音楽になって〔…〕」と振り返っている(『バズリズム』、2017年3月10日)。今日の彼が「ドゥワッチャライク」と「うさぎ!」という新旧の連載作と並び、自らの代表的「作文作品」として挙げる「赤い山から銀貨が出てくる」(『モンキー』第6号、2015年)はぜひとも読まれるべき驚きを秘めた傑作だけれど、ある意味では「音楽作品」を含めた活動の全体が、小沢健二というひとつの文学的事件を構成しているのだ。そんな存在について本を書くこと。なるほどこれは、「もし勝ち負けで言うなら、絶対に勝てる見込みのない勝負に挑むようなもの」(はじめに)というほかない。そしてもちろん『小沢健二の帰還』の著者は、「作文家」の仕事に文章の力において匹敵する本をつくろうなどという野心に駆り立てられて、執筆を引き受けたのではなかった。
音楽ジャーナリストを突き動かしたのは、別の野心である。宇野維正は、最初の著書となった『1998年の宇多田ヒカル』(新潮新書、2016年1月)においてすでに、「ミュージシャンの肉声」重視の音楽ジャーナリズムのありかた――それはかつて彼自身が社員として過ごした、ロッキング・オン社が打ち立てた伝統だ――を相対化する必要性を説いていた。なぜなら、「「語られなかったこと」と「訊かれなかったこと」に興味深い真実が隠されている」からだ。続く共著『くるりのこと』(新潮社、2016年9月)は、バンドのメンバーと「親しすぎない」という利点を活かし、「客観性と相対性」を保ちつつ行われたインタヴューの記録である。アーティスト自身の言葉に丹念に付き合いながらも一定の距離を置き、緊張感をもって、ゴシップの低俗性に陥らないよう配慮するのは当然としてもしがらみにとらわれることなく、実像を浮びあがらせていくこと。このような姿勢を貫いている音楽ジャーナリストにとって、小沢健二の「空白期」の探究が、このうえなく取り組みがいのある企てに思えたのは当然だろう。その成果の判断は、個々の読者に委ねられている。しかしおそらく、以後、小沢健二が紡いできた言葉に向き合おうとする最も熱心な試みも、本書を無視することはできないだろう。本稿のこれまでの叙述は、そのことを証明しえていることと思う。
『Eclectic』をどう聴くか
読者は本書のページをめくりながら、あるいは自分自身の小沢健二体験の記憶をたどり直し、あるいは著者の記述に促されて新たな探究に乗り出す。思いもかけない指摘に新たな認識を得ることもあれば、以前からの理解を確認し深化させることも、さらにまた、時には、解釈の相違に行き当たることもあるだろう。たとえば本稿の筆者の場合、『Eclectic』――最も好きなアルバムである――について、「底なしの孤独感、深い喪失感」(第二章)を強調する本書の観点には、半分しか同意することができなかった。ということはつまり、半分は同意しているわけであって、じっさい、この作品のなかに「いくつかの喪失」を、そしてとりわけ「9・11の影」を読み取るときの著者に反対することなど、誰にもできないだろう。
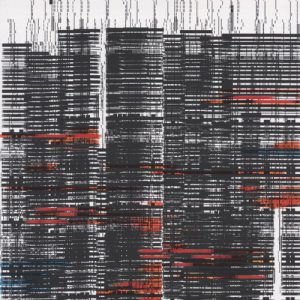
しかし『Eclectic』全編を貫く官能の手触りは、深い憂鬱の気配に伴われてはいても、あるいはそれゆえにかえって、生のこのうえなく力強い肯定の響きを感じさせる。そのこととも関わるけれど、本作にあって愛の官能的・肉体的次元が思い切り強調されているのはたしかだとしても、追求されているのはやはり愛なのであって、官能のきらめきはここで、刹那的な快楽の地平にとどまっているのではなく、むしろ未来へと続く何かであるように思われるのだ。作中で「あなた」が「穢れのない魔法使い」と呼びかけられ(「麝香」)、「神様」の導きにより知り合った「あなた」の「大きな心」が歌われて、「その輝きにつつまれた」自分自身が想い描かれる(「今夜はブギーバック/あの大きな心」)のを見るなら、ここにはやはり――わたしたちの音楽家の198歳年長のドイツの詩人だったら、「おお、あなた、天の使い」(ディオティーマ頌歌のひとつ)とでも呼びかけそうな勢いが感じられるのであって――、ある決定的な出会い、未来への扉を開く運命的な出来事を想像したい気持ちになる。じっさい、「あなた」の瞳から発せられる「軽い衝撃波」を受けて、歌われるのはこうした言葉だ――「1つの魔法を あなたに返すよ/値段のないおくり物/それは 未来への魔法」(「1つの魔法(終わりのない愛しさを与え)」)。
少なくとも本稿の筆者は、2002年以来ずっと、この美しい作品をこんな風に聴いてきた。そして『小沢健二の帰還』の読書によって、アルバム発売直後の南米旅行――おそらくは未来の妻に伴われた――について教えられた今、『Eclectic』の最も素朴で単純で、たぶん美しい聴き方は、「9・11の影」のもと、世界各地への放浪生活を始めるに先立って、これらの旅の――そして今後の人生の――パートナーとなるエリザベス・コールとの出会いを作品化したものとしてそれを聴くことだと考えている。もちろん、実際のところはわからない。人生の成り行きは必ずしもつねに、素朴で単純で美しい解釈に適ったものではないのだから。しかしいずれにせよたしかなのは、『小沢健二の帰還』が、著者の主張に全面的には同意しない場合にさえ、読者が自分なりのやり方で小沢健二を聴き、読み、理解していくための有益な対話相手となってくれるということだ。本書がこの類まれな「ミュージシャン、作文家」に関心を抱くすべての人の手元に置かれるべき著作である所以だ。
「こうじゃない世界」の可能性と実在
ともあれ、こうして始まった放浪の日々のなか、「うさぎ!」の連載が開始され(2005年秋)、またエリザベス・コールと共同で製作した映画『おばさんたちが案内する未来の世界』の上映の集いが、日本各地で持たれた(2007年)。そこで説かれたのは、一方では「灰色」の支配の執拗さと巧妙さであり、しかしまた他方では、そこから逃れ去ることの可能性、とりわけ南米諸国の経験を通して生き生きと感じられる、「こうじゃない世界にできる」(「小沢健二に聞く」、「ひふみよ」2010年1月19日)という変化への予兆だった。こうした活動はたしかに、「間違い」(「流動体について」)に気づいて日本を離れた小沢健二が、渡米後に獲得した新たな認識なしでは可能にならなかっただろう。
けれど、「やっぱり小沢健二さんなんだよなー」とうさぎはつぶやく。彼を主人公として書き継がれる一連の物語は、「以前の音楽とか書き物とかと、明らかにつながっているというか、完全に一体のもの」だというのだ(第22話、本書第五章に引用)。以前の書き物とは何より、『オリーブ』の名物連載だった「ドゥワッチャライク」(1994~1997年)を指しているが、『我ら、時』(「通常版」ではないほう)に収録されたこの連載の抜粋版を、同時収録の「うさぎ! 2010-2011」と読み比べるなら、少年の印象の正しさがただちに実感される。「昼日本」と並行して存在する「夜日本」の伝説のうちに、「くつろぎのコックピット」を形成し「一人の世界」に入り込む人びとや自ら「人間コックピット」と化す人びとのうちに、「本に載せる服の値段の上限」を設定することで「今が勝負! 今年のシャネル!」、「ぜったい欲しい! 春のプラダはお嬢さまセクシー!」といったたぐいのコピーを自らに禁じ、それらの代わりに「見つけたよ、春のジーンズ・スタイル」と表紙に書く『オリーブ』のうちに、1990年代の小沢健二は「こうじゃない世界」の手触りを感じ取り、熱っぽく読者に伝えようとしていた。こうした感性が、渡米後の知見の広がりをはるかに準備するとともに、今日の「帰還」のたしかな基盤ともなっている。だからこそ小沢健二は、「新しい友人たちだけでなく、「うさぎ!」を通じて古い友人たちと新しい気持ちでまた会えたこと」(「うさぎ!」第26話、本書第四章に引用)を、喜びをもって確認することができたのだと思う。
2003年夏のアメリカ北東部大停電の経験を振り返って――『災害ユートピア』(亜紀書房)のレベッカ・ソルニットはこの時の人びとの助け合いのうちに、「地獄から入るパラダイス」のひとつの例を認めたのだったが――、「ひふみよ」ツアー(2010年5・6月)のモノローグではこのように語られた。「いつも同じ感じで進んでいく世の中で、ある全然ちがう世の中が見える。一瞬だけ、全然ちがうぼくらのありかたが見える。明日は電気が復旧して、また、元の生活が帰ってくる。けれど、今夜だけは、ぼくらは全然ちがう世界で時を過ごす。そして、元の生活に戻っても、世の中の裂け目で、一瞬だけ見たもの、聞いたものは消えない」(「闇」)。もちろん「こうじゃない世界」は、ただ災害のような出来事によってひととき現出するばかりではない。「世の中の裂け目」は、普段の生活のただなかにも、そこここに見え隠れしている。ただ人びとがそれに気づかないか、気づこうとしないだけだ。「そう、世の中の裂け目、あるんですよ。意外なところに」(「東京の街が奏でる」、「ひふみよ」2011年11月29日)。小沢健二は、それらの裂け目を、また、「引っ張ったら世の中がほどけ」(同)そうなほつれ目を見つけ、ここにある、ほら、あそこにも、と指し示すために、わたしたちのもとに帰ってきた。「時間軸を曲げて」。
![Read more about the article 【連載】ノン・エクスクルシーブ・ニューヨーク[第2回]/大崎晴地](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2023/10/31.jpg)

![Read more about the article 【連載】誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[第4回]前編/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2022/12/p-1-90657615-how-the-olympics-ruin-cities.webp-1-768x512.jpeg)