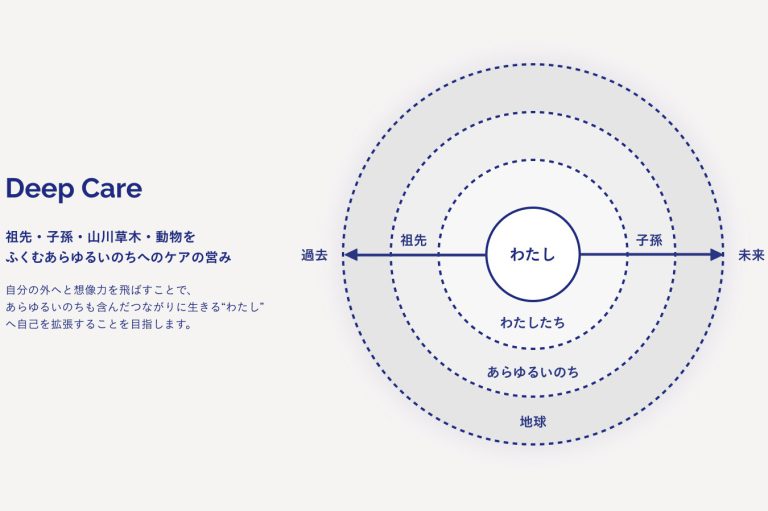戦争から脱走する
サンドロ・メッザードラ
2022年3月11日(http://www.euronomade.info/?p=14889)
北川眞也訳

ウクライナで戦われているのは——民間人に対する破壊的影響を万人が目にしている——、紛れもなくヨーロッパの戦争である。プーチン体制内で影響力を増す「保守革命家」アレクサンドル・ドゥーギンの「ユーラシア」論が、文化的かつ「地政学的」な観点からロシアを自立空間と設定していようとも、ロシアはヨーロッパの切っても切れない一部分である。無論、それは独特の流儀においてのことだ。歴史叙述上の有名なテーゼにしたがえば、18世紀以来、ロシアはヨーロッパの「自意識」を表している。それは、ヨーロッパを定義する行為が、境界空間(spazio liminale)——ヨーロッパの発展の内部にあると同時に外部にある空間——として理解されたロシアをおのれの映し鏡として設定してきたという意味においてだ。ロシア革命自体がこの境界空間に起源を有していたと言える。つまりボリシェヴィキは、たとえロシアの状況の独自性を自覚し、反植民地的蜂起を推進する必要に駆られて東方へと向かったとしても、西洋をみつめていたのだと。いずれにせよ、ロシアの位置は、ヨーロッパにとっては潜在性(virtualità)の一要素をなす。この要素は、ヨーロッパの自己定義、具体的に言えば、ヨーロッパの境界と境界をめぐる政治を規定する力学とをオープンなものとして保つよう迫るものだ。この潜在性という要素こそ、プーチンの戦争が消去しようとするものにほかならない。それゆえにこれが、この戦争にあらゆる手段を尽くしてわれわれが反対せねばならない第一の理由である。
けれども、ウクライナでの戦争がヨーロッパの戦争であると一旦主張したなら、以下を付け加える必要がある。この戦争はヨーロッパの戦争というのみには限られない、と。むしろ逆である。こんにち問題となっているのは、まさしく「世界秩序」にほかならない。とはいえ、この世界に秩序はほとんどない。90年代には「新しいアメリカの世紀」の出現が広範に信じられ、それが多国間的であると同時に帝国的でもあった建築構造〔アーキテクチャ〕の設計を支えたのであれば、続く9.11以後のゼロ年代には、「対テロ世界戦争」によってアメリカの単独行動主義を主張する企てが、イラクとアフガニスタンでの軍事的苦境(と後の敗北)をもとに粉砕されたのだった。その一方で、2007/8年の金融危機がアメリカの経済的支配力とその全世界への〔グローバル〕投影のありようを大きく揺り動かし、中国の台頭、さらには「世界の工場」からデジタル技術・知識経済・人工知能の領域での潜在的リーダーへと向かう中国の移行を加速させた。2013年に提唱されたとはいえ、その後しばらくの間に準備された「一帯一路」という大規模なロジスティクス計画は、こうした意味で、国内で起こる移行を拡張していく動き、つまり、中国特有のグローバル化プロジェクトを体現するものなのだ(習近平によって、多国間主義の視座からこの用語が頻繁に用いられ、擁護されているのは偶然ではない)。こうした枠組みのなかで、アメリカの世界的覇権の危機——世界システム論の理論家たちが90年代に描写しはじめていた事柄——が、安定の欠如と戦争を蔓延させるにつれて、グローバルな行く末を見通すための基本的主題となった。この危機的情勢の基本的特徴を把握しようとするなかで、「遠心的多極性(multipolarità centrifuga)」や「対立的多極主義(multipolarismo conflittuale)」のような定式が近年広く流通しているわけである。
こうした状況の推移のなかに、ロシアはどのように身を置いてきたのか? 要約すれば、エリツィンによる激しい新自由主義改革の年月に引き起こされた正真正銘の本源的蓄積に基づいて、ロシアでは「政治的資本主義」のある独自の形態がしだいに姿を現してきたのだと言える。別様に言えば、政治権力がレント収入(主として原材料に基づいた)を保証し、比較的限られた経済的アクター——それゆえに、まさしく「寡頭制〔オリガルヒ〕」と呼ぶことができる——の範囲に、その独占権を配分する一方で、このレント収入自体の一部が、合意を調達するために、住民へと振り分けられるというわけだ。同時に、政治的資本主義のこの種別的形態(当然とりたてて動態的でもないし、革新的でもない)は、ロシアの諸境界のみならず、シリアやリビア、サヘル地域における戦争と軍事介入(「ワグナー・グループ」として知られる民間軍事企業を通じても)でも近年みられたように、軍備拡張でも同様の種別的形態を生じさせている。ここに、ウクライナでの戦争を理解するための鍵となる要素(また必要なあらゆる手段を用いて戦争に反対する第二の理由)がある。つまり、プーチン時代に具体化した「政治的資本主義」の強化および膨張である。それは拡大を必至とする空間の内側でなされるとはいえ、寡頭制の一員〔オリガルヒ〕の多くがグローバルな視座に立ってかれらの活動範囲を拡大しており、プーチンの戦略と客観的には緊張状態に入っているのだ(結局のところ、かれらはますます「寡頭制的」ではなくなり、ジェフ・ベゾスやイーロン・マスクのような資本主義的アクターにますます類似するようになっている)。その結果、ロシアをはじめとする国家からすれば、国家とは別の名で呼ばれうる別種の資本主義的利害との間に激しい矛盾が生じているのであり、それがこの数週間に生じていることの背景にあるのは確かである。だがこの視角からすれば、衝突は必然的にグローバルなものとなる。とりわけ、中国を巻き込むものとなる。中国はたとえ多くの面でロシアと結びついているとしても、おのれの経済的支配力の対外的投影のありようと国際関係のマネジメントという視座からみれば、ロシアとはまったく異なる戦略を有している。
これについては、さらなる論点が明示されねばならない。新型コロナウイルスのパンデミックは、今一度、「グローバル化の終焉」への礼賛を広めるための好機だった。この説についての十分な議論は、別の機会に先延ばししても問題はなかろう。むしろここで強調に値するのは、戦争が地球規模での〔グローバルな〕相互依存の深さを、基本をなす主題として浮かび上がらせてきたことにある。原材料(穀物、エネルギー源、鉱物など)の市場について考えてみるとよい。そこは完全な金融化がなされるとともに、中長期契約を中心にした編成となっており、輸出向け資源の国内利用への転換を実質的に不可能としている。世界の主要小麦生産国のひとつであるアルゼンチンでの小麦粉価格の30%の上昇は、この意味において典型的な一例となろう。ロシアへの経済・金融制裁をめぐる同様の事態は、それゆえに非常に重大な意味を持つのだ——一方では、この制裁自体が制裁を実行する当の国々に及ぼす影響(と、その結果、特にエネルギーの面で引き起こされる西洋内部の分裂)のためである。他方では、明らかに意図してではないにせよ、以前から進んでいる「脱ドル化」(人民元中心の新たな通貨連合の強化とともに)と、スイフト・システム〔SWIFT、国際銀行間通信協会〕に代わる銀行支払い回路(中国の類似のシステムはCIPS〔人民元国際決済システム〕と呼ばれる)の形成過程とに与えられる刺激のためである。この視点からみても、中国が中心的な位置を占めているのは明らかだ。中国は「デカップリング」、つまり西洋の経済・金融システム(とりわけヨーロッパでの利益を考えれば)からの分断という展望には非常に慎重な態度をとっている。その結果、客観的な水準においては、中国は戦争を終結させる上で極めて重要な役割を果たしうる位置にいるわけだ。中国がそのように決断するかどうかは、また別の問題であるが。
ここまで政治的、特に経済的力学にかんする視点から、戦争を分析する要素をいくつか提出しようとしてきたとすれば、今度は別の視角——「上部構造」などでは些かもない——を導入する必要がある。イリヤ・ブドレイツキーは、ヴァーソ(Verso)社から最近出版された著書(Ilya Budraitskis, Dissidents Among Dissidents. Ideology, Politics and the Left in Post-Soviet Russia, 2022)の第1章を「プーチンはハンチントンによって構築された世界を生きる」と題している。ここで言及されているのは、もちろんサミュエル・P・ハンチントンであり、『文明の衝突〔原題:文明の衝突と世界秩序の再形成〕』(1996)である。この著書の基本テーマが思い起こされる。それは、現存する社会主義の終焉後、グローバルな水準での対立線は、「文明」(特に宗教が重要な役割を果たす)の間に走ることになろう、というものだ。ブドレイツキーの議論は単純である——ハンチントンの著書は、こんにち先見の明があったかのように思われるかもしれないが、それはこの著書が特別な分析力を有していたからではない。『文明の衝突』は一種の政治的・イデオロギー的マニフェストだったのであり、影響力のあるアクターたち(ジョージ・ブッシュからアブー・バクル・アル=バグダーディーまで)がそれを実践へと翻訳しようとしてきたからなのである、と。こうしたアクターのなかでも大御所的存在なのが、ウラジーミル・プーチンなのだ。ブドレイツキーは、プーチンを「ハンチントンの優等生」と定義する。プーチンによって実践される種別的なアイデンティティの政治は、伝統的な家族・宗教・「諸価値」を、安定と秩序の防波堤として強迫的に繰り返し提示することで、実際にロシア「文明」という神話の輪郭を描き、固めることを目標としている。このイデオロギー的構築物は、プーチンとロシア支配階級による政治の鍵となる要素である。同性愛とフェミニズムの悪魔化、ひいては家父長制への正真正銘の称賛が、ロシア正教会のキリル総主教の言葉にみられるのは驚くべきことではない。ウクライナでは「ゲイ」に対する戦いが行なわれているのだ、と。われわれがここに、プーチンの戦争に反対する三つ目の理由を見出すのは言うまでもなかろう。それは何より、ロシアでプーチンとかれの「文明」と戦っている女性、男性を支援する(もう一度言えば、必要なあらゆる手段を用いて)ためでもある。だが、ここに何かしら付け加える必要がある。ブドレイツキーがさらに書き記すように、文明の衝突は、ヨーロッパに、西洋に「鏡面反射」を生じさせているのだ。3月9日の『コッリエーレ・デッラ・セーラ』紙に掲載されたフェデリーコ・ランピーニの記事〔なぜ西洋はプーチンの侵略に備えてなかったのか?〕を読めば、その見事な例証を得られよう。
とはいえ、ウクライナでの戦争が西洋を団結させた、次は自らのアイデンティティを強化せねばならないと主張する人びとの声が広まっている。ここで西洋という捉えにくい概念の歴史を遡るつもりはない。冷戦終結後の年月について簡単に言及しておけば十分だろう。90年代の情勢下では、西洋はアメリカという議論の余地なき指導者を有していた。「孤独な超大国」——たびたびそう呼ばれていた——は、対ロ関係に多大な経験を持つ外交官たち(ソ連に対する「封じ込め」政策の創案者であるジョージ・フロスト・ケナンのような)からの節度を求める訴えには聞く耳を持たなかった。アメリカはむしろ、「新しいアメリカの世紀」への自信に酔いしれ、NATO〔北大西洋条約機構〕の東方拡大へと向かった。客観的にみれば、この動きはロシアを包囲する結果を招くこととなった。このプロセスのなかで、数多くの旧東側の国々(バルト三国からポーランドまで)が果たした役割については長く議論することができるだろう。事実上こうした国々は、EUへの加盟を、NATOへの加盟に伴う副次的なものとして経験することになったのだ。さしあたりNATOの東方拡大は、現在とはまったく異なる情勢下——アメリカがおのれの経済的、政治的、軍事的、文化的、さらには道徳的ですらあった優位性に自信を持っていた——で起こったことだったと強調しておけばよいだろう。NATOの東方拡大は、ロシアとの緊張を高め、軍縮の交渉をとりわけ困難なものとした。なんなら当時は、1975年にヘルシンキで開催された会議をモデルとして、新たな全欧安全保障協力会議について検討する必要があった時機だったのだ。けれども、ここ数十年の間、NATOは外交政策でのヨーロッパの独立性を不断に束縛する存在であり、ヨーロッパの領域を不断に軍事化する装置に相当するものでもあった。プーチンの戦争にあらゆる手段で反対せねばならない3つの理由を明示してきたが、ここでわれわれは以下を付け加えるべきだろう。われわれにとって、NATOは問題の一部をなすものであり、解決策の一部となるものではない、と。
その一方、少なくとも朝鮮戦争の時代以来、「西洋」はもはやヨーロッパ・大西洋という地理的範囲には限定されていない。周知のように、近年では、アメリカの政策におけるグローバルな軸は、インド太平洋地域へと移動しており、AUKUS(オーストラリア、イギリス、アメリカ)や QUAD(インド、アメリカ、日本、オーストラリア)のような頭字語で略される、対中国用の新たな同盟体系を設けることに狙いを定めてきた。それゆえに、インドがウクライナでの戦争について、実質的にロシアを支持する立場をとったことには重要な意味があるようにみえる。インドは国連での戦争非難決議の投票を棄権したのである。とはいえ、これは過剰に評価すべき事柄だというわけではない。インド——モディ現大統領は、簡単に言うなら「ヒンズー・ファシズム」と定義できる立場をとっている——は、歴史的にロシアとの協力関係にあるし、QUADの特徴は、「安全保障をめぐる対話」であり、完全なる軍事同盟ではない。けれども、インドを取り込むことは、バイデン政権の戦略上、必須の要素であると思われていた。トランプ政権とは違って現政権は、その発足時から、グローバルな関係性システムの一部であることに自覚的な西洋を(再)構築するという展望で動いてきたのである。したがって、インドの姿勢は、こうした戦略の変化の兆候として解釈することはできる。トルコ、イスラエル、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(特に後者二国は、石油の問題に関わる)のような国々がとった立場を踏まえるなら、それは重要な意味を持つことになろう。ここに見て取れるのは、グローバルな構築物としての西洋なるものには、本質的に壊れやすい要素があるということだ(当然、われわれに近い諸集団による行動から生じるものではないが)。これは、自由と平等を求めて戦う運動と勢力によるグローバルな政治を(再)構築することを目指す——私は必要不可欠な事柄だと考える——のであれば、考慮に入れておくべきファクターである。
このような運動と勢力について最後に簡単に述べておきたい。こんにち、反戦の闘いはまずもって、投獄と死の危険を犯して、ロシアとウクライナの諸都市の路上でデモを行なう人びとによってなされている。それから、戦争から脱走して、その論理を拒否し、安全と思われる場所へと逃亡する人びとによって闘われている。だが、ヨーロッパをはじめ世界各地でデモに参加する何万の人びとによっても闘われている。もちろん、そのパースペクティブは様々であり、たびたび対立することもある。「プーチンとでもなく、NATOとでもなく」、「抵抗するウクライナの人びとに武器を」。後者のスローガンは特に、強硬路線の政治家やジャーナリスト、軍国主義者のコメンテーターや熱狂的戦争ファンによってのみ支持されているだけではない。われわれに近しい人びともまた支持していた。当然、イタリアにいるウクライナ人ディアスポラ(ヨーロッパで最も多く、ケア女性労働者をはじめ無数の人びとがいる)の間でも広がっている。私の考えでは、これは支持すべきスローガンではない。問題は原則ではない。戦争拡大を阻止するために、あらゆることをなさねばならないという事実の認識こそが大切だ。交渉の空間を開き、増殖させなければならない。反戦運動は、この意味において、重要な役割を果たすことができる。それは何よりもまず、「下からの外交」を実践し、支援物資を送って援助を提供し、難民の逃走を手助けして出会いの空間を拡大することによってである。
その一方で、〔戦争の〕初期の局面では理解できるものだとはいえ、こうしたスローガンの曖昧さと袂を別つことが必要である。無論、われわれは反プーチンである。NATOは問題の一部であって、解決策の一部になるとも考えない。けれども、この戦争の背景をなす、国際秩序および無秩序の再定義という混乱を極めるプロセスのさなかでは、われわれは思い切ってそれ以上のことをなさねばならない。2003年2月15日にグローバルな規模で行なわれた巨大なイラク反戦デモの後、『ニューヨーク・タイムズ』紙は、平和運動(シアトル、ポルトアレグレ、ジェノヴァをバックグラウンドとした運動)は、「世界で二番目のパワー」であると書き記した。当時、われわれはこの定義を批判した。というのは、この定義が運動を「オピニオン」へと封じ込めてしまうものだったからだ(いつも通りの明晰さでベネデット・ヴェッキがそのように書いていたことを思い出す)。こんにち、これを思い返すのなら、それは挑戦としての意味を持ちうる——つまり、われわれが生きるこの「ぞっとするような」時代に応じた勢力、パワーを創出するという挑戦にほかならない。パンデミックの間にこのことについて検討した人が、われわれの間には多くいる。パンデミックに戦争がほぼ途切れることなく連結した今、これはよりいっそう重要となる。もちろん、グローバルな政治を必要とするまた別の問題——まず気候危機——が消え去ったわけではない。戦争が加速させる再軍備の趨勢もグローバルであり、欧州軍の創設が議題に上っている限り、それはヨーロッパの財政政策自体に多大な影響を与えることになろう。戦争から脱走することは、こんにち有無を言わせぬ命令=責務であるが、脱走の実践は、グローバルな枠組みに関連づけられなければ効果的にはなりえない。机上では実現不可能な新たなるインターナショナリズム——別名で呼ぶこともできようが、グローバルな政治を求める精神と結びついたものでなければならない——によって支えられなければ。数日前に、ロシアから、ウクライナから、「新たなツィンマーヴァルト」の開催を求める訴えが届いた。1915年9月、戦争に反対の立場をとる社会主義者たちが、スイス・ツィンマーヴァルトで開催された会議に集まったのだ。ロシアとウクライナからの訴えは、この精神を受け継ぐ会議の開催を求めている。この訴えがどれほど具体的であるかはわからない。こんにちの状況が、一世紀前とは完全に異なっているのも確かだ。それでも、これは強力な提案であり、聞き流されてはならないものである。
著者紹介
サンドロ・メッザードラ(Sandro Mezzadra)
1963年生。ボローニャ大学教員。現代政治理論、社会理論。ポスト・オペライズモを牽引する知識人として、マルクスやポストコロニアル研究からグローバル資本主義の批判分析に取り組む。翻訳に『逃走の権利——移民、シティズンシップ、グローバル化』(北川眞也訳、人文書院、2015年)、『方法としての境界(仮)』(ブレット・ニールソンとの共著、北川眞也、箱田徹、平田周、前田幸男訳、共和国、近刊)、『金融危機をめぐる10のテーゼ——金融市場・社会闘争・政治的シナリオ』(アンドレア・フマガッリとの共編、朝比奈佳尉、長谷川若枝訳、以文社、2010年)など。
訳者紹介
北川眞也 (Shinya KITAGAWA)
1979年生まれ。政治地理学、境界研究。博士(地理学)。三重大学人文学部准教授。主な著書に『惑星都市理論』(「惑星都市化、インフラストラクチャー、ロジスティクスをめぐる11の地理的断章——逸脱と抗争に横切られる「まだら状」の大地」、平田周+仙波希望編、以文社、2021)。主な論文に「地図学的理性を超える地球の潜勢力——地政学を根源的に問題化するために」(『現代思想』第45巻18号、青土社、2017)、「ロジスティクスによる空間の生産——インフラストラクチャー、労働、対抗ロジスティクス」(原口剛との共著、『思想』1162号、岩波書店、2021)など。