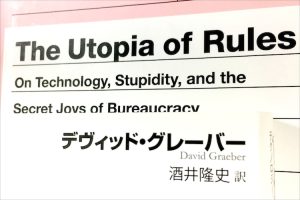人間狩り・奴隷制・国家なき社会
──シャマユー、ミシェル、そしてクラストル
酒井隆史 × 中村隆之 × 平田周
第3回
「ピエール・クラストル/国家をもたぬよう社会は努めてきた」

中村 さて、ここまでお話してきた2冊の書物『人間狩り』と『黒人と白人の世界史』と同じタイミングでもう1冊、ピエール・クラストルの『国家をもたぬよう社会は努めてきた』(洛北出版、2021年)という本が出版されました。本日のゲストの酒井さんが訳された本ですが、こちらの本についてもこの機会にお話ができれば、と思います。
この本の前半部は、クラストルへの1974年のインタビューが基本テキストになっています。インタビュアーであるミゲル・アバンスールの長文に、クラストルのインタビューが続き、さらにその後に、この本の半分くらいを占める酒井さんの解題があります。
ピエール・クラストルに関しては、渡辺公三さんが訳した『国家に抗する社会』(水声社、1989年)が主著になるかと思いますが、クラストルをいまどう読み直したらよいのかを考えるにあたって、今回出版されたこの本が、現代的な課題としてクラストルの仕事を位置付ける入門書として、おそらくもっとも適した本だと言えると思います。少し前には『政治人類学研究』(原毅彦訳、水声社、2020年)という本も翻訳がようやく出ましたが、それに続く待望のクラストルの書籍の出版ですね。
私はこの本を読んで、酒井さんのご関心のひとつにもつながる話だと思いますが、非常に面白かったのがホッブズの問題系についてです。「なぜ、われわれは国家を持つようになったのか」というとき、ヨーロッパではホッブズの考えた人間社会の「自然状態」という見方が非常に根強い。それは、「自然状態」では、みんな互い互いに怖れあう、という人間観です。「怖れあうからこそ、戦争になるのだ。だからルールをしっかりとつくる」と。そこで近代法や国家が必要になる、という説明の仕方をホッブズはします。
実は、この捉え方は非常に特殊ヨーロッパ的なものであって、ほかの社会を説明する普遍的な装置ではないのだ、とクラストルは言います。国家や社会のあり方には、もっと別のやり方がある、という社会認識です。クラストルは、インディオと一緒に暮らすなかで、ホッブズ的な国家が生まれないようにして成り立っている社会共同体を学びます。
ホッブズ的な人間観については、酒井さんもご著書(『暴力の哲学』)のなかで触れられていて、そこから反暴力のありかを探求されていたと思いますが、『暴力の哲学』では、クラストルの話は直接は出てきませんでした。それが時を経て今回の本でしっかりとつながったことが興味深かった。
平田 私は酒井さんがこれまでに書かれてきたものは(論文単位でも)かなり追ってきたつもりでしたが、酒井さんの翻訳と解説によるクラストルの本が出ることを知って少し意外な気がしました。しかし、たしかにアンチ・ホッブズという点で、酒井さんのモチーフとしては連続していますよね。実際、読んでみると中村さんがご指摘されたように、間口が広い入門書で、一から説明もしてくれていますが、読み進めていくとかなり奥深いところまで誘われる本でもあります。
以前、シャマユーの『ドローンの哲学』を訳された渡名喜さんを中心に、クロード・ルフォールの『民主主義の発明』(勁草書房、2017年)の翻訳に参加したことがありますが、ルフォールは、コルネリュウス・カストリアディスとともにジャーナル『社会主義か野蛮か(Socialisme ou barbarie)』を刊行したあとに、クラストルやミゲル・アバンスールらとともに、『リーブル(Libre)』というジャーナルを創刊しています。この文脈において、酒井さんが書かれている文章を読みながら、フランスにおける「政治的なもの」の哲学の開始段階で人類学との協働が強くあったことの意味は、もっと振り返られていいことだと思いますね。
また、ドゥルーズ&ガタリの『千のプラトー』でのクラストル批判についても、ラ・ボエシ解釈を足場にして、今回の本でいくつかの重要な争点を示してくれています。自分の周りを見ても、クラストルを熱烈に好きな人は多いですが、ドゥルーズ&ガタリからの批判を通したあとで、どのようにクラストルを取り上げるかにまで至る人はなかなか出てきませんでした。そういったなかで、ようやくこの本で風穴が空いたと思いますので、議論が進んでくれることを期待しています。
酒井 ありがとうございます。『国家をもたぬよう社会は努めてきた』の解題で、もう少し触れたかったけれど結局できなかったのは、ルフォールとクラストルの関係なんですよね。解題では彼らの関係にはほとんど言及していないのですが、『社会主義か野蛮か』のメンバーのうち、おそらくカストリアディスはクラストルの影響をほとんど受けていないと思います。ただ、ルフォールにはかなりあって『エクリール』(宇京頼三訳、法政大学出版局、1995年)という本のなかに比較的長いクラストル論があるのですよね。ただちょっと読むのはしんどいのですが。
ピエール・クラストルという人はきわめて重要な人類学者かつ思想家であり、グレーバーとウェングロウの共著『The Dawn of Everything(万物の黎明)』も、クラストルなしではありえなかった本だと思います。
ある意味で、クラストルは世界史、あるいはわれわれの諸制度に対する考え方をすべて塗り替えていく、というかそういう爆弾を仕掛けてこの世を去ったような人です。それは彼が、人類学さらには考古学的な叡智を独特に解釈・集約して展開できたからなんですね。クラストルは「ワン・ビッグ・アイデア」の人だとも言われていますが、それは、いろいろなことをあれこれと論じるのではなくて、ひとつのアイデアをもとに大きな知的展開を成し遂げた人物、という褒め言葉なのです。
クラストルのワン・ビッグ・アイデア、つまり「未開社会というのは、国家を知らない未熟な社会なのではなく、国家を意識して遠ざけたのだ」というアイデアは想像以上のインパクトがあって、いまだにそのインパクトが拡大を続けている。これがこの本での解説で伝えたかったことのひとつです。
とくに人類学のみならずそれを超えてひとつの知的な要点になるのが、中村さんも指摘されたように、反ホッブズということになるかと思います。ホッブズ本人の思想はもっと厳密なものですが、ホッブズ的な思考のフレームは驚くほど浸透しています。私たちの強固な常識の地平、しかもすべてを反動に引き寄せる強力な磁場をなしているとも言えるほどです。
要するに、「人間は放っておくとヤバい」ということですね。つまり、各々が自らの利益をひたすら追求しはじめ、やがて戦争をおっぱじめる、というわけです。ヨーロッパだけでなく、日本でも同じです。さらには右派も左派も関係ありません。左派であっても「人間は放っておくとヤバいから、規則をつくって管理しなければ」みたいな発想にすぐなりますよね。
「放っておくと人間はろくでもない」「どんどん自分の好きなことばっかりやってどうしようもない」という発想は、すぐに人口に膾炙してしまうというか、世俗的なかたちで充満します。しかし、このこと自体がわれわれの社会をろくでもないものにしていると言いますか、どうしようもない袋小路に追い詰めているのではないか。
そもそも、「人間は放っておくとヤバい」という発想、それはある時代のヨーロッパ社会で生まれ、資本主義の席巻とともに普遍化し、「やっぱり国家は必要でしょう?」「国家がなくなったら困るでしょう?」「喧嘩や人殺しが起きたり、それが紛争に繋がったらどうするの?」と。
それでも、少し前までは日本でも多かれ少なかれ警察や「警察的なもの」を忌避する感性は社会のなかで薄く広く共有されていたように思います。1980年代くらいまで「日本人は本当に警察が嫌いなんだな」と私は感じていましたし、実際にそうだったと思います。私が中学、高校生のときは十代の若者がもっとも荒れていた時代だったと思いますが、余程のことが起こらない限り、若者も、そして教師も保護者も、警察に頼ることはしなかった。大学に入っても「秩序派」というのは悪口として言われていました。「あいつは秩序派だ」というのは、明白に悪口でしたから。
その感覚は、社会がよくなっているときの人間の振る舞い方の豊穣さとも結びつくと思うのですが、そうした領域がどんどん狭くなっていき、「放っておくと人間はろくでもない」「だから上から押さえつけないとまずい」という発想に置き換わっていく。それがネオリベラリズムとも絡むかたちで、どんどん世界を窒息させているのではないか。
だからいま、人類学的な学問を使い、こうした認識を解除していくことはとても重要だと思うのですね。つまり、「反ホッブズ」とは単に思想的課題ではなく、イデオロギー闘争的な課題でもあるのです。
ところで、今回はお二人の訳書が主役なので、本書の細かい部分にあまり深入りしないようにしたいと思いますが、ひとつ確認しておきたいことがあります。それは、ラ・ボエシの『自発的隷従論』(西谷修監修、山上浩嗣訳、ちくま文庫、2013年)のクラストルへの影響です。解説でも書きましたが、ラ・ボエシ的な問題設定というのは、少しアンビヴァレントなところがあって、例えばドゥルーズ&ガタリなどは『千のプラトー』で、ラ・ボエシを一蹴するわけです。クラストルはラ・ボエシ的問題に囚われて身動き取れなくなったんだ、と。
この『自発的隷従論』をどう捉えるかということがすごく重要になってくると思うのですが、私が『自発的隷従論』を何で知ったかというと、アナキストがしょっちゅう引き合いに出していたからです。この本はアナキストにすごく愛されてきたのです。なぜ愛されてきたかというと、アナキストの場合の本書への力点は「われわれの意志でいつでもこの社会をやめられる」というところにあったからです。「われわれの意志がこの社会を成り立たせているなら、われわれの意志でいつでも撤回できるんだ」と。つまり、アナキストによる自発的隷従論への愛は、「大衆は権力を欲望した」といったところには、少なくとも力点がない。
ドゥルーズたちがラ・ボエシ的問題を一蹴するとしたら、こうしたところ(「われわれの意志でいつでもこの社会をやめられる」)にはないと思います。一蹴するのはもうひとつの力点の方です。つまり、大衆は権力を欲望した、というような力点。日本だと「それでも大衆は◯◯を欲望した」「それでも大衆は◯◯を求めた」といった言い方が最近ではよくされますよね。実際、多くの歴史的場面がそういったフレームに収められてしまう。私はこういう問いの立て方は危険、とまで言わないまでも、少なくとも慎重であるべきだと思っています。
先日の選挙(2021年衆院選)でも大阪で維新が躍進したことを受け、「愚民論」のようなものが噴出してましたよね。つまり、「大阪人は、あんな党に票を入れてなんて愚かな大衆たちなのか」と。これが2010年代の知的空気を集約的に表していたように思います。ポピュリズム批判、反知性主義批判、フェイクニュース批判、通俗道徳批判。こうした枠組みが2010年代には強力に作動していました。そこにはすべて、そこはかとなく「愚民論」が貫通しています。「自発的隷従論」の読まれ方も、そのような流れとマッチしていたように思うのです。そこでは、アナキストの力点、「いつでもやめられる」のほうがほとんど吹っ飛んでいました。
クラストルの読解は、こうした「リベラル」なものとは断絶していることは明らかです。しかし、やはりクラストルの場合もアナキストとは違い、「いつでもやめられる」というところに力点がない意味では共通している。つまり彼は、ラ・ボエシの議論に、隷従を自発的に意志しない契機を強力に読み込んでいます。そして、それが一転して人間は自発的に隷従を意志することになる、その転機を「災厄」だと見たラ・ボエシの、この「災厄」の還元不可能性を全力で強調するのです。
そこにはいかなる論理も因果も超えた断絶があるし、なければならない。これはクラストルが自由の思想家たるゆえんだと思います。というのもその断絶で賭けられていたのは、人間の意志の自由なのですから。
しかし、この還元不可能性がどこまでも深かった。「いつでもやめられる」の契機があまりにも乏しいのです。
この問題を私は天皇制を引き合いにだして再考してみました。自発的隷従を日本で論じるときに天皇制を避けるわけにはいきません。そこで本書の解題では、天皇制への自発的隷従と見なされているものが、はたしてそうなのか、と疑義を呈しました。「一木一草が天皇制である」という命題と、自発的隷従論は非常に相性がいいと思います。そして、こうした論じ方自体が袋小路であることは明らかです。
考えてみるなら、日本において天皇制は強力なタブーであり、暴力に囲まれていることは誰もが知っています。それを侮辱する者への嫌がらせはもちろん、物理的殺害もめずらしいことではありません。そして、このテロリズム(天皇制を擁護する暴力)に対しては、この社会において強い非難や排撃、取り締まりの対象にならないこともみな知っています。知識人ならなおさらそうでしょう。
天皇制はこうした字義通りのテロルに浸りきっている。だから知識人もふくめて日本における天皇への敬愛なるものは、こうした恐怖にべったりと取り憑かれていると思います。右翼ではない知識人が、天皇への愛着や信頼をなにがしかポジティヴに捉えることそれ自体に、恐怖感とその否認がある。これは暴力への恐怖を直裁に表現できない、それを抑圧してしまうマチズモとも深く関係していると思います。
「自発的隷従」論は、こうした恐怖感の自己抑圧にも相性がいいのです。ドゥルーズたちがそれを警戒し、クラストルがそれに誘われるのを批判したのには、こういう要素もあるように思います。
よって、この本の解題では、クラストルが人類学を超えて知的にインパクトを波及させていくときに生じる「トラブル」のひとつの原因をそこに求めてみたわけです。
中村 クラストルの仕事と、シャマユーやオレリア・ミシェルの本は、向かっている先は違うかもしれませんが、ちょうど合わせ鏡のように見えるところがありますよね。
なぜかというと、『人間狩り』にしろ、『黒人と白人の世界史』にしろ、やはり「特殊ヨーロッパ」をすごく意識しています。前の世代の人たちの仕事というのは、やはり「ヨーロッパ=普遍」から始まっているように思うのですね。そこから、自分たちの立ち位置を相対化し、植民地主義の問題を思考の射程に入れようとする。
前者が「なぜこのような社会が生まれてきたのか」という特殊性を歴史的・思想的に解明していくのだとすれば、クラストルの仕事は、むしろヨーロッパの思考の外部をどのように発見していくのかという問いの系譜だったと思います。それこそ酒井さんが、クラストルの解説の中でも引き合いに出していた、ジェームズ・C・スコットの『ゾミア』(佐藤仁監訳、みすず書房、2013年)の話もそうですね。
われわれはある種の先入観で、「非」近代的な人たちは、「前」近代的な生き方をしていると決めつける側面があります。クラストルの仕事は、そのような人びとの生活のあり方、あるいは知のあり方を発見していく作業だと思います。そもそもがわれわれの偏見であったのではないか、と。そういう意味で合わせ鏡というか、非常に響きあっている著作同士だと捉えています。
酒井 これは、今後の課題になるか思うのですが、基本的に奴隷という存在は未開社会にも存在するわけですね。つまり「人間狩り」は、未開社会、クラストルの言う「国家に抗する社会」にもある。クラストルが観察した南アメリカでも、奴隷狩りは日常でした。国家を遠ざけているシステムのなかにも、「奴隷狩り」は組み込まれています。
大西洋奴隷貿易においては、資本制のなかに、要するに経済原理の中にそれが取り込まれていきます。未開社会の場合も、(グレーバーが言うところの「人間経済」という)人間を目的とした経済のなかにおいても、奴隷は位置づけられます。
シャマユーの議論は、古代ギリシアと聖書の伝統から始まっていて、古い時代にまで目を配ってはいますが、「国家のない社会」ないし「国家に抗する社会」の狩猟、つまり「狩ること」をどう捉えるのか。
一方で、たとえばドゥルーズ&ガタリの理論においては、「遊牧民」「ノマド」という形象がポジティヴな概念として出てきますが、あれもシャマユーの言う「狩り」を、人間をもふくめて行なう捕食的遊牧民族の話ですよね。ここにある狩猟というもののアンビヴァレントな側面をどう捉えるのか。
そして「逆転可能性」についても少し思うところがあります。シャマユーも「逆転可能性」の話をしていますが、それは逆転可能性自体の土俵を破壊する話です。「狩られているものが狩る」という逆転可能性に、シャマユーはとどまってはいけないというのです。
しかし、たしかにそうであるけれども、やはり逆転可能なことに意味がないとは言えないと思うのですよ。つまり、狩られていたものが狩る、というモメントです。人類学に照らし合わせるなら、必ずしも同じ土俵を再生産するのではなくて、国家のある社会と国家のない社会を隔てるような何かがそこにあるわけですよね。
その場合に「狩る」というモメントは、人類史に広げた場合、果たしてこのように暴力とヒエラルキーと抑圧だけにとどまるのか、と。そういう問いはあると思いました。自分でなにか応答があるわけではないですし、シャマユーが言っていることが正しいかもしれない。しかし、狩られていた側が逆に狩るようなカタルシス。それを考えていくのも課題かなと思いますね。
『国家をもたぬよう社会は努めてきた』の解題にも書きましたが、クラストルについては、ほぼ『国家に抗する社会』しか論じられていないところがありますね。それをどう展開するかで、理論の方向性が分岐していきます。ある意味でクラストルは、執拗なまでに自分の研究対象を限定したところがあり、それが彼の議論のインパクトにつながっている、というのが私の解説のひとつの趣旨です。ですから、国民国家の誕生のあと、大西洋貿易、資本主義以降の問題設定とどう連接するかは意外と簡単ではないですよね。
中村 普段、クラストルの話は人類学のなかでも酒井さんがおっしゃったような限定のなかで語られがちです。もちろん、ドゥルーズ&ガタリ経由のインパクトもありますが、もう少し広い意味での「思想」にクラストルを開いていくとき、今回の酒井さんのお仕事はすごく重要だと個人的に直感しています。
人が人を差別するときのロジックに、「知性」の基準で人間をはかる面があると思います。知的であるかどうか、文明か野蛮か、と。そのとき、野蛮と言われているものを、もっと分節化して考えていくこと。それこそが、いま私たちが考えなければいけないモメントになっているのは間違いないと思います。このまま近代主義的な社会・制度・技術のあり方に乗ってしまうなら、われわれの未来はないでしょう。
SDGsと言われる時代ですから、誰もが薄々分かっているわけですが、その課題に対して改良主義的に進むのか、あるいは抜本的にものの見方を変えていくのか、というところですよね。ものの見方を変えるというのは、実は思想や文学などの大きな役割でした。文学については、近年かつてほど人々の関心にのぼらなくなってきていますが、われわれが本当に異なる世界や異なる社会を構想していくときには不可欠なものです。
現在の、あまりにも現実主義的な思考回路が「そんなことはあり得ない」というような想像力の貧困をもたらしているとすれば、クラストルのこの本をここで再発見することの意義はすごく大きいのではないかと思います。
酒井 これは先ほどの「愚民論」ともかかわるのですが──2010年代くらいから「反知性主義」批判が目立ってきたあたりからの態度だと思いますが──、やたらと知性や教養が持ち上げられて、それ自体に価値がある、といった語り口を頻繁に耳にするようになりました。「想像力よりも教養の方が大事だ」というような。でも、想像力に裏打ちされない「教養」になんてなんの意味もないですよ。ナチスだって「教養」ある知識人があれだけ加担したわけですから。ここに階級差別や学歴差別自体が強力にあるとまでは言いませんが、少なくともそれが潜んでいるとは言えるでしょう。
いま、ポスト資本主義の議論が活発になるなかで、SFがよく参照されていますね。グレーバーもそうですが、SFをよく参照します。SFというジャンルは、一貫して「テクノロジーと人間の和解」を想像してきました。人間の幸福に技術が寄与していく、というもっとも基本的なモメントが疎外されないテクノロジーのあり方を空想してきたわけですよね。
グレーバーが『官僚制のユートピア』(酒井隆史訳、2017年、以文社)のなかでも何度も論じていることですが、テクノロジーが人間を疎外する、というとき、いつも枕に「「ある種の」テクノロジー」とつけなければいけません。「ある種のテクノロジー」は、資本制のなかに完全取り込まれ、予算配分されていくようなテクノロジーです。
たとえばエクセルというソフトが代表的ですが、これまでこのソフトの開発にどれほど莫大なコストと時間を費やしてきたか分かりませんが、エクセルが人類を幸福にしたことなんてほとんどない……、と断言してしまうと行き過ぎかもしれませんが(笑)、おそらくわれわれがエクセルを操作して日常的に遭遇している小さな不幸を合算すれば不幸が勝るのではないでしょうか(笑)。最初に開発されてから、すでに2、30年経っているのに。
結局これは、そのように回路づけられているなかでの想像力の産物だからです。こういうときに、それこそハイデガー的なテクノロジーと人間の関係みたいな話にリアリティが出るのですね。
中村さんが「異なる社会を構想していくときには不可欠」と言われた「思想や文学」、その代表的なものがSFなどに現れている想像力です。海外のSF作家には、ル=グウィンを筆頭に左派が多いですよね。そして、いま活躍している多くの思想家が、ラディカルにポスト資本主義を考察するときにSFをひとつの参照軸にしている。やはり文学の想像力はすごいな、と。
中村 今回のイベントのタイトルは「私たちは「人間」であって、人間ではない?」でしたが、まさしく、カッコつきの人間である、ということですね。
この『人間狩り』や『黒人と白人の世界史』が示していたものは、線引きされて非人間化されていく人たちがいることです。われわれはいま、人間の条件ともいうべきものが非常に脆くなっている状況を生きています。そのことが、今回のタイトルの趣旨でした。
それでは、本日は長らくお付き合いくださりありがとうございました。
今後の皆さんの読書に資するようなひらめきが少しでもあったとすれば大変うれしく思います。
(了)
著者紹介
酒井隆史
1965年生まれ。大阪府立大学教授。専門は社会思想、都市史。著書に、『ブルシット・ジョブの謎』(講談社現代新書)、『通天閣』(青土社)、『暴力の哲学』『完全版 自由論 現在性の系譜学』(ともに河出文庫)など。訳書に、デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ』(共訳、岩波書店)、『官僚制のユートピア』(以文社)、『負債論』(共訳、以文社)、ピエール・クラストル『国家をもたぬよう社会は努めてきた』(洛北出版)など。
中村隆之
1975年生まれ。早稲田大学准教授。フランス語を主言語とする環大西洋文学、広域アフリカ文化研究。著書に『エドゥアール・グリッサン』(岩波書店)、『野蛮の言説』(春陽堂書店)など。訳書に、アラン・マバンク『アフリカ文学講義』(共訳、みすず書房)、エメ・セゼール、フランソワーズ・ヴェルジェス『ニグロとして生きる』(共訳、法政大学出版局)、エドゥアール・グリッサン『フォークナー、ミシシッピ』(インスクリプト)など。
平田 周
1981年生まれ。南山大学准教授。思想史。共編著に『惑星都市理論』(以文社)など。共著に、『コロナ禍をどう読むか』(亜紀書房)、共訳書に、グレゴワール・シャマユー『人間狩り』(明石書店)、クリスティン・ロス『もっと速く、もっときれいに』(人文書院)など。
![Read more about the article 誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[第1回]後編/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2021/12/PXL_20210130_134106265.MP_-768x512.jpg)


![Read more about the article 【連載】ノン・エクスクルシーブ・ニューヨーク[第3回]/大崎晴地](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2023/12/16-768x513.jpg)