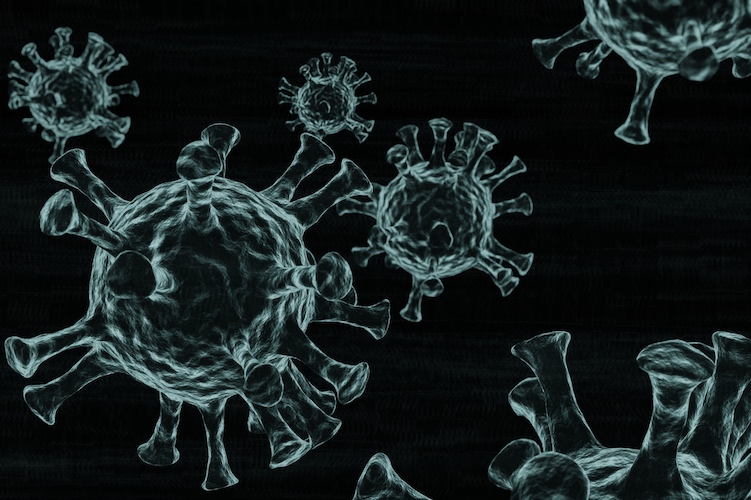手製銃から超現実へ
アナキズムとシュルレアリスムから考える現在
五井健太郎
安倍晋三が撃たれて死んだ。山上徹也による今回の行動はあえていうなら、19世紀末以来のアナキストの戦略である「行為によるプロパガンダ」の系譜に連なるものだ。そして要人や要所の暗殺や爆破という直接的で無視しえない「行為」によって、自らの主張を広く世に知らしめるという戦略として見るかぎり、彼の行動はさしあたり成功しているといえる。安倍と統一教会のつながりをあらためて白日の下に晒し、後者の(あるいは両者の、あるいは戦後民主主義の)カルト性にふたたび注目が集まることになったのだから。
手製の銃による殺害劇それ自体は手段にすぎず、当人が獄中にいながら進行していくそこからの情勢こそが、山上の闘争の本体である。以後の積極的な担い手として私たちを名指しながら、いまもつづいているこの闘争がどこまで行きうるのかは、山上の行動にたえず立ち返りつつ、彼が最終的に何を望んでいたのかを見極めながら問われるべきことだが、いずれにせよその到達点が、より〈クリーン〉な政治などでないことはあきらかだろう。大手メディアと手を取りながら火消しに慌てる連中を尻目に、ネット上の言説空間も媒介にしながら、民衆的な想像力はけっして容赦しないはずである。
「行為によるプロパガンダ」小史
だが上記のような「行為によるプロパガンダ」型の行動には批判も多く、そうした批判はそのまま、今回の行動にたいしても繰りかえされかねないものだ。そこでまず、その歴史を概観しておこう。
そもそもこの戦略は、アナキズム運動内部でさえ広く受けいれられてきたものではなかった。この戦略がもっとも多く採用された国の一つであるフランスに話を限ればそれは、パリ・コミューンの大弾圧を受け、それまでにあった集団性が壊滅し、避けがたく運動が個人化するなかで、余儀なく選びとられたという側面が強い。強いられた行動の単独性が、その過激さを加速させていったわけだ。運動の組織化を志向していた理論家たちからすれば「行為によるプロパガンダ」は、戦術的な功利性を超えたものであり、さらなる弾圧を呼びこみ、再建すべき集団性を根絶してしまいかねないものだったのである。
たとえば、若干20歳のアナキスト、エミール・アンリは、いくつかの紙面で「行為によるプロパガンダ」を支持する論陣を張ったうえで、同じ紙上でのマラテスタらの批判にまったく耳を貸すことのないまま、体制を支える人的・物的な流通の要所であったサン=ラザール駅付近のカフェで爆破事件を起こしていくことになるが、それを受けてエリゼ・ルクリュは、アンリのような行動は「真の同志からすれば犯罪にすぎない」のだと断じている。またクロポトキンは同様の文脈で、「何世紀にもわたる歴史にもとづいた構造体を、数キロのダイナマイトで破壊することはできない」と述べ、単独犯たちによる「行為」の、それ自体としての無用性を強調する。

じっさい彼らが憂慮していたとおり、フランス政府はあいつぐ爆弾事件を受け、「極悪法」というふざけた名前の法律を通していく。アナキストの疑いがあるだけで逮捕・拘禁することが可能になるこの法律が、大局としてアナキスト運動に与えた影響は想像に難くない。結果として情勢はより合法的な路線をとるサンディカリズムの方へと流れ、運動は急進性を減じたまま、なすすべなく大戦へとなだれこむことになる。
「行為によるプロパガンダ」という戦略がたどってきた以上のような歴史は、同型の行動を経験した私たちの現在とも無縁とはいえないはずだ。今後また権力は、〈テロリズムを許さない〉という聞き飽きた定式とともに、私たちの自由をいまよりもさらに制限しようとするだろう。山上が開始した闘争において、彼の「行為」が権力側の「プロパガンダ」に盗用されない保証はどこにもない。だが、だとしたら私たちは、山上の行動を「犯罪にすぎない」と見なし、その無用性を批判して、あとはただ、何度目かの来たるべき〈反テロリズム〉の時代を耐えしのぶしかないのだろうか。以上を受けつつあらためてここで、「行為によるプロパガンダ」の歴史に戻ってみよう。とはいえ先に見た運動内部におけるその正史のようなものにではなく、その傍系にあった歴史に。
アナキズムの黒い鏡
リーダー格の理論家たちからは煙たがられた「行為によるプロパガンダ」だが、この戦略に誰よりも熱狂し、諸手を挙げて受けとめた者たちがいた。運動の外縁にいた文学者・芸術家たちがそれである。たとえば象徴派の詩人たちは、単独者たちの「行為」が見せる破壊性に──より正確にいえば、一般的な功利的計算を超え、アナキストの〈大義〉さえ超えたその直接性に──共鳴し、それと並行するものとして、定型を破壊する自由な詩のあり方を求めていく。爆破や暗殺と定型表現の破壊を同一視するこうした認識は、けっして一方的なものではなかった。コミューンの闘士ルイズ・ミシェルはこの当時、ランボーやマラルメらも参加した『デカダン』誌に招かれ、「デカダンたちは文体のアナーキーを創造しているが、アナキストたちもデカダン同様、古い世界を無に帰すことを望んでいる」と述べている。
こうした並行性は、大戦を経てアナキストの戦線それ自体が後退するなかにあって、さらに前へと進められていく。象徴主義の鬼子たるシュルレアリスムの登場だ。象徴派詩人の熱心な読者だったアンドレ・ブルトンは、10代のころに参加したサンディカリズムのデモで翻る赤旗の波を見つめつつ、わずかにそこに穿たれる黒い旗のすがたに胸を躍らせている。また彼は、グループの形成期にあたる1920年代、何度か繰りかえし、「一番簡単なシュルレアリスム的行為とは、両手に銃を持って街頭に出て、群衆のなかでできるだけでたらめに発砲することだ」と書くが、小児病的なニヒリズムとも批判されてきたこの一節とともに彼の念頭にあったのは、他でもなくあのエミール・アンリのことであり、その「行為」に宿る直接性だった。ブルトンが後年、「シュルレアリスムがはじめてはっきりと自分のすがたを見いだしたのは、アナキズムの黒い鏡のなか」だったと書くとき、そのアナキズムとは、——マラテスタでもルクリュでもクロポトキンでもなく——「行為によるプロパガンダ」とともにあるそれだったのだ。
シュルレアリスムと集団性の問い
各人がアンリのようである集団はいかにして可能なのか。単独者同士がそれでもたがいに出会い、そして共にあるためにはどうしたらいいのか。いいかえるなら、功利的な計算の外にある直接的な「行為」が、〈何でもあり〉の無秩序に堕してしまうことを避けながら、しかしあくまでもその直接性を保ったまま組織化をおこなうには、いったいどうしたらいいのか。こうしたグループとしてのシュルレアリスムの問いはそのまま、「行為によるプロパガンダ」とともに隘路に陥った19世紀末アナキズムが答えを出せずにいた問いであり、同時にまたわれわれの現在にかかわる問いだといえるはずだが、およそ半世紀にわたってつづいたシュルレアリスム運動の歴史からこの問いにたいするヒントを探すことは他日に期すとして、ここではひとまず、運動を要約するブルトンの言葉を引いて終わりたい。「美は痙攣的なものだろう、さもなくば存在しないだろう」。
初出:『アナキズム』29号(2022年8月1日)、アナキズム紙編集委員会
著者紹介
五井健太郎(ごい けんたろう)
1984年生まれ。東北芸術工科大学非常勤講師。専門はシュルレアリスム研究。
共著に『統べるもの/叛くもの』(新教出版、2019年)、『ヒップホップ・アナムネーシス』(新教出版社、2021年)など。
訳書にマーク・フィッシャー『わが人生の幽霊たち』(Pヴァイン、2019年)、ニック・ランド『暗黒の啓蒙書』(講談社現代新書、2020年)、同『絶滅への渇望』(河出書房新新社、2022年)など。

![Read more about the article 【連載】ノン・エクスクルシーブ・ニューヨーク[第2回]/大崎晴地](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2023/10/31.jpg)