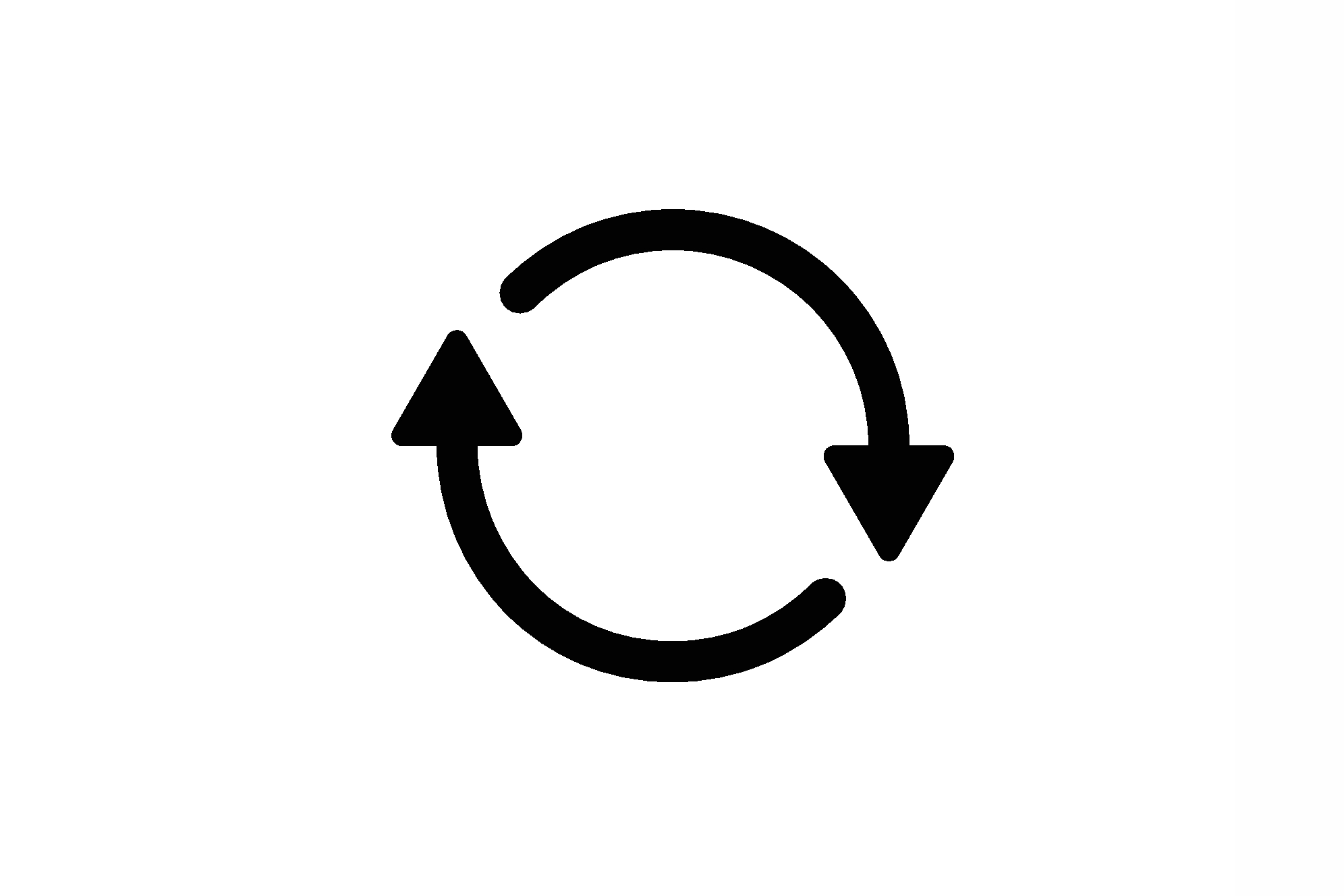反−万博論 対抗の地図を描き出すために
序(introduction)
原口剛
1.万博体制下の「街の光景」
万博の開催を目前にして大阪の街は、すみずみまで「いやな気配」に覆われようとしている。鉄道やバスや商店街はどこもかしかも万博広告に溢れかえり、「ミャクミャク」の姿をみずに街に出るのはほぼ不可能だ。民営化され「大阪メトロ」と名を変えた地下鉄に乗ろうと思えば、いやでも顔認証システム搭載の改札機が目に入ってくる(図1)。この不気味な生体情報採取マシンもまた、大阪・関西万博に向けた「実験」のひとつだ。いつも気分転換を与えてくれていた近所の淀川沿いの河川敷は、万博を絡めた延伸工事によって立ち入り禁止にされてしまった。河川敷ちかくの道路は、「散歩への権利」を阻止するかのように、ひっきりなしに工事用トラックが往来する。

このような生活空間の変容は、あからさまな暴力と地続きである。昨年12月1日、「寄せ場」として知られる釜ヶ崎でくらす野宿者や、かれらが集う団結小屋は、不意打ちの暴力によって強制的に立ち退かされた。目の前にそそり立つ星野リゾートのホテル「OMO7 OSAKA」のファサードは、夜になるとLED照明をもちいた万博宣伝が、これ見よがしに映し出される。
こうした日常生活の変容は、10年前に万博の舞台となったミラノでも起きていたことだ。北川眞也は、「地球に食料を、生命にエネルギーを」という理念を掲げた2015年ミラノ万博の内実について、「反万博の会」の主張を引きながら次のように論じる。
しかし、万博は万博である。どれほどクリーンとかグリーンだとか言われようとも、その本質は変わらない。土地を奪うこと、搾取すること、利潤を生み出すこと、階級的支配権力を強化すること、そして万博「以後」に適用されるべき社会統治のメソッドを実験に移すこと。……万博はいわば、そのための好機として既存の支配階級によって利用される。「メガイベント」や「大事業」は、ジェントリフィケーションの過程をさらに加速させる装置として重宝されるのである。それゆえ、「地球に食料を、生命にエネルギーを」などいかなる理念が掲げられようとも、それはただの「装飾」でしかない 1。
「装飾」を隠れ蓑にした暴力は、いま、10年後の大阪で再現されようとしている。違いがあるとすれば、2,000万人以上の人びとが訪れたミラノ万博が「成功」とされたのに対し、大阪・関西万博は破たんへの道をひた走っていることだろう。だが問うべき問題の核心が、「成功か失敗か」という二者択一にあるわけではない。ミラノ万博の経験が伝えるのは、こんにち万博とは暴力を作動させる装置にほかならない、ということである2。
こうした問いへと進んでいくために、まず、次のことを強調したい。大阪・関西万博をめぐる諸々の問題とは、よく言われるように「大阪」という土地に例外的な現象なのではなく、世界に共通する問題だということだ。たしかに万博誘致は、IR・カジノとともに、大阪維新の会が目玉として掲げた都市戦略である。だが私たちは、維新の台頭という現象そのものを、一方では新自由主義的アーバニズムの世界的普及の現われとして、他方では日本政治に受け継がれた土建国家的体質の現代版として、捉えなければならない。さらに重要なのは、ミラノの「反万博の会」の主張がそうであるように、万博や五輪といったメガイベントに対する対抗は世界的に広がっている事実にこそ目を向け、かつ、足元に潜在するはずのラディカルな民衆の伝統に根ざすような、連帯の感覚を呼び覚ますことである。つまり私たちが求めているのは、メガイベントの暴力に抗うための〈対抗の地図〉なのだ。
この連載は、そのような地図の作製に向けたひとつの試みである。「はじまり」となる本論考は、目前の大阪・関西万博の暴力と対峙するために、ありうべき世界的かつ歴史的な問いの可能性を探りつつ、これからの議論の見取り図を示したい。なお、筆者は本連載と並行して、『反‐万博の地理学(仮題)』を以文社より刊行すべく執筆を進めている。本連載では、いま書き進めている文章からアクチュアルだと思われる部分を先行発信し、10月まで開催されるという万博とその体制に対する問いを投げかけていきたい。
2.メガイベントの暴力は連鎖する——五輪と万博をめぐって
冒頭で筆者は、こんにち万博とは暴力を作動させる装置にほかならない、という命題を掲げた。なかには「いくらなんでも大げさではないか」といぶかしく思う読者もいるかもしれない。ここでは、いくつかの調査研究や実践を参照しつつ、この命題の裏づけの作業を行なっておこう。
スイスのジュネーブに拠点を置く(残念なことにいまは閉鎖されてしまった)「居住権および立ち退きに関するセンター」(the Centre on Housing Rights and Evictions: COHRE)が発行する報告書は、世界各地の立ち退きの実態に迫った調査研究として知られ、ジェントリフィケーション研究の基礎資料として世界的に参照されてきた。ここで取り上げたいのは、COHRE が2007年に発刊した報告書『居住権のためのフェアプレーを——メガイベント、オリンピック、居住権』である(図2)。

1980年代以降のオリンピックがもたらした暴力と立ち退きのひとつひとつをレビューしつつ、この報告書は、オリンピックを含むメガイベントとは「都市開発の触媒」であると結論している。その要点は、以下のとおりだ。
① オリンピックは、その開催が決定される以前から存在していた開発計画を正当化し、加速させる機会となる。
② オリンピックの開催は大量の公共投資や民間投資を呼び込む機会となり、通常であればあり得ない規模の開発を実行可能にする。
③ オリンピックの開催日程のスケジュールの縛りにより、期限までに間に合うよう急ピッチで進められる。
④ オリンピックの誘致・成功を望む国家や都市自治体と、開発から利潤を得ようとする建設企業の思惑は、ここにおいて完全な一致をみる。
ここで重要なのは、このような「開発の触媒」としての性格はオリンピックに限らず、政治的・文化的・スポーツ的なあらゆるイベントに共通すると報告書が指摘していることである。とすれば、私たちは、オリンピックや万博といったイベントの種別にこだわるのではなく、それらの共通性に目を向けなければならない。だからこそ報告書は「メガイベント」というキーワードを強調するのだ。現代世界のなかでメガイベントに期待されているのは、五輪であろうと万博であろうと、「開発の触媒」の装置としての作用であることに変わりはない。そしてメガイベント主導の開発は、世界各都市で社会的不公正を刻み込んでいるのだ(末尾の付録資料の表1・表2を参照)。
このような視点を踏まえたうえで、2025年の大阪・関西万博の招致活動が始まった時点をあらためて振り返ってみよう。万博の誘致活動がはじまったのは、2020年東京オリンピックの開催が決定した翌年の2014年のことである。大阪市特別顧問であった堺屋太一の「東京が五輪なら大阪は万博だ」との主張を皮切りに、橋下徹市長および松井一郎府知事(いずれも肩書きは当時)の働きかけによって、誘致の火ぶたが切られたのだった3。2018年11月のBIE総会にて大阪での開催が決定したわけだが、このイベントに政府が期待するものはすでに明らかだった。すなわち、「20年東京五輪・パラリンピック後の景気刺激策」となること、である4。つまり大阪・関西万博に期待されていたのは、2020年東京五輪につづく経済的機会としての作用だったわけだ。
このように万博と五輪が連動する一連の都市戦略であり、しかも五輪が万博に先行するのであれば、さらにさかのぼって五輪の原点に立ち返る必要があるだろう。表向きは「復興五輪」や「コンパクト五輪」を謳ったこのメガイベントの目的とは、首都・東京の大規模開発を実行することだった。またそれは、東日本大震災および原発メルトダウンという惨事から目を背けさせるために考案されたスペクタクルであり、その帰結として被災地は切り捨てられた。ジェールズ・ボイコフが世界各地を舞台としてその地を収奪する五輪の権力を「祝賀資本主義」と呼ぶように5、まさに五輪は、祝祭的な「どさくさ」を人為的につくりだしつつ開発事業を強行しようとするプログラムだった。「どさくさ」に紛れた火事場泥棒がいかに悪質だったかは、汚職や談合で逮捕された人物のリストをみれば一目瞭然である。そして大阪・関西万博もまた、震災の直後に企てられた政治的「どさくさ」のひとつなのだ。
よって、2021年に開催された五輪のもと東京で起きた出来事を振り返ることは、いま関西でなにが起きているのかを知るうえで、重要な手がかりを与えるはずだ。たとえば、五輪のために新たに建設された国立競技場である。巨額の公的資本を投下して建設されたこの競技場の建設過程では、都営霞ヶ丘アパートの住人は不当にも移転を余儀なくされ、また、明治公園を日常的に利用してきた野宿者は前代未聞の暴力によって立ち退かされた6。しかも五輪のあとに残されたこの巨大インフラは、維持費だけで毎年24億円が必要だといわれる。その維持費をまかなうためには、これからもイベントを開催し、収益をあげつづけねばならない(さもなければ公費が投入されなければならない)。ここで私たちは、奇妙な事態に立ち会っている。インフラとは本来、人びとの必要に応じて建設されるべきはずのものだ——橋を架けなければならないのは、そこに川を渡りたいと思う人がいるからだ。ところが新国立競技場については、事態はあべこべである。巨大インフラの経済的生命を維持するために、人びとの〈生〉が動員され、注ぎ込まれるのだから。これが、東京五輪がもたらした帰結のひとつである。
あるいは、渋谷駅ちかくにある宮下公園の改造である。もともと宮下公園は、野宿者をふくめさまざまな人びとがゆるやかに共有する都市公園であったが、2000年代以降は公園の私営化(privatization)をめぐって激しい論争と対抗的実践が繰り返されてきた7。ネーミングライツをナイキに売却して遂行された2010年代の公園改修は、そのひとつである。その後に全面的な改造が着手され、COVID-19のパンデミックにより延期されたオリンピックを目前にした2020年7月、緊急事態宣言の直後のタイミングで、新たに「MIYASHITA PARK」が開業した。三井不動産が手がけるホテルとショッピングモールで構成されるこの建造物は、屋上に設えられた緑地をもって「公園」を名乗る。だが、ショッピングモールのフードコートに等しいこの疑似的な「公園」は、消費行為にふさわしくない者の立ち入りを拒み、長らく公園を利用してきた野宿者は完全に締め出されてしまったのである。COHREの報告書が指摘するとおり、五輪の暴力は都市を浄化し、貧しい住人や野宿者の立ち退きを引き起こしたのだった。
いま、これらの暴力が、場所を移しかえて大阪の地で再現されようとしている。注意しておきたいのは、五輪体制下の東京における開発が、競技場やその周辺だけに限らなかったということだ。たとえば公園の私営化が強行された渋谷駅周辺には五輪に関連した施設は見当たらず、直接の開発地からは外れている。にもかかわらず、「2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて宮下公園が新たな都市型立体公園として生まれ変わることが決まりました」との渋谷区長・長谷部健の言葉が示すように、公園改造は五輪をエンジンとして進められた8。メガイベントの政治・経済的効用とは、イベントの直接の対象地にかぎらず、都市全域で「開発の触媒」の力を発揮する、という点にある。万博体制下の大阪も、その例外ではない。
3.イベント中毒都市・大阪——1980~90年代の都市開発とその帰結
次に、もう少し長いスパンから万博を位置づけてみよう。近年の日本列島は、メガイベントのカレンダーで覆われたかのようである。日本政府および自治体は、2020年東京オリンピックの5年後に大阪・関西万博を開催し、さらにその5年後には北海道・札幌冬季オリンピックを誘致しようとした。2030年の冬季オリンピックの誘致を住民の力で断念させたことは、権力の暴走に歯止めをかけた重要な成果として胸に刻むべきだろう。
このようなメガイベントの暴走は、いつ始まったのだろうか。じつのところ大阪は、イベント頼みの都市政策へと突き進み、その末に破たんへと行き着いた経験をもつ都市である。過去に苦い経験を味わったにもかかわらず、ひたすら同じことを繰り返しているところに、大阪という都市が抱える病の根深さがある。この症状を体現する人物といえば、維新のブレーンであり大阪・関西万博の誘致を先導した堺屋太一が筆頭に挙げられるだろう。堺屋こそ、1980年代に「イベント・オリエンテッド・ポリシー」なる都市戦略を提唱した人物である。70年万博の経済的成功に取り憑かれたこの戦略の狙いは、イベントの「経済効果」を最大限に引き出すために、道路や公園、港湾や河川といった公共空間を舞台に大小のイベントを開催しつづけ都市に定着させることであった9。この戦略を柱に据えつつ、1980年代以降に大阪府市は、イベントと都市開発とを組み合わせた「大阪21世紀計画」を繰り広げた。主要なイベントとしては、1983年の「大阪築城400年まつり」および「世界帆船まつり」、87年の「天王寺博覧会」、90年の「国際花と緑の博覧会」などが挙げられる。そうして集大成として掲げられた目標こそ、(結局は北京に競り負けて失敗に終わった)2008年の五輪招致であった。また2000年代以降は、「大阪21世紀計画」の主要なスローガンは「水都再生」へと移行した。「ジェントリフィケーション」という言葉を肯定的かつ積極的に打ち出した「水都ジェントリフィケーション」なる提言書10が世に出されたのも、このような文脈においてのことである。
このように2025年大阪・関西万博のルーツのひとつは、1980年代の「イベント・オリエンテッド・ポリシー」にある。重要なことに幻に終わった2008年大阪オリンピックの主要会場として予定されたのは、舞洲や夢洲を中心とする大阪湾の埋立地であった(図3)。かつてオリンピックの舞台とされたその人工島が、いまは万博の会場と成り代わっているのだ。この点からすれば、メガイベントへと突き進む現代の大阪は、80年代の路線を反復しているにすぎないという見方もできよう。

(2008 年大阪オリンピック招致委員会編)
出 典 : OLYMPIC WORLD LIBRARY
(https://library.olympics.com/accueil.aspx)
だからこそ私たちは、「イベント・オリエンテッド・ポリシー」が席巻した状況のもとでなにが起きたのかを思い起こす必要がある。ここで、1987年の天王寺博覧会を取り上げてみよう。天王寺博覧会のテーマは「いのちいきいき」であった。まるで「いのち輝く未来社会のデザイン」という25年万博のテーマを先取りしているかのようではないか。この87年の博覧会が会場としたのは、寄せ場・釜ヶ崎に隣接する天王寺公園であった。8月1日から 11月8日までの期間に247万人の入場者を動員した博覧会が閉幕したのち、天王寺公園は全面改造され、1990年にはほぼ全面が柵で囲まれた有料公園としてリニューアルされた(図4)。この有料化の目的は、表向きには関西国際空港の開港を控えて国境をこえやってくる旅行客に対し「南の玄関口」としてのイメージを向上させることだと言われた。だがその内実とは、有料柵を設置することによって、この公園を長らく利用してきた日雇い労働者や野宿者を追い払うことにあったのだ。つまり「いのち」の名のもとに行われた博覧会の帰結とは、「いのち」を選別して公共空間から締め出すことだったのだ。この事例は、のちに「排除オブジェ」や「排除アート」と呼ばれる排他的な環境設計の先駆であるといえよう。

有料化によって公園は、思惑どおりに「きれい」になった。けれども重要なことに、かつての天王寺公園がもっていたアナーキーで雑多な魅力は根こそぎ失われ、有料公園の内部は「空っぽ」になった(図5)。むしろ、閑散とした有料公園内のあいだを縫うようにして走る無料の通行路にこそ雑多な営みが詰め込まれ、有料化に抗うかのように強烈な活気を放っていたのである。これらの経緯についてはのちの連載で詳しく論じるが、さしあたりその教訓を示すとれば、排除は公園を殺すということだ。

なお、2010年代に天王寺公園は私営化され、90年代以降公園を囲い続けた柵はようやく取り払われた。だが、消費空間へと変貌させられた公園では、物理的な柵にかわって消費空間に特有の「雰囲気」が、あいかわらず「招かれざる者」の立ち入りを拒みつづけている。
これと同じようなことが、2000年代以降の大阪では繰り返されてきた。さらに、大阪維新の会が大阪市会の与党会派に昇りつめた2010年代以降は、いっそう大規模な公園の私営化が強権的に進められるようになった。そしていま、万博体制のもとで、公園の私営化はこれまでにない規模に達しようとしている。維新は「公園が明るくなった」ことを自身の成果として誇ってやまないが、公園の原則とはなにか。誰もが自由にアクセスできること、つまり利用の公平性こそが、近現代の公園のもっとも基本的な原則ではなかったか。私たちは、いまこそそのような問いを投げかけなくてはならないはずだ。
さらに、1998年に刊行されたガバン・マコーミックによる『空虚な楽園』は、開発されゆく大阪湾を目の前にして、次のような問いを発した。
1960年代に日本の高度成長が始まって以来、この地域〔大阪湾岸一帯〕における開発のテンポは目をみはるばかりだった……しかしここで問題なのは、30年間も徹底的な変革がつづいた結果、一種のめまいというか酩酊状態が生じて、なによりもまずこんな成長をなぜ企てたのか、その行き着く先はどこなのかといった反省が困難になってしまったということである。……1990年代の問題は、成長と開発が目的達成の手段ではなく、自己目的化してしまうという、微妙な変化が生じてはいないかということである。11
「成長と開発が自己目的化してしはいないか」という98年の問いを、過去のものとして片づけることはできないだろう。2008年の世界金融危機を経験し、さらには2011年の東日本大震災を経てなお、自己目的化した都市開発はつづき、しかも大規模になっている。目の前の万博、そしてその裏に隠されたIR・カジノ開発が示すのは、そのような形骸化した開発のありようである。そう考えれば、万博の内実が理念を欠いたお粗末さを露呈していることは、当然の成り行きというべきだろう。そこには、過去になったはずの開発プロジェクトをひたすら反復することがもつ構造的な愚かさが、根深く巣食っているのだから。
4.原点としての第五回内国勧業博——ラディカリズムの伝統に向けて
さらに私たちは、歴史的な視座をもっと広げて、ある時代は「文明」の名のもとに、別の時代には「成長」や「未来」の名のもとに、近現代の博覧会が刻んできた暴力の歴史を捉えなおす必要がある。1903年に大阪で開催された第五回内国勧業博覧会は、実質的に日本初の「万国博覧会」であり、日本における博覧会史の原点であった。現在の天王寺公園および新世界を会場として開催されたこの博覧会は、原初的というべきふたつの暴力を引き起こした。ひとつは「人類館事件」として知られる事件であり、もうひとつは貧民の追い払いである。立ち入った考察はのちの連載で論じるが、さしあたり後者に論点を絞って、その含意を提示しておきたい。
かつて日本橋筋の界隈には、「長町」と呼ばれる木賃宿街が広がっていた。しかし内国勧業博覧会が開催されることにより、日本橋筋は一転して博覧会場に至るためのメインストリートとなり、貧民は追い払われたのである。そして、追い払われた貧民たちの場所として見出されたのが、新たに形成されたドヤ街・釜ヶ崎であった。つまり「ドヤ街」としての釜ヶ崎の歴史のはじまりには、博覧会の暴力が刻まれているのである。
さて、やや込み入った話になるのだが、この起源の物語については2000年代の研究によっていくつか重要な変更があった。かつては、博覧会開催に伴って木賃宿街がいっせいにクリアランスされたという物語が通説であった。ところが実際には、いっせいクリアランスの証拠は見当たらず、そのかわりに道筋に広告や看板を設置して貧民街を隠蔽するなどの措置が講じられていたことが分かったのである。貧民を一掃しようとする力が働いているのは明らかだが、とはいえ、貧民はその場所に居続けていたわけだ。そして、博覧会後に数年間の時間をかけて、警察による強権的な取締りによって、また博覧会を契機として動き出した都市開発の趨勢によって、その場所から貧民は立ち退かされたのだった。
貧民を一掃しようとする力が作動していたにもかかわらず、かれらは存在しつづけた。ということはつまり、貧民は、たやすく立ち退かなかったのである。それどころか追い払われた貧民は、都心へと戻ろうとする動きを絶やさなかった。たとえば1918年の米騒動では、大阪に飛び火した「騒動」は釜ヶ崎の街角で火の手をあげ、怒れる群衆は天王寺公園に集った勢力と合流しながら都心へと向かった。そして、かつて長町があった日本橋筋の界隈で群衆は、警察や軍隊と対峙しつつ、大暴動を巻き起こしたのだった。
決してたやすくは立ち退かなかった民衆が生みだした集団的実践、そこに生み出された対抗の空間、そして「博覧会的なもの」への抗いの歴史。それらこそ、筆者が根ざしたい伝統である。いつの時代もメガイベントは、まつろわぬ者たちの抗いに取り囲まれ、亀裂を入れられてきたのではないか。
たとえば70年万博についてみれば、「ハンパク」の名のもとに集った「反戦のための万国博」は、ベトナム反戦の声を響かせる空間や、前衛的かつ反体制的な芸術の空間を、大阪城公園を中心として都市全体へと押し拡げていった。さらに、万博会場の建設や関連する都市開発に必要な労働力を確保するために「寄せ場」へと変容させられた釜ヶ崎では、1970年12月の蜂起を皮切りに、数多くの「暴動」がたたかわれた。「暴動」と聞くと「見境なく暴れまわる暴徒」というイメージが浮かぶかもしれないが、それはメディアが与えたレッテルにすぎない。その内実とは、日雇い労働者を搾取する土建のシステムや、かれらを日々抑圧する警察権力にこそ敵対しようとする行為であった。さらに重要なことに、「暴動」とは日雇い労働者が群れとなってみずからを自己解放する「まつり」でもあった。たとえば、釜ヶ崎に生きた詩人の寺島珠雄が「暴動」を表現しようと書き綴った、次の光景に表わされるように12。
袋は
ビニールより紙がいい
新聞紙より丈夫で
セメント袋ほどでかくない奴
バラスより砕石
それと
鉱滓も使えるだろう
太鼓と鐘も準備しよう
にぎやかにいくのだ
もうひとつ、近年のメガイベントに目を向けるなら、2020年東京五輪に抗議し、対抗する数々の実践が生みだされていたことに気づく。たとえば「反五輪の会」13は、驚くほど豊かな創造性とラディカリズムをもってメガイベントの暴力と対峙し「ジェントリフィケーションとはなにか」、「公園は、都市は誰のものか」などの根底的な問いを突きつけた。とくに強調しておきたいのは、「反五輪の会」の声や行動が、「アートとはなにか」という問いを内包していたことである。万博という装置は、オリンピックがそうであったように、アーティストや研究者を明に暗に動員しようとするものである。また、小笠原博殻がオリンピックについて「決まった以上はよくしよう」という「善意」こそ問題であると述べた指摘14は、万博についてもいえることだ。アートや学問が万博体制を支持してしまうのか、それとも拒絶して対抗への道を模索するのかは、表現行為の自律の力にかかわる重大な問題である。また、国境を越えた連帯を広げられるかどうかの試金石でもある。メガイベントへの対抗とは、ミラノ万博における「反万博の会」の声がそうであるように、世界各地の民衆にとって共通のプロジェクトなのだから。
この連載で積み重ねていく論考も、そのような連帯の地平をめざすものでありたい。「はじめに」となる本論考では、いくつかの論点を提示しつつ、今後展開していく議論のおおまかな見取り図を描くことを試みた。次回以降は、過去に関西で開催されてきたメガイベントをひとつひとつ取り上げ、そこに潜在する議論の地平を広げていくつもりだ。
そのような思考を展開するための指針として、最後に、建築師の宮内康の言葉を掲げておきたい。宮内は、70年万博への動員をもっとも徹底的に拒絶した者のひとりであり、「美化された都市とは一体誰のものか」を真摯に問いつづけた人物でもある。「建築家はまず自らのつくるものすべて——その意図、そのイメージ、その反権力的な姿勢等々のすべて——を、権力によって回収されることを拒否すべく身構えねばならない」。そう宣言する宮内が目指したのは、「アジテーションとしての建築」であった(図6)。
アジテーションとしての建築は、都市の問題を決して解決しようとしない。それは都市のおかれた状況を、あるがままに明るみに引きずり出す。それは、秩序の綻びを補完するのではなく、綻びを押し広げる。
君は、あの公団住宅の空疎な明るさよりも、ドヤ街の嫌悪ではあるが密美な暗さに、より建築を見いだすであろう。君は、あのつくられた広場やコミュニティよりも、築かれたバリケードの中に、より都市を見いだすであろう。15

注
- 北川眞也「大都市化するミラノに抗する「反万博の会」(1)——退廃・装飾・品位の暴力」反ジェントリフィケーション情報センター, 2017年8月31日(https://antigentrification.info/2017/09/02/20170831ks/)。 ↩︎
- このような暴力は直近の2020年ドバイ万博においていっそう明らかなのだが、これについてはのちの連載で論じることにしたい。 ↩︎
- 松本創編著『大阪・関西万博——「失敗」の本質』筑摩書房, 2024. ↩︎
- 「2025年 大阪万博が決定、55年ぶり 年内にも運営組織」日本経済新聞, 2018年11月24日(https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38139440U8A121C1AM1000/)。 ↩︎
- ジェールズ・ボイコフ『オリンピック秘史——120年の覇権と利権』早川書房, 2018[原著:2016]. ↩︎
- 小川てつオ「オリンピックと生活の闘い」(小笠原博毅・山本敦久編『反東京オリンピック宣言』航思社, 110-132, 2016)。この立ち退きは過去に例を見ない悪質なやり口だったのだが、この点についてはのちの連載にてくわしく論じたい。 ↩︎
- 木村正人「〈共〉の私有化と抵抗——渋谷におけるジェントリフィケーション過程と野宿者運動」『空間・社会・地理思想』第22号, 2019. 139-156. ↩︎
- 「2016年、渋谷からTOKYOが変わる!? 長谷部健さん(東京都渋谷区長)」TOKYO HEADLINE Vol.658, 2016年1月9日(https://www.tokyoheadline.com/362266/)。また、渋谷における五輪開発と排除については以下のウェブサイトを参照のこと。「2020年オリンピック・パラリンピックに向けた再開発のための宮下公園強制封鎖、野宿者排除に抗議します。」反五輪の会, 2017年4月8日(https://hangorin.tumblr.com/post/159327118186/)。 ↩︎
- 堺屋太一『イベント・オリエンテッド・ポリシー——楽しみの経済学』エヌジーエス, 1984. ↩︎
- 財団法人関西社会経済研究所『水都ジェントリフィケーション——大阪 Triangle 構想』関西社会経済研究所資料08-05, 2008. ↩︎
- ガバン・マコーミック『空虚な楽園』みすず書房, 1998, 38. ↩︎
- 寺島珠雄『釜ヶ崎――旅の宿りの長いまち』プレイガイドジャーナル社, 1978, 256. ↩︎
- 「反五輪の会」については以下のサイトを参照のこと。「NO OLYMPICS 2020> 反五輪の会 (Hangorin No Kai)」(https://www.tumblr.com/hangorin) ↩︎
- 小笠原博毅・山本敦久編『反東京オリンピック宣言』航思社, 2016.15)
↩︎ - 宮内康「アジテーションとしての建築」『風景を撃て 大学七〇‐七五——宮内康建築論集』相模書房, 1976, 232. ↩︎


著者紹介
原口 剛(はらぐち・たけし)
神戸大学大学院人文学研究科教授、専門は都市社会地理学および都市論。著書に『叫びの都市――寄せ場、釜ヶ崎、流動的下層労働者』(洛北出版)、『惑星都市理論』(共著、以文社)、『釜ヶ崎のススメ』(共著、洛北出版)など、訳書にニール・スミス『ジェントリフィケーションと報復都市――新たなる都市のフロンティア』(ミネルヴァ書房)、ロレッタ・リーズほか『ジェントリフィケーション入門』(共訳、ミネルヴァ書房、近刊)がある。
![Read more about the article 【連載】ノン・エクスクルシーブ・ニューヨーク[第4回]/大崎晴地](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2024/04/20230722_142815946-1-768x513.jpg)
![Read more about the article 【連載】誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[第4回]後編/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2022/12/スクリーンショット-2022-12-15-18.00.00.png)
![Read more about the article 誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[第3回]/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2022/05/JO-Paris-2024.jpg)