後期新自由主義──酒井隆史『完全版:自由論』の刊行を契機に
平田周
はじめに
2001年に刊行された『自由論――現在性の系譜学』(酒井隆史・著)は、それまでそのタームすらほとんど知られていなかった「ネオリベラリズム(新自由主義)」によって規定された現在を解読し、そのオルタナティブを希求した先駆的な書物であり、発売から20年近くの時が経過した現在においても、文化社会学、都市研究、社会思想史など複数の学問領域における重要な参照先でありつづけている。
参照されるのはアカデミズムの領域だけではない。当時の私のように、2003年のイラク戦争反対を訴え渋谷などで行われたサウンド・デモに参加するかたわら、この本を手に取った人も多いだろう。それゆえ、この労作が2019年8月に大幅な増補をともない、新たに文庫版として再刊されたことは大変喜ばしい。
以下の小論は、今後も議論されつづけるであろうこの著作に関する一つの議題として、トリノ大学で教鞭をとる都市研究者で、またアウトノミアの議論の場を提供するウェブ・サイト『ユーロノマド・コレクティブ』の編集委員でもあるウーゴ・ロッシ(Ugo Rossi)によって論じられる「後期新自由主義」のテーマと関連させつつ、『完全版:自由論』(2019年、河出文庫)を論じようとする試みである。
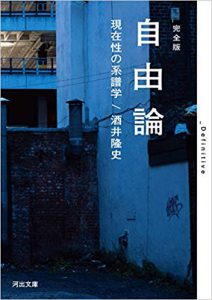
『自由論』のインパクト
さて、『自由論』の新しさは何であったのか。この著作で酒井は、1970年代に展開されたミシェル・フーコーの権力論・統治論に関する従来の理解を根本的に読み変えつつ、それを「使って」新自由主義に至る「現在性の系譜学」を描いた。
主要著作とは異なる独特で紆余曲折とする思考の運動を垣間見せるフーコーの数々の論文や発言を繙きながら、それまで語られていた規律訓練の「ミクロ物理学」といったテーマ系(当時の日本ではフーコー理論の代名詞のように語られ、安直な国家衰退論とも裏腹な関係にあった)に対して、たとえばアントニオ・ネグリとマイケル・ハートが、ドゥルーズの管理社会分析などを通して展開していた、マクロな次元にある「資本」や「国家」(の変容)といったテーマ系と接続し、また君主が有する「死」を与える権力から「生」かす権力へ、という図式的な「生権力」理解に対して、マイク・デイヴィスのロサンゼルス論『要塞都市LA』(2001年、青土社)や犯罪社会学者ジョック・ヤングの『排除型社会』(2007年、洛北出版)で論じられる「暴力」や「排除」といった主題系と切り結び、フーコーの思想的限界にぎりぎりにまで迫ろうと試みた。
しかし『自由論』は、単に思想史の領域にとどまって新たなフーコー像を描いただけではない。
そこで描かれたのは、自らの生活を営むための労働、それが企業のように経営されること――企業家精神――を求められる上に、終わりなき絶えざる自己革新を迫られながらも雇用市場の「弾力性」の名のもとのパートタイム化や失業といったリストラにさらされ競争を強いられるポスト・フォーディズム的な労働・雇用システム、ケインズ的な福祉国家の縮小――緊縮――によるかつて社会化されたリスクの個人への転嫁や自己責任の領域の増大――包摂型社会から排除型社会への移行(ヤング)――、監視カメラを備えた防御壁で覆われたゲーテッドコミュニティによる物理的な公共空間の「プライヴァタイゼーション」と、それによって引き起こされた「分断」に結びついたセキュリティ――他者に対する不信が過剰になって生まれた恐怖――の道徳的内面化――フーコーであれば「ノルム」や「秩序」――とも呼ぶべきものをもたらす管理社会であり、これらすべてによって特徴づけられたネオリベラリズム(新自由主義)の世界であった。
こうした世界は、その言説がもはや空気のように自然なものになった感があるだけになおいっそう2019年の私たちの現在に連なるものである。この著作の冒頭に掲げられたスピノザの言葉「悲しみの受動的感情」はいまだ建設的なかたちで怒りや喜びの共有に変わることなく、何も変えられない、変わらないという諦めの感情として私たちの日常の気分を覆っている。
『完全版:自由論』をめぐって
2019年の『完全版:自由論』に付された増補では、初版の後に出版されたデヴィッド・ハーヴェイの『新自由主義——その歴史的展開』(Harvey 2005=2007)のなかで打ち出された命題「階級権力回復のプロジェクト」としての新自由主義を中心として進められるマルクス主義派の議論に一定の理路を認めつつも、そこには新自由主義を「経済現象」ではなく、国家の介入によって競争的市場を構築することなどを含めた「政治的合理性」として分析する視点が希薄であると指摘している。
その上で、自らと同じく1970年代の「民主主義の統治可能性の危機」という診断を転機として新自由主義を論じたグレゴワール・シャマユーの『統治不能社会――権威主義的自由主義』に自らの議論との一致を見ている。
シャマユーの著作の副題にある権威主義と自由主義の結びつきは撞着語法ではない。それは、国家権力の平面では、政治的決断はその影響範囲を経済によって制限されながらも――自由主義的側面――、民衆による下からの異議申し立てを制限する――権威主義的側面――ようにして、民主主義の原理を遠ざける。
同様に社会的平面では、経営者は市場の代弁者である株主の要求にならって振舞うが、――労働法の規制緩和よって契約関係における雇用者の力が強まり、労働者の地位が不安定化させられたように――彼がその配下に振るう権威は強化される(ある意味で、日本ではこうした権威主義的自由主義の権力関係は、メディアを賑わせている「忖度」という言葉によって最もよく表されている)。
シャマユーがこの著作を通じて示す重要な論点のひとつは次のものである。
この帰結をもたらした新自由主義の理論家たちは、一般的に言われるようにケインズ主義的な福祉国家への対案ではなく、68年の世界的な運動から派生した反国家主義的な自主管理運動――「個人主義の競争」よりも「協働における個人性」のほうが社会的にも歴史的にも優れているという考え――に惹かれながらも、それへの反駁を試みたということにある。つまり、「この巨大な反動は対案への対案だった(une alternative à l’alternative)」。それゆえ結論として導き出されるのは、「権威主義的自由主義に抗して、自主管理の作業場を再開すること」である(Chamayou 2018 : 264-267)*1。

したがって、現在にまで連なる新自由主義の政治的・イデオロギー的推進力の一つとなったものとは、酒井が『自由論』のなかで繰り返すように、1968年に起きた世界的な民主主義的異議申し立て運動に対する反動なのである。
しかし、ここで素朴な疑問を差し挟むことが許されよう。酒井の『自由論』やハーヴェイの『新自由主義』などが出版された時代は、オルター・グローバリゼーションに代表されるようなグローバルな市民社会運動が成果を上げ、2008年の金融危機の後にはオキュパイ・ウォールストリートのような大きな社会運動が立ち上がり、それに呼応するように、アメリカ(オバマ政権(2009-2017))やフランス(オランド政権(2012-2017))で左派政権が生まれた時代である。そこから今日のトランプ政権に象徴されるような権威主義的ポピュリズムの台頭や反グローバリズムの「右」旋回と呼ばれるような時代に移行するなかで、新自由主義はどのように存続したのであろうか。
この点に関して、酒井が新自由主義を存続させる強力な要因として挙げる「日常的ネオリベラリズム」および「創造都市」と「ジェントリフィケーション」の関係をめぐる議論は重要である(酒井 2019:523、541-542、引用ママ)。
以下では、この論点を深めるために、ウーゴ・ロッシによる「後期新自由主義」に関する分析を参照しよう(Rossi 2017a; Rossi 2017b; Enright and Rossi 2018)。
後期新自由主義──クリエイティブ・シティと共有経済
住宅と金融の結びつきが主要な要因であった2008年のグローバルな経済危機の後に、なぜ新自由主義は存続したのか、という問いについて、このアウトノミアの若き論客は簡潔に次のように答える。新自由主義が自らの延命のために利用してきたものとは、――2007年のiPhoneの発売に象徴されるような――「テック・ブーム」にほかならない。
サンフランシスコのシリコンヴァレーに集積し、今や世界の株式ランキングトップテンを占めるGAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)によって提供される何らかのサービスに触れない日はないと言っても過言ではない。
しかし、こうしたハイテック産業への公的資金の投資がこれまでの公共事業と比べて雇用を増やすことはなく、またその恩恵を受けた企業が減税措置や租税回避を利用するため、国家の税収増になることもなく、むしろこうした政策が先進国の不平等の拡大に結びついているという問題も指摘されてきている(隠岐 2018)。
ロッシの議論が興味深いのは、こうした1990年代中頃におけるインターネットの普及から2000年代中頃に拡大するスマートフォンの利用に特徴づけられる情報・モバイル・テクノロジーの発展に至る情報社会化と2008年の金融危機以降の新自由主義との関係を問い、「後期新自由主義」と対象化したことにある。
この問いの枠組みにおいて、ロッシは、「ポストフォーディズム的労働」や「生政治的労働」の議論(Hardt and Negri 2009: 133-42=2012)を参照する。生政治的労働とは、「資本の外部にありながらも資本が自らのうちに社会や生活そのものを包摂することによって自らのものとする一連の知識、情動、社会関係」に依拠した労働である(Rossi 2017a: 74)。
こうした知識集約型のポスト・フォーディズム的労働は、「クリエイティブ・シティ」や「スマート・シティ」といった都市政策によって取りまとめられる。クリエティブ・シティ論は、トロント大学の都市計画を専門とするリチャード・フロリダの著作(Florida 2002=2008)のなかで定式化されたものである。その要点は、
(1)(建築家やエンジニアからソフトウェア開発者やデザイナーに至る)クリエイティブな知識を用いる職に就くクリエイティヴ・クラスが、民族的・性的マイノリティに寛容で、芸術家のような共同体に類する多様性を持った都市環境を作り出し、
(2)その協働的な労働環境とともに能力主義や個性の思想に基づく価値と態度を共有する共同体を作り出す、
というものである。
世界中の都市がクリエィティブ・シティ政策を合理的なものとして都市ガバナンスやプランニング戦略に組み込んだのだが、それはしばしば単に以前からあった都市再生の構想を名づけ直しただけなのであった」(Rossi 2017a: 69)。しかしこのことは、単にクリエイティブ・シティ論が、「都市を売り出す」ための新自由主義的都市政策における「空虚なレトリック」(Wiig 2016)であるということにとどまるのではない。むしろ、クリエイティブ・シティ論は、都市環境およびそこで生まれる社会的情動という経済的外部性を占有する試みとして広まっているということをロッシは強調する。
この都市環境の占有という論点、すなわち酒井が指摘した「創造都市」と「ジェントリフィケーション」の関係に関して、ロッシはこう述べる。「西洋の都市では、(中略)クリエイティブ・クラスの存在は疑いなくジェントリフィケーションの過程と、とくに歴史的地域における地元の帰属意識の除去と結びついている」(Rossi 2017a: 105)。
シカゴ、ワシントン、ボストン、ニューヨークのような経済的にダイナミックな都市におけるクリエイティブ・クラスによる下町の植民地化が、施設や労働者階級の住人を中心部の外にある最も望まれない場所に追いやり、社会空間的な隔離を作り出しているという事実を、フロリダ自身が最近の共同研究者との論考で認識している(Florida et al., 2014)。
しかしその対案として、クリエイティブ・シティは万人に開かれていなければならない、という趣旨で提出された「クリエイティブ・コンパクト」に関して言えば(Florida 2012=2014)、「財政的インセンティブ、小さな政府、コーポラティズム〔利害集団間の調整〕といった新自由主義的合理性のお決まりを反映する一連の推奨に基づき、文化とライフスタイルの観点で都市環境の魅力を改善することを目的とした措置によって補完された、「薄い政策」的提案」でしかない(Rossi 2017a: 107)。*2
酒井が指摘した存在の奥深くにまで浸透する「日常的ネオリベラリズム」という論点に連なる資本による社会的情動の包摂に関して、ロッシは、住宅、交通、飲食、教育といった都市環境と結びついた消費セクターにおいて、インターネットのプラットフォーム企業を介して成立する共有経済(sharing economy)を分析する。それは新たな文化とそれに関連する生活様式を生み出す。「共有経済は、社会や生そのものの包摂を深めることが資本主義の回復や再発明の過程に必須のものとなったことを示すものである」(Rossi 2017a: 168)。
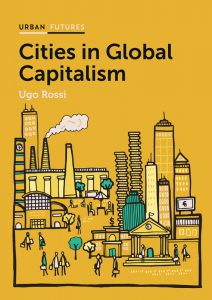
この点で、共有経済のパイオニアである配車サービスのウーバーや民泊のエアビーアンドビーなどのデジタル技術を介したプラットフォーム企業がそれぞれ2008年と2009年に創業し、アメリカの景気後退に終わりの兆しが見えた頃に収益を上げ、存在感を増したことは特筆に値する。*3
共有経済は、デジタル・テクノロジーを介した「マッチング」によって、日々営まれる様々な生活形態に応じて、労働の需給関係を調整する。「無償性」「主体性」「相互性」「出会い」、そしてそれらから生まれる「コミュニティ」によって特徴づけられる経済を、西欧の政府やEUのアドバイザーも務めたジェリミー・リフキンは「協働的コモンズの現象」として述べるが、それは必ずしも新自由主義的な企業家精神――刹那的な利益追及の個人化――から免れていない点において、「両面価値的なもの(ambivalent)」が含まれているのである(Rossi 2017a:181)。
ここでの議論はもちろん、テクノロジーそのものに対して肯定や否定の評価を下すことでも、それにとって重要なのは使い方次第であると言うことでもない。固定電話の普及をまたずに携帯電話が普及した中国やアフリカの国々の人々にとって、またフランスやイタリアなどの先進諸国に暮らす移民にとって、こうした共有経済が日々の生活の糧となっている現実を否定することはできない。しかし、テクノロジーが可能にした新しい働き方と言われるものが、労働とその疎外の関係という「旧い」問題を呼び込むのものではないか、と問うてみる必要があるだろう。
2016年3月に惜しまれながらも亡くなった澤里岳史が、脱工業化社会の労働をめぐる言説について次のように問うたように。
疎外の克服をめぐる言説は、産業構造の変動が工業の時代における闘争の成果を次第に圧迫しているという事実を考慮に入れずに展開されるならば、不十分かつ危険なものであるだろう。労働者の主体性の獲得と彼らの権利の縮小が並行する、さらには前者が後者の結果として成立するという事態が生じうるのであり、それは脱工業化における現実にほかならない(澤里 2018: 134、強調引用者)。
もしテクノロジーによって利用者にもたらされた多幸症的な全能感が、自らを保護し「私たち」の紐帯にもなってきた社会権の漸次的消滅と結びつくのであれば、これほどおぞましくも滑稽な技術的成果を示すものも歴史上類を見ないのである。
繰り返せば、『自由論』が完全版となって再び刊行されたことは大変喜ばしい。しかしそれは単に過去の思想的営為を証言するからというだけでなく、この著作が私たちを突き動かす不透明な現在を解読し、自律的で自由な領域を作り出す契機や手がかりでありつづけているからである。それゆえ、『自由論』は今後も日々の生活のなかで読まれ、それをめぐって議論され、そこからさまざまな方向に議論の線が引かれていくことだろう。
その意味で、ロッシの「後期新自由主義」というテーマを用いて、『自由論』の初版(2001年)と完全版(2019年)のあいだの時間に時期区分を導入しようと試みた本小論もまた、無数に引かれていく議論の線の一本として書かれたのである。
注
- 1938年のフランスにおけるリップマン・シンポジウムを起点として1947年のモンペルラン協会の設立によって構築されていく理論としての新自由主義ではなく、1970年代以降に具体的に運用されていく実践としての新自由主義に焦点を当てるという点では、ハーヴェイの議論に依拠するニール・ブレナーとニック・セルドアの「現存する新自由主義」に関する議論は、酒井のそれと共通する部分があるように思われる(Brenner and Theodore 2002)。この点については東京をめぐる1980年代後半以降の世界都市仮説の議論から2000年代以降の新自由主義化する都市の議論に至る変遷を考察した丸山(2010)を参照。新自由主義の東アジアへの定着について、それを、北米のケインズ主義福祉国家に対するアジアの開発主義国家というレギュラシオン経済学の国家類型との制度的相互作用や葛藤の関係から分析したものとしてPark, Hill and Saito(2012)を参照。 ↩︎
- 以上のクリエィティブ・シティとジェントリフィケーションの関係をめぐる議論は、平田周・仙波希望(2019)の対談のなかで議論を十分に展開できなかった部分を補足するものでもある。 ↩︎
- 「こうした活動は、貧窮する中間層に副業的収入の機会を提供しようとする。さらに文化的には、こうした経済活動は対面的な接触と協働に基づいた人間経済という感覚を伝達する。しかし、それは資本主義社会において共有可能な実物を私的所有物と感じるような幻想を与えるだけである。しかし同時にこのテクノロジーに基づく経済は、搾取と自己搾取の新たなかたちを作り出すことで、生活を全体として商品化していく資本主義の傾向に光を投げかけるものでもある。この文脈において、史的資本主義の時代にはあったような労働の場と私的領域の間の厳密な区分はもはや存在しないのである。むしろ室内の空間と自家用車は資本主義的な価値生産(valorization)の回路のうちに直接包摂されることになる」(Rossi
2017a: 9)。 ↩︎
参照文献
Chamayou, Gregoire. (2018) La Société ingouvernable: Une généalogie du libéralisme autoritaire, Paris, La Fabrique.
Enright, Theresa. and Rossi, Ugo. (2018) Desiring the Common in the Post-crisis Metropolis: Insurgencies, Contradictions, Appropriations, The Urban Political: Ambivalent Spaces of Late Neoliberalism, Cham: Palgrave Macmillan, p.45-64.
Florida, Richard. (2002) The Rise of the Creative Class, New York : Basic Books.〔= (2008)井口典夫訳『クリエイティブ資本論—新たな経済階級の台頭』ダイヤモンド社。〕
Florida, Richard. (2012) The Rise of the Creative Class – Revised and Expanded, New York : Basic Books.〔= (2014)井口典夫訳『新クリエイティブ資本論—才能が経済と都市の主役となる』ダイヤモンド社。〕
Florida, Richard., Matheson, Zara., Adler, Patrick. and Brydges, Taylor. (2014) The Divided City: And the Shape of the New Metropolis, Toronto: Martin Prosperity Institute.
Hardt, Michael. and Negri, Antonio. (2009) Commonwealth. Cambridge, MA: Havard University Press.〔= (2012)水嶋一憲監訳・幾島幸子・古賀祥子訳『コモンウェルス(上・下)』NHK出版。〕
Harvey, David. (2005), A Brief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University Press. 〔= (2007)渡辺治監訳『新自由主義—その歴史的展開』作品社。〕
Park, Bae-Gyoon., Hill, Richard Child. and Saito, Asato. (ed.)(2012)Locating Neoliberalism in East Asia: Neoliberalizing Spaces in Developmental States, Oxford: Blackwell.
Rossi, Ugo. (2017a) Cities in Global Capitalism, Cambridge: Polity Press.
Rossi, Ugo. (2017b) Neoliberalism. Jayne, Mark and Ward, Kevin (ed.). Urban Theory, New Critical Perspective, London and New York: Routledge, p. 205-217.
Wiig, Alan. (2016) The empty rhetoric of the smart city: From digital inclusion to economic promotion in Philadelphia. Urban Geography 37(4): 535-553.
隠岐さや香(2018)「高学歴競争の過熱と不平等の拡大――イノベーション政策2・0の負の遺産」『文系と理系はなぜ分かれたのか』星海社、145−148頁。
酒井隆史(2019)『完全版:自由論――現在性の系譜学』、河出書房新社。
澤里岳史(2018)「労働するとは別様に――生政治的生産の時代における人間活動」『交域する哲学』、月曜社、133-151頁。
平田周・仙波希望(2019)「進行形の都市研究を立ち上げる──プラネタリー・アーバニゼーションは遷移、侵犯する」『10+1 website』6月号。以下のサイトで閲覧できる。
http://10plus1.jp/monthly/2019/06/issue-01.php
丸山真央(2010)「ネオリベラリズムの時代における東京の都市リストラクチュアリング研究に向けて」『日本都市社会学会年報』28、219−235頁。


