【論考】無感性的暴力──パレスチナにおける植民地的取り締まりとアナーキー
イアン・アラン・ポール
北川眞也 訳
編集部より
原題「Anaesthetic Violence」と銘打たれたこの記事は、2023年12月16日にIll Willにアップされた。以前、本サイトでは同じ著者の「海とセキュリティ・フェンスの狭間で――パレスチナにおける植民地的抽象とジェノサイド」をやはり北川眞也氏の翻訳で掲載したが、本記事は実質的にその続編とも言うべきものである。
なお、8月28日(水)にジュンク堂書店池袋本店にて開催されるマニュエル ・ヤン『バビロンの路上で――律法に抗う散歩者の夢想』の刊行記念イベントに、北川氏は登壇予定である。以下の詳細、申込方法をご覧のうえ、ぜひご参加いただきたい。https://honto.jp/store/news/detail_041000100244.html?shgcd=HB300
アーティストのヤザン・ハリリは、「言葉の自由、音の自由」という小論のなかで、ヨルダン川西岸のある街に友人らと集まり、パレスチナ自治政府によるイスラエルとの安全保障協力を嘲笑するグラフィティを描こうとしたことを回想している1。パレスチナ自治政府の警官が近づいてきて、そこに描くのは禁止されていると指示してきたのだ。その後、ハリリは以下のことを理解した。
エルサレムに向かう途中の街のはずれにあるイスラエルが建設した壁は、政治的内容のグラフィティを描ける唯一の空間となっていた。イスラエルの人びとは、それがパレスチナ側である限りは、パレスチナ人が描きたいものは何であれ壁に描くことを許可していた(…)けれども、イスラエル側に何かを描くことは厳しく禁じられていた。
この土地の分割=共有(partitioning of land)は、感性的なものの分割=共有(partitioning of the sensible)としても機能しており、植民地的取り締まり[ポリシング]について検討するための出発点として、ハリリによって取り上げられたものだ。つまり、誰が、何が、どこで現れてよいのか、何が言葉として聞かれ、何が音として無視されるのか、何が意味をなすことを許可され、何が意味をなすことを禁じられるのかをめぐる植民地的取り締まり[ポリシング]である。ハリリの小論は、ジャック・ランシエールの仕事を利用しており、場所と人びとに対するこの感覚的な取り締まり(sensual policing)が、パレスチナの全体においてどのように生を編成しているかを理解する手助けとなる。ある人はエルサレム旧市街の景色へと滑らかに溶け込んでいくことを許されるが、別の人は目について尋問と逮捕にさらされる。ある集団はハイファの路上でシュプレヒコールを大声で上げ、派手にデモをすることを許されるが、別の集団はこん棒でぶん殴られ、解散させられる。あるドライバーはベツレヘムのはずれにある検問所[チェックポイント]を自由に通り抜けられるが、別の集団は制止され、身体を調べられる。こうした取り締まり[ポリシング]の形態のいっさいが、ランシエールが社会生活の根幹にある感性論=美学(aesthetics)として述べるもの、すなわち、誰が、どこに、何のために属しているのかを確立し、遵守させる感性的な分配(sensible distribution)に立脚しているのだ2。
パレスチナをめぐる感性的=美的取り締まり[ポリシング]は、イスラエルの植民地的支配(archē)とその階層的秩序の確立を手助けすべく機能している。そこにおいて、生は割り当てられた分け前、割り当てられた居場所を守ることを強いられる。この取り締まり[ポリシング]は、毎朝パレスチナ人がイスラエルの入植地の入口で自分の携帯電話を渡すよう指示され、かれらが報酬のため果物を収穫する農場の写真を撮れないようにするときのように、日常生活の低周波において作用している。しかしまた、ヘブロンを歩くパレスチナ人がイスラエル兵に事もなげに「ここを歩けるのはユダヤ人だけだ」と告げられるときのように、はっきりとわかる強度においても作用している3。このようにして感性的なものの植民地的行政管理は、誰が分け前を持つのか、こうした分け前の取得がどのように社会的に分配されるのか、こうした参加がどのようなかたちをとるのか、とらないのかを取り締まるのだ。共通感覚と呼ばれるものは、ポリス、すなわち経験と知覚の限界に設置される検問所[チェックポイント]や監視塔、あるいは、社会生活全体の輪郭を形成し横断する感性的=美的行政管理がもたらす感覚的秩序のことにほかならないのである。
この感性的なものの分配のなかで、ランシエールは唯一真に政治的な応答とは、こうした形態の取り締まり[ポリシング]に逆らい、闘うことであると主張する。このような政治はいつも、いっさいの支配(archē)の根底にありつつ、それをおびやかすアナーキーとして生じる。政治とはつまり、感性的=美的秩序をつねに粉砕、変容させようとする手に負えない無秩序として生じるのだ4。確立済みの感性的=美的地勢に挑戦し損ねて、所与の分け前のヒエラルキーと秩序をシャッフルし、再編するために機能するだけであるなら、政府、政党、デモ、ストライキ、そして革命ですら政治的であることに失敗する。この感性的=美的フレームのなかでは、イスラエル国家とパレスチナ自治政府は両者ともに完全に非政治的なのであり、ポリスの働きと区別不可能な占領の分割=共有の論理を再生産し、再調整することに役立っているだけである。つまるところ、ランシエールにとって政治とは、数えられておらず、分け前を持たない者たちが、おのれを数え、おのれの分け前を取得しはじめて――労働者がおのれをプロレタリアとして認識する、女性がフェミニストとして認識する、植民地化された者が人民として認識するなど――、感性的なものの分配を切断し、新たな分配を強制するときにのみ生じるのだ。一方には、社会の支配(archē)をコード化し、遵守させるポリスがある。他方には、社会秩序の感性的=美的行政管理に混乱を与え、リセットする脅威をつねに与える政治的アナーキーがある。
ランシエールのアプローチは、階級闘争から家庭生活、現代アートまで、あらゆるものを理論化するべく広く展開されてきたが、パレスチナで進行中のジェノサイドに対峙するとき、ランシエールの企ての限界があらわとなる5。イスラエルがパレスチナ全域でアパルトヘイトを維持し、ガザを荒廃させる動きを強めるとき、植民地的・社会的秩序が感性的=美的なもの、つまり誰が分け前を持ち、受け取るのかを決める生への取り締まり[ポリシング]だけではなく、わたしが無感性的(anaesthetic)と呼ぶもの、すなわち参加ではなく、根絶を実現する生への取り締まり[ポリシング]にも依拠していることがこれまで以上に明らかとなっている。
無感性的暴力は、生をこれまでになく正確に数える。ただ生の破壊をこれまでになく正確に算定できるようにするためだけに。無感性的暴力は、生に分け前を割り当てる。ただ生をより広範囲に浄化する動きに加わるためだけに。無感性的暴力は、生をこれまでになく可視的にする。ただ生をさらに完璧に消去できるようにするためだけに。無感性的なものは、感性的=美的なものの形式的反転なのであり、支配(archē)や秩序をかたちづくる手段としてではなく、アナーキーで混乱したものを壊滅させる手段として分け前を配分し行政管理するのだ。感性的=美的なものは、おのれの内側において分け前の計算と分配を生み出し維持するのであるが、それゆえに数え損ねるもの、参加し損ねるものという余分なものにおのれをさらすことになる。他方、無感性的なものは、形式的に包囲し、続いて根絶やしにする目的で、余分なものへと向かっていく。それゆえ無感性的なものは、本来的には相反する形式的論理、つまり感知することと破壊することにつねに固執するのである。感性的=美的なものと無感性的なものは、資本主義的かつ植民地的秩序を補完する次元として展開しており、前者は生を行政管理し、後者は生を消滅させる。
イスラエルの無感性的暴力の研ぎ澄まされた殺戮は、多数のデジタル技術を通じておびただしいほどに循環しており、かつてなくネットワーク化された破滅の波を植民地化された者にもたらすことで植民地プロジェクトを前進させる。イスラエルは自国の最先端の監視技術を誇りにしている。そうした技術は、占領する領域のありとあらゆる小片を記録し、情報学的な仕方で取得しようとするものである。植民地的諸装置の内側へと壊滅させるものを情報学的に統合し、その中身を理解することに照準を合わせるのだ。ドローンがパレスチナ人居住地域の上空を旋回して映像をストリーミングし、顔認識技術が検問所[ポリシング]にはびっしりと配備され、携帯電話の位置と会話はいたるところで追跡されている。けれども、こういった監視のいっさいは、こうして詳細に記録するものを抹消し、感知可能となったものにジェノサイド的破壊をもたらそうとする植民地プロジェクトの一環としてのみ行われている6。パレスチナにおいて、支配する者たちにもっともはっきりと声を聞かれ、もっとも見られているのは、まさしく支配される者たちなのだ。パレスチナでもっとも徹底的に記録され、監視され、感知されているのは、支配される者たちである。パレスチナで進行中のジェノサイドのなかで、居場所と分け前を割り当てる無感性的暴力にさらされているのは、支配される者たちなのである。
感性的=美的なものは政治と対立するポリス的秩序として機能する一方、無感性的なものはポリスの政治として作用する。無感性的なものはつまり、アナーキーを、浄化を進める自らの暴力の仕組みの内側で計算=考慮に入れられ、分割=共有されるべき対象とみなす、支配(archē)として作用するのである。感性的=美的レジームでは、数字は追跡し、社会で分け前を持つすべての者の生政治的座標を配分する手段として身分証明書に印刷され、データベースに保存される。その一方、無感性的レジームでは、数字は腕に刻まれ、絶え間なく作動するさまざまな死の機械へ情報提供を行う手段として、ドローンの映像上に表される7。感性的=美的なものから無感性的なものへの変移はここにおいて、足し算の論理から引き算の論理への変移を表す。つまり、社会的分配のなかに生を足し算し統合する計算から、生を引き算し、存在から除去する計算への変移だ。こうして無感性的なものは、差し引きの計算訳注1に依拠する。つまり、特に余分なものへと暴力を配分し、割り当てるために、事物を除外するマイナス方向への計算〔10、9、8……という数え方〕という、並行するプロセスに依拠するのである8。いわゆる国際社会が暴力の比例的な量について議論しているとき、かれらが実際に決めたがっていることは、感性的=美的暴力と無感性的暴力の正しい割合であり、パレスチナ人にとってのアパルトヘイトとジェノサイドとの正しいバランスにほかならない9。
パレスチナに対するイスラエルの無感性的攻撃は、今や基本的にデータとして生を数え、分割=共有している。それは、ジェノサイドの自動化をますます可能とする抽象の展開である。『+972マガジン』が公表した記事内でイスラエル軍内部の情報筋は、ガザの軍事的破壊がハブソラ(福音)として知られるシステム、すなわち「「数万人の情報部員が処理できなかった」膨大な量のデータを処理し、リアルタイムで爆撃場所を推奨する」人工知能(AI)技術にいかに依拠しているかを語っている10。こうしてパレスチナ全域に配備されたデジタル化された監視装置が、ありとあらゆるパレスチナ人の生についての莫大な量のデータを生産している。そのデータのすべてが「大量暗殺工場」へと供給され、それを通じて「軍隊は攻撃を実際に行うよりも速い速度で新たな標的を生み出すことが可能となっている」。「殺害される可能性のある民間人の数は(…)算出されているのであり、軍隊の諜報部隊には事前に知られている」11。イスラエル軍は、ハマース〔イスラーム抵抗運動〕のメンバーのみを標的にしていると主張し、殺害された民間人については巻き添え被害(collateral damages)であるとしている。けれども、こうした技術の使用が明らかにするのは、殺戮がはじまる以前に死者のすべてが計算=考慮に入れられているということ、つまり一人ひとりの生を感知し、一人ひとりの生へと爆弾を向けるデジタル化された技術のただなかで、そうした生は適切な分け前を割り当てられているということだ。無感性的レジームにおいては、巻き添えの死者は、計算装置のなかで照合されている。そこにおいて生は数えられ、算定され、それから殺害される。
数々の爆弾がすでに投下されていたが地上侵攻ははじまっていなかったとき、ドローンで大量のビラをばら撒いて今後の暴力を警告するイスラエル軍によって、パレスチナ人はガザの南半分に避難するよう命じられていた。このナクバ〔大厄災〕の続きを生き延びようと願って逃げることを選んだ人たちは、自分の荷物をまとめ、家をやむなくただちに捨て去り、避難路にそって設置された監視技術搭載の輸送コンテナを通り抜けることを強いられた――かれらの顔をイスラエルの生体認証データベースと照らしてチェックするためである。このデータベースは、避難者たちをふるいにかけて精査し、追加的ターゲットを抹殺するために設計されている12。ひとたびガザ南部にたどり着きはじめると、新たなビラが上空から投下され、人びとはそれを受け取る。このビラにはオンラインマップへのリンクが貼られている。ガザはそこで、番号の振られた数々の小区画からなるグリッドへと分割されており、まさにそれゆえに、イスラエル国防軍は避難を命じ、より細かなスケールでの作戦を実行できるのである。このオンラインマップは、必要に応じて数々の殺人地帯を設け直すことが可能な空間へと、ガザの地勢を無感性的な仕方で改変しているわけである13。人びとに住んでいる場所から逃げるよう強いるだけでは十分ではない。スナイパーの銃弾と戦車の砲弾のもとで縮み上がらせるだけでは十分ではない。病院も学校も安全ではないと教えるだけでは十分ではない。分厚く積もった燃え盛るほこりや瓦礫のなかに埋めるだけでは十分ではない。飢えに苦しませて、水を止め、電気の供給を止め、通信手段をカットするだけでも十分ではない。領域全体を封鎖することで必要物資の深刻な不足を引き起こし、緊急治療の切断や外科手術が麻酔薬のない状態で行われねばならないというだけでも十分ではない14。ジェノサイドの無感性的な論理は、生がこのすべてに耐え忍ぶことを要求するのみならず、生が絶滅させられるときに、生が記録され、分割=共有され、計算=考慮に入れられること、生とその殺戮の両方が感知可能となることを要求するのである。
大量殺戮をめぐるこの感覚的分割=共有は、大規模な爆撃と地上侵攻の後、つまり生存者が世界じゅうの聴衆に自分たちが被った絶滅についての詳細な証拠を提出することを期待されるときに、無感性的な仕方で反映される。無感性的なものが再帰的に現れ状況を支配するために、パレスチナ人居住地域の衛星によるマッピング、ドローンによる撮影、それに続く瓦礫化が、その後のプロセス、つまり廃墟と死と破壊を記録し、オンライン上で流通させていくプロセスの単なる第一段階となっている。生と死は、軍事行動のなかのデータ点、ジェノサイド的装置のただなかで認識され、記録される暴力的な小さな点[ブリップ]――それ自体がジェノサイド的装置によって惹起させられている――としての意味しかなさないようになる。イスラエルは自らがパレスチナにもたらす荒廃を成功の証拠として持ち出すと同時に、瓦礫のなかで生き残った人びとには、〔パレスチナ人は〕自分たちで自分たちを爆撃したのだと伝え、状況をジェノサイドの「進展」のみを明らかにするかたちの証拠へと切り縮めてしまう。それ以上明らかすることは何もないと。この無感性的な文脈において証人になることは、ポリスの証人という役割を担うよう宣告されるということである。それは、自身のまわりの人びとの生と死を、ジェノサイドの勝利による見事な戦利品としてのみ証拠を蓄積する諸勢力の尋問と検証にさらすということである。パレスチナ人居住地域が背後で爆撃されているときに、イスラエル兵の集団が微笑みながら自撮りしているように、こうした病的な自尊心は行為遂行的なかたちで表される。
ここで最終的に無感性的なものは、口語的用法に近い何かに類似するようになる。最初は破壊する感覚(sensing)として機能するが、その後に感覚を破壊する暴力へと達するのである。爆弾がガザの住宅建物のなかで爆発するとき、それは天候や空模様から屋内を保護していた屋根を吹き飛ばす以上のこと、寝室と台所、保育園と図書室、庭とシャワー室を隔てていた壁を瓦解させる以上のこと、建物の住人を瓦礫の山の下敷きにする以上のことを行っている。爆弾は感覚を破壊する暴力の形態としてもまた機能しているのである――内か外か、既知のものか未知のものか、馴染みのものか見知らぬものかといった、あらゆる感覚を爆破するのである。それは、建物と身体をともに瓦礫と肉の山へ、生き残った人びとによって理解されることはおろか、分類されることにすら抗う瓦礫と肉の山へと粉々に砕いてしまうのだ。イスラエルによる爆弾の雨は、ある場所と他の場所、この生とあの生のあいだの差異を吹き飛ばし、生存者たちをトラウマとショック状態のなかで生き続けさせる。かれらは、自身のまわりの破壊された世界を理解することがもはやできないことに気づく。こうして植民地的レジームの軍事化された感覚は、世界と生そのものをますます無意味なものにする暴力の諸形態へと、もはやきちんと分割=共有もできないし、はっきりと認知もできない廃墟へと、そしてただジェノサイドとしてしか理解できないものへと流れ込んでいくのだ。
イスラエルの無感性的な植民地的暴力のなかで、パレスチナ人の生は最終的に、処分可能、廃棄可能な物質へ、アシーユ・ンベンベが「廃棄物と同種の人間」と呼ぶものへと変容させられる15。感性的=美的なものが生の座標を設定し、無感性的なものが死の座標を設定するとき、生をポリス的秩序のなかに位置づけるため、ないしは処分するために、生には分け前が割り当てられる。ガザとヨルダン川西岸は、植民地プロジェクトの残滓として、その除去を十全に確認し達成するためだけに、完全に分類され、目録化される必要のある遺物としてのみ理解されるようになる。ここにおいて、シオニストの幻想、つまりイスラエルが砂漠に花を咲かせることになるという幻想は、イスラエルが支配する生が結果的に残骸として枯れ果てるという現実に照らして読み直されねばならない。イスラエルの無感性的暴力の流れのなかでは、あらゆるものがこれまで以上により高い迫真度で理解されるが、それはただ世界の表面全体に広がり、ますます植民地化がなされていく荒れ地をよりうまく取り締まり[ポリシング]、浄化する手段としてのことにすぎないのだ。
感性的=美的なものがそのアナキズム的基盤を分割=共有し、取り締まる[ポリシング]支配(archē)として機能し、無感性的なものがアナーキーなものの根絶に基づいた支配(archē)として生じるのなら、アナーキーそのものにはいったい何が残るというのか? ランシエールにとって、政治のアナーキーは、まさにそれが対峙しようとするポリス的秩序にくくりつけられるときに終焉に至る。政治のアナーキーはおのれをアナーキーそれ自体として実現することはない。アナーキーな仕方で社会秩序をただ再編し、それからその秩序の内側へと再吸収されるだけである16。この意味でランシエールは、アナーキーなものの政治を、ポリスの秩序を改革し、分配し直す手段としてだけみなしている。そして最後には、アナーキーな政治を、それを凌いでは鎮圧する取り締まり[ポリシング]を超えては決して存続することのない稀な出来事であると結論づける。この飼い慣らされ、抑制されたアナーキーの理解を受け入れるとすれば、世界の感性的=美的かつ無感性的な行政管理がアナーキーの本質的な一部分であることを受け入れなくてはならなくなる。これが生を成り立たせるものなのだろうか? 取り締まられるか、根絶させられるかを選択することが。
わたしはヨルダン川西岸の町アブ・ディスで授業を担当していたことがある訳注2。その間、学生、職員、教員たちとともに構内に出入りするたびにいつも、大学の入口がある通りのちょうど反対側に建設された分離壁の脇を歩かねばならなかった。壁にはエルサレムの絵や青い波がうねっている絵が描かれており、كفاية(キファーヤ、「十分だ」の意味)のようなスローガンが走り書きされていた。また、そこで定期的に繰り広げられていたイスラエル国防軍のパトロール部隊との衝突のあいだに放たれた多数の火によって、壁のところどころが黒く焦げていた。壁にはひとつ穴があった。学生たちによって開けられたものだ。学生たちはクーフィーヤで顔を隠し、ハンマーで壁のコンクリートを打ち砕いたのだ。それは腕を通せるぐらいのものであり、それ以上の隙間はない。この穴は分割=共有の一部ではなく、単純にその不在として存在する。この穴は、まさしく植民地世界の一部が解体され破壊されたという理由ゆえに、その否定性においてのみ知覚し、経験することができる裂け目(opening)として存在するのだ。この分け前の否定、生の分配と行政管理を突き抜けるこの穴は、アナーキーについての異なる考え方を追求しはじめられる場所、つまりアナーキーを完全に捕捉し、束縛しようとするポリス的秩序から生を解放しはじめる可能性を宿す場所なのである。
この穴は、壁の進路をより好ましい方向、より公正な方向、より民主的な方向へと変化させることを望んだものではなかったし、あれやこれやと美的価値を加えようとするものでもなかった。この穴は、壁の不在の証拠、かつて分割=共有があったが、もはやそれがない世界の証拠としてのみ存在したのだ。この穴の真の美点は、それが誰にも何も証明する、説得する必要がなく、計算=考慮に入れられることも、理解されることも必要としないという事実、その存在が表象されたり数えられたり、表示されたり検証されたり、定義されたり区切られたりすることに依拠しないという事実にこそ見出せる。この穴はむしろ、それそのものとその現実の証拠、ポリスを超える存在の証拠、アナーキーの証拠なのである。構築された秩序の脱構築、植民地的形式の脱形式化、そして分割=共有からの離反のただなかに、アナーキーなものは存している。権力の構造におけるこの空隙は把握することができないものであるが、それにもかかわらず、すべてを把握しようとするものの廃絶として存在する。アナーキーそれ自体のようなものがあるとすれば、足し算されることも引き算されることもなく、支配の計算式を無効にし、すべての構成された権力に特有の計算と分け前を拒否し、その代わりに、物事のまさしく核心に裂け目をつくりだすこうした実践とレパートリーにこそ見出されるのだ17。その植民地的破壊から逃れ、ポリスから、分割=共有からおのれを解放することのできるパレスチナの可能性は、感性的=美的かつ無感性的な世界のなかに穴を開け、見るべきものではなく、そこからのぞき見ることを可能とするものを与えてくれる、こうした生のなかでこそ存続する。
2023年12月
注
- Yazan Khalili, “Freedom of Speech, Freedom of Noise.” e-flux journal, February, 2019. Online here. ↩︎
- ランシエールは感性的なものの分割=共有(distribution)を、以下のように定義している。「感性的な諸明証性がなす体系のことであり、それが共同なるものの現実存在と同時に、そこでの各々の居場所と分け前を規定する区分を目に見えるようにする(…)この分け前と居場所の配分は、空間、時間、そして活動形式の分割=共有〔partage〕に基づいており、この分割=共有が、ある共同のものが分有に供される仕方そのもの、そして各々がこの分割=共有の分け前に与る仕方そのものを規定している」(Jacques Rancière, The Politics of Aesthetics, Continuum, 2004, 12〔ジャック・ランシエール(梶田裕訳)『感性的なもののパルタージュ――美学と政治』法政大学出版局、2009年、6−7頁、〔partage〕は北川が追加した〕)。 ↩︎
- “Separation policy in Hebron: Military renews segregation on main street; wide part – for Jews, narrow, rough side passage – for Palestinians.” Online here. ↩︎
- ポリスが課すコンセンサスに対して、ランシエールはこう論じる。政治は「「支配 [archē]」の論理の特殊な切断である。政治は、実際に力を及ぼす者と力を被る者との間の位置を「規範的に」分配する切断であるだけなく、この位置を「固有なものに」する配置の理念の切断でもある」“Ten Theses on Politics,” Theory & Event 5, no. 3 (2001)〔ジャック・ランシエール(杉本隆久+松本潤一郎訳)「政治についての10のテーゼ」VOL 1、以文社、2006年,26頁〕。 ↩︎
- ランシエールは剥き出しの生という概念を拒否しているが、それは絶滅させられる者たちもまた数えられることを理解し損ねているからである。結局のところ、これはランシエールのプロジェクトの失敗を表している。この点で例示的なのは、アガンベンのホロコースト分析に対するランシエールの反応だ。ランシエールは、デモス(民衆)は剥き出しの生という不確定な場所としてではなく、「数えられないものの計算(the count of the uncounted)」として、「あるいは、分け前なき者の分け前として(…)数えられないものの計算を余分なものとして刻み込む余分な主体」として理解せねばならないと論じている。そうすることでランシエールは、数えられないものの計算が、さまざまな仕方でジェノサイドの対象となる形式、ジェノサイドにより抹殺すべき余分となる形式を把握し損ねている。以下を参照。Jacques Rancière, Dissensus, Continuum, 2010, 70. ↩︎
- パレスチナの文脈において、こうした感知の形態が抽象の形態としてどのように機能しているかを理論化する作業については、わたしが以前に書いたテクスト“Between the Sea and the Security Fence” (Online here)を参照〔日本語版「海とセキュリティ・フェンスの狭間で――パレスチナにおける植民地的抽象とジェノサイド」はこちら〕。 ↩︎
- 腕に数字を書き込むことは、20世紀、21世紀を通じて公式に縫い付けられてきた支配の糸であり、ホロコースト、移民への集団的抑圧、まさしくガザで進行中の攻撃において歴史の表面に穴を空けるものである。ガザでイスラエル兵に拘禁されていた14歳のパレスチナ人モハメド・オデーは、以下のことを思い起こす。「連中は言い続ける。「おまえらはみなハマースだ」と。連中はわれわれの腕に数字を書き込んだ。わたしの数字は56だった」。オデーが腕を伸ばすと、皮膚の上に赤いマーカーがまだ見える」。Linah Alsaafin and Maram Humaid, “‘Like we were lesser humans’: Gaza boys, men recall Israeli arrest, torture,” Al Jazeera, December 12, 2023. Online here. ↩︎
- カトリーヌ・マラブーの指摘によれば、ランシエールにとって感性的=美的レジームとは、「権力を行使する資格(…)の分配(…)つまり、万人がみずからの分け前をもっている、もちうると信じさせる分配〔partage〕」を伴うものである(Stop Thief!: Anarchism and Philosophy, Malabou, 190〔カトリーヌ・マラブー(伊藤潤一郎+吉松覚+横田祐美子訳)『泥棒!――アナキズムと哲学』青土社、2024、332頁、〔partage〕は北川が追加した〕)。ランシエール自身は、感性的=美的な余分については、社会的なものの計算から生じるものと定義している。ランシエールの指摘によれば、ポリスの機能は「空白と余分との不在を特徴とする感性的なものの分割=共有にある」にもかかわらず、この計算は「あらゆる余分なものの排除」として生じる。つまり、政治が自らのものとして数える余分の排除として生じるのである(Rancière, Dissensus, 36)。この意味で、感性的=美的なものは、おのれを全体として宣言し、強要する。たとえこの全体が数えられないもの、分け前なき者の分け前という構成的余分――無感性的なものなら、自らのものとしてそれを数え上げてしまう余分――を伴って現出するのだとしても。 ↩︎
- 感性的=美的なものと無感性的なものの両方を貫く計算の論理は、反乱を起こした兵士を処刑する古代ローマの慣例にはっきりと現れていることがわかる。decimateという言葉はここに由来する。つまり、10人のうちの1人の殺害が、残りの9人に秩序を課す手段とされていたのだ。 ↩︎
- Yuval Abraham, “‘A mass assassination factory’: Inside Israel’s calculated bombing of Gaza,” +972 Magazine, November 30, 2023. Online here. ↩︎
- Abraham, “Mass assassination factory.” ↩︎
- 『ワシントン・ポスト』紙の調査報道記者エヴァン・ヒルは、いずれも同時期の衛星写真と地上で撮影されたビデオを用いて、このプロセスのあらましをツイッター上で述べていた(こちらを参照)。 ↩︎
- Julian Borger and Ruth Michaelson, “IDF instructions on Gaza refuge zones cruel ‘mirage’, say aid agencies.” The Guardian, December 7, 2023. Online here. ↩︎
- Nidal Al-Mughrabi and Abir Ahmar, “Surgeon flees Gaza City’s last functioning hospital after anaesthetics run out.” Reuters, November 17, 2023. Online here. ↩︎
- Achille Mbembe and Torbjørn Tumyr Nilsen, “Thoughts on the Planetary.” New Frame, September 5, 2019. Online here. ↩︎
- カトリーヌ・マラブーは、ランシエールをアナーキーの哲学者とはしているが、まさしくこの理由のために、アナキストとはしていない。マラブーはこう指摘する。「問題は、政治――根源的な意味での政治――とポリスが異質なものだと述べられてはいるものの、ランシエールがポリスの不可避性をそれでも擁護しているところにある。「政治はとりわけポリスと対立する」にもかかわらず、ポリスはラディカルな政治によって打倒されるべき悪しき対象ではないのである」(Catherine Malabou, Stop Thief! Anarchism and Philosophy, Polity, 2023, 182〔カトリーヌ・マラブー(伊藤潤一郎+吉松覚+横田祐美子訳)『泥棒!――アナキズムと哲学』青土社、2024、318頁〕参照)。ランシエール自身も同じことを主張している。「政治がポリスの論理とはまったく異質な論理を使うとしても、それはつねにポリスの論理に結びついている」〔ジャック・ランシエール(松葉祥一+大森秀臣+藤江成夫訳)『不和あるいは了解なき了解――政治の哲学は可能か』インスクリプト、2005年、63頁、北川が一部訳文を変更〕。 ↩︎
- アナーキーを脱構成する権力として理論化する作業、つまり「動物/人間、むきだしの生/権力、家/都市、そして構成する権力/構成された権力といったように〈生の形式〉を分割する主権権力の技術を脱活動化すること」として、「私たちをかくも多くの装置の主体として定義している切り詰められた実存から、なんであれ任意の形式を担うための生それ自体の最大の可能性を奪い返す権力あるいは能力」として理論化する作業から学ぶことはまだたくさんある(Hostis, “Destituent Power: An Incomplete Timeline.”〔元のサイトへはリンク切れだが、以下に日本語訳が所収。ホスティス(HAPAX訳)「脱構成的権力――未完の時系列」『HAPAX』II-1、以文社、2023年、74頁、北川が一部訳文を変更〕)。 ↩︎
訳注
- 差し引き(deduction)には、引き算という意味だけではなく、別のところに配置するという含意がある。たとえば、「口座から資金を差し引く」、「取引から一定の金額を取り除く」などの場合、そこにはここから取って、別のところに置くという意味がある。ここでは、パレスチナ人の生を分け前を分配する社会から引き算して、根絶の暴力が行使されるところに置く、除外するという意味である。
- 著者が授業を担当していたのは、アル・クッズ大学である。「アル・クッズ」とはアラビア語におけるエルサレムのことである。
翻訳にあたり、訳者の質問に快く回答してくれた著者のイアン・アラン・ポール氏に感謝する。
著者
イアン・アラン・ポール(Ian Alan Paul)
1984年生まれ。2016年にカリフォルニア大学サンタクルーズ校で博士号を取得(映画・デジタルメディア研究)。現在はバルセロナを拠点にアメリカ、メキシコ、スペイン、エジプト、パレスチナを横断しつつ、グローバル権力のレジームと抵抗の実践をめぐってアーティスト、理論家として活動している。論文に“Controlling the Crisis” in Moving Images, Transcript Verlag, 2020、“Civil Disobedience” in The Routledge Encyclopedia of Citizen Media, 2021などがある。
訳者
北川眞也(きたがわ しんや)
1979年生まれ。政治地理学、境界研究。博士(地理学)。三重大学人文学部准教授。著書『アンチ・ジオポリティクス――国家と資本に抗う移動の地理学』(青土社,2024年)。その他、共著として『惑星都市理論』(「惑星都市化、インフラストラクチャー、ロジスティクスをめぐる11の地理的断章——逸脱と抗争に横切られる「まだら状」の大地」、平田周+仙波希望編、以文社、2021)。主な論文に「地図学的理性を超える地球の潜勢力——地政学を根源的に問題化するために」(『現代思想』第45巻18号、青土社、2017)、「ロジスティクスによる空間の生産——インフラストラクチャー、労働、対抗ロジスティクス」(原口剛との共作、訳書にフランコ・ベラルディ(ビフォ)『NO FUTURE――イタリア・アウトノミア運動史』(廣瀬純との共訳、洛北出版、2010)。
![Read more about the article 【連載】誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[最終回]/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2023/07/佐々木_cartedesouvrages_画像.jpg)
![Read more about the article 誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[第1回]前編/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2021/12/PXL_20210530_093805138.jpg)

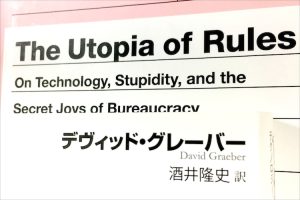

![Read more about the article 誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[序]/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2021/11/noparis2024.jpeg)