マルチスピーシーズ人類学の可能性
──生物と非生物の境界を超えて
奥野克巳 × 近藤祉秋 × 箭内匡
後編
種の絶滅という問いかけから、マルチスピーシーズ的希望のほうへ
マルチスピーシーズ人類学の射程
近藤:マルチスピーシーズの射程とは何か、ひいては多種とは何かということについて、奥野さん、箭内さんのお考えをお聞きしたいと思います。少なくとも私は、前回でも述べたように、人間と動物の関係からマルチスピーシーズ的な探究を始めたという経緯があります。そのため、どうしても動物を起点に考えてしまいがちです。
しかし、マルチスピーシーズ民族誌を読めば読むほど、確かに石が語られたり、植物が語られたりと、動物はもはや乗り越えられてしまっている。「乗り越え」というと変かもしれませんが、少なくとも人間や動物だけを語っていればよい世界というのは、もう終わりを告げつつある。人間だけにとらわれずに考えるために動物を持ち出してきたわけですが、ある意味では動物は人間に近しいということが明らかになってきた。奥野さん、箭内さんのお話を聞きながら、そのような思いが余計に深まってきた感じがします。
前回、奥野さんはデボラ・バード・ローズの「流れる水の技法」について言及されていました。河川の脈動であったり、砂漠における不安定な降雨――普段はあまり降らないけれども、降る時には一挙にたくさん降る――という洪水パルスと呼ばれる現象であったり、降雨によって水が動くのにあわせて――もちろん土も動いているわけですが――さまざまな植物が咲き誇り、鳥が飛来して、それは「湿地帯が動いていくようだ」というような表現も「流れる水の技法」の中にはありました。
その脈動の中に人間もいると思うのです。非常に不安定な降雨のパターンの中で、突然一気に咲き誇る不思議な恵みのオアシスの中に、人間もいる。乾燥した砂漠に雨が降り、水源ができると、砂漠に住むアボリジニの人々は一斉に旅を始めるとローズは説明しています。人々が集まるところで儀礼が行われ、その際に新しい命を授かる女性もいる。つまり、人々の遊動の仕方であったり、ドリーミングと呼ばれる神話的な世界であったり、儀礼であったり、人間の営為もまた流れる水の脈動の中で生まれているということです。
ただ単に動物だけ、あるいは人間と動物の関係、人間と植物の関係、人間と精霊の関係だけを個別に見ているだけでは絶対にわからないものがあります。降雨のパターンや砂漠の生態系、水文学、地質学も踏まえて、その中で人間を含むさまざまな複数種を考えていくというのは、非常に興味深いと思います。それはもちろん、箭内さんの植物人類学においても、動物をモデルにして考えていた人類学を批判し、植物をベースに考えたらどうなるか、これを問い直すという、スリリングな試みが伺えます。
「石」という非生物から「生命」を問い直す
近藤:前回、奥野さんと箭内さんのご発言から出てきたものとしては、「石」に代表されるような地質学的存在というものがありますね。この「石」という存在(ひいては地質学的存在)を、マルチスピーシーズ研究において、どのように扱いうるか、この問いを考えていかなければならないと思います。さらに言えば、それは果たして「多種」という捉え方のままでよいのか、という問題にもつながります。
一般的に考えると、「種」というのは、どうしても「生物種」というイメージがありますね。まさにマルチスピーシーズを主題とした雑誌を「たぐい」と命名した背景には、「種」(スピーシーズ)だと、「生物種」のイメージとなってしまうため――もちろん、私は生物学の専門家ではないので、実際のところはわかりませんが――どうしても種として分類した時点で、最初から決まってしまっているのではないか、という懸念がありました。より広い使い方ができるように、また、関係性の中で築かれるものを考えるために、「たぐい」という言葉を使えないか、特にエドゥアルド・コーンのkinds(たぐい)の使い方から着想を得て、考えたものでした。つまり、マルチスピーシーズと言った時に、常に問題になるのは、「スピーシーズ(種)とは何か」ということです。インゴルドは、マルチスピーシーズ民族誌が「種」という西洋由来の考え方に縛られているのではないかと批判しています。その点で種をめぐる問いは、インゴルドによるマルチスピーシーズ批判とも繋がってくるのだと思います。
もうひとつ、「石」という存在から考えると、「非生命」的存在、生命でないものをどのように扱うか。その時、「種」というものはいったいどう考えればよいのか。ぜひ、おふたりに伺ってみたいです。
箭内:まず石から始めますと、これはもちろん生物/非生物の区分の問題と関わっています。ところで、ミシェル・フーコーが『言葉と物』などで細かく論じたように、そもそもヨーロッパの科学の中でも生物学が登場するのは、18世紀末から19世紀にかけてのことです。それ以前、つまり18世紀以前には博物学という分野があったわけですが、そこでは実は生きているか死んでいるか、生物か非生物かというのは問題にされていませんでした。生物種の分類の原点にあるリンネはその時代の人間だったので、リンネの分類学では動物と植物と鉱物という3つが様々な種に分けられています。
それを生物学が引き継ぎ、ダーウィンらが登場してきて、今日のような生物種を意味するようになったわけですが、もともと種という言葉は、近代の生命観の外で考えるなら、必ずしも生物種に限定される必要はない、というのは考えるに値する点です。フーコーの『言葉と物』はやはりこの点で大いに参考になります。
もう一つ、こうした思想史的な話とは別に、もう生物種自体について考えてみると、一方で絡まり合いや関係性から「種」を見てみると、「種」という形で固定的に捉えても意味がないのではないかといった方向に向かいがちですが、もう一方で生物学的にみると、やはり「種」がというものの重みも否定できません。実際に「ある生物の形が存続していく」という事実があるわけです。猿は猿ですし、犬は犬ですし、ずっと続いていて、その中にさまざまなバリエーションが出てきますが、そこには「種」として「存続する力」というものがある。
レヴィ=ストロースが『野生の思考』の中で、とても面白いことを言っていたことを思い出すのですが、彼は、植物の種が絶滅してしまうことの悲しみ、これはある芸術家が死んだ時の悲しみと同じだというような独特な表現をしています。そういう固有の存在というのが種であるということは確かだと思います。
この点も踏まえつつ、最後にマルチスピーシーズという言葉自体について考えてみると、この言葉は、「種」(species)と「多」(multi-)が結びついた言葉ですよね。最初から、種がいくつもあるものとして考えられている、ということが大事だと思います。つまり、他から区別されるものとしての種があり、それが複数あって、相互に結びついているというイメージとして、マルチスピーシーズという言葉があることは非常に大事だと思います。

マルチスピーシーズ的な世界を拡張する
奥野:ダナ・ハラウェイによれば、speciesという言葉は、味覚よりは視覚に関わっていて、ラテン語のspecereには「見る」「凝視する」といったニュアンスがあるということのようです。それは、語源的には、「見る」ことに関わっています。speciesは、もともとは、見て、区別し、種類分けをすることだったんですね。私たちが、見て、まとめあげたものを対象として取り出すことに関わる言葉なんですね。そのspeciesを、生物種として限定的に私たちは考えてしまっている。
箭内さんがおっしゃるように、マルチスピーシーズ民族誌/人類学がもっぱら有機体を扱うイメージで捉えられているというのは、その通りだと思います。他方で、存続する生物種というのがあって、それが単数ではなく複数あり、それらが相互に結びつき合っているイメージを喚起するものとしてのマルチスピーシーズという言葉は、確かに大事ですね。
しかし、マルチスピーシーズ民族誌/人類学は対象を生物種だけに限定しなくてもいいのかもしれません。自然をめぐる文化・社会人類学の第一波を引き継いでいる以上、第一波の「存在論的」人類学で扱われていた、気象や風やら山や川などにエージェンシーを認めることを除外して考えることはできないようにも思えます。自然をめぐる文化・社会人類学は、第二波になると、生物学的な人類学と共存するようになり、生物種だけに限定して語り始めたのでしょうか。ハラウェイの影響だったのかもしれません。
ローラ・オグデンらによる、わりと初期の、よく知られたマルチスピーシーズ民族誌の概説論文では、そもそも、動植物と人間だけでなく、事物が取り上げられています(Ogden, L., B.Hall & K.Tanita 2013 “Animals, Plants, People, and Things: A Review of Multispecies Ethnography”, Environment and Society: Advances in Research40(1): 5-24)。また、第一波と第二波を分けて考えるのではなく、それらを一括して、自然をめぐる社会・文化人類学としてみるという点でも、事物を含めてもいいように思えます。
人類学に限らずですが、ある研究ジャンルをやり始めると、その中に閉じていってしまう傾向がありますね。Multispeciesだからspeciesに限られているんだというところから出発して。それを開いていくには、環境人文学のような、より大きな学際的な枠組みにつながっていくことが重要なのではないでしょうか。そのことに気付かされたことがあります。
『図書新聞』の企画で、近藤祉秋さんと結城正美さん、私の3人で鼎談をしたのですが(『図書新聞』3530、2022年02月05日号)、そこでも、「種とは何か」をめぐって同様の問いかけが出されました。石やAIをマルチスピーシーズ人類学ではどう考えるのかという問いです。
そこで、結城さんが取り上げたのは、アメリカ先住民オジブワの血を引く物語作家のルイーズ・アードリックの作品「The Stone」です。結城さんは、岩石は名詞ではなく、動詞であるというのが地質学の基本だというところから話し始めていますが、アードリックは、動詞的あるいはエージェントである石と性的な関係を結ぶ人の話を書いています。
その話を聞いて私が思い出したのは、日本でも奥泉光さんの『石の来歴』という小説です。太平洋戦争中にレイテ島に送られ、時空を超えた「悠久の時間」を経てきた石に魅せられた主人公は、戦後、日本国内で石に夢中になるあまり、子どもを死なせ、妻を狂気に追いやることになったのです。石と人をめぐる物語です。
石と人間との関係は、想像力や直観によって書かれた文学作品の中で豊かに表現されていて、大きな示唆を与えられます。環境人文学では、種とそうでないものに線を引いていない以上、マルチスピーシーズ人類学を、種を含めて、諸存在の絡まり合うさまを扱うジャンルと捉えれば、何も生物種だけに限定してしまわなくてもいいのかもしれません。自然をめぐる社会・文化人類学の第一波と第二波を連続するものと捉えて、「人間以上」が相互に結び付き合っているさまを考えていっても、何ら問題はないとも言えます。マルチスピーシーズ人類学から見れば、マルチスピーシーズ概念の拡張ということになるのかもしれませんが。
マルチスピーシーズの拡張という点で、もうひとつ別の話をしようと思います。マルチスピーシーズというのは、マルチスピーシーズ民族誌/人類学を指すだけではありません。
そのことは、『週刊読書人』誌上で実施した、近藤祉秋さんと川地真史さんとの鼎談(『週刊読書人』3421、2021年12月31日号)を通じて理解したことなのですが、マルチスピーシーズというのは、アカデミーの中でのマルチスピーシーズ民族誌/人類学だけでなく、人類学では、エベン・カークセイらが取り組んだような「アートやパフォーマンスとの連携」という流れがある。そして、もうひとつの大きな広がりとしては、この『思想』の「マルチスピーシーズ人類学」特集にも寄稿されている川地真史さんらが取り組んでいる「社会実装」という側面があるんです(http://www.ibunsha.co.jp/contents/multispecies01/)。
私たち人類学者は、マルチスピーシーズ人類学という研究ジャンルの流れの中で、綿密な現地調査を通じて民族誌を書くということを基本的な仕事としています。他方で、当の「マルチスピーシーズ」という概念によって、私たちが考えてみなければならないのは、人間中心主義がどのようにしたら乗り越えられるのかということであり、その理念をどのように表現したり、より具体的に考えたりすることができるのか、また多種の共存の実現がどのようにしたら未来においいて可能になるのか、といったことでもあるのです。
「人間が人間のために作り出す世界」ではなく、「マルチスピーシーズ的に作られた世界」をどのように築いていくのかを、より具体的にかつ現実的に考え、実践していこうとしている人たちがいる。マルチスピーシーズの「社会実装」とはそういうものです。
「マルチスピーシーズ民族誌/人類学」、それと「アートやパフォーマンスとの連携」、マルチスピーシーズの「社会実装」という広がりの中で現在、マルチスピーシーズ研究=実践が行われてきているんです。
マルチスピーシーズ人類学はいかに「絶滅」に向き合うのか
近藤:先ほど、箭内さんは、種が絶滅することは一人の芸術家が亡くなることと同じだというレヴィ=ストロースの言葉を引かれていました。この言葉を聞いて、トム・ヴァン・ドゥーレンというオーストラリアの環境人文学、環境哲学の研究者が書いた絶滅論を想起しました。ヴァン・ドゥーレンは、ほぼ絶滅しかけている5種の鳥たちが、今現在、いかに地球で生きていこうとしているかを議論する『絶滅へむかう鳥たち』という本を書いています。この本の原著タイトルは、Flight Ways、つまり「飛び方」です。今回の鼎談で出てきた大地や植物のような、生命の基盤となる場所の中で織り上げられてきた「飛び方」 が、それぞれの鳥たちが直面する危機的な状況の中でゆっくりとほどけていき、絶滅へ向かっていくという話が展開されています。そのような観点からすると、ヴァン・ドゥーレンが述べている「飛び方(Flight Ways)」というのも、レヴィ=ストロースがいうような芸術家の生、つまり芸術家による作品制作のようなものであると言えるのかもしれない。鳥たちが生きていた姿というのは、うまく存続する力の延長にあって、一種の芸術作品のように続いてきたにもかかわらず、人間のさまざまな活動によって、ほどけていってしまう。そのような問題意識が同書にもあったのかもしれないと考えました。
それこそ芸術作品のように続いてきたものが、人新世によって今、ほどけつつあることをどう考えるのかというのは、マルチスピーシーズ民族誌でも議論されていることです。また、トム・ヴァン・ドゥーレンも環境哲学をベースにした研究者でもあり、非常に環境人文学的な問題でもあります。
そして、奥野さんから紹介いただいたデボラ・バード・ローズも、やはり絶滅の問題を議論していると思います。
そもそも人新世とは、人類史と地球史、地質学的な時間とが重なるところだという議論がありますが、人新世や環境問題について、また絶滅というテーマにおいて、マルチスピーシーズ人類学、ひいては環境人文学はどのように扱っているのか、どうお考えになりますか。
奥野:マルチスピーシーズからの切り口ではないのですが、最近読んだ本で「絶滅」に関する興味深い研究がありました。最近、ラトゥールの「テレストリアル」概念の広がりについて調べている間に見つけたエコクリティシズム/環境文学の論文があります。アン・マッコネルの「テッド・チャンの「大いなる沈黙」の中に地上存在の声を聴く」という論文です(Anne MaConnell “Listening to Terrestrial Voices in Ted Chiang’s “The Great Silence””, Literature 202, 2(2): 77-89)。
テッド・チャンというSF作家は『息吹』という作品集を出していますが(テッド・チャン『息吹』、2019年、早川書房)、その中に「大いなる沈黙」という作品が収録されていて、プエルトリコの展望台の話が出てきます。展望台では、地球外生命体に信号を送って、反応があるかどうかを調べています。地球外生命体を探しているのです。
他方で、その展望台があるプエルトリコでは、あるオウムが絶滅に瀕しています。もうほとんど残っていないようです。森が開発された結果、住む場所がなくなって絶滅しかけている。オウムは、話すことができる動物で、頭がよく、人間と会話ができるとチャンは書いています。
人間は地上から離れて、地球外生命体を必死になって探しているけれども、実は、人間の近くに絶滅しかけているオウムが、人間に語りかけているのです。耳を澄ませばわかるはずなのに、人間はそうしない。オウムが絶滅してしまったら、両者はもうコミュニケーションを取ることはできないと言うのです。
「大いなる沈黙」と題する短編で描かれているのは、展望台で地球外生命体を探すのに必死になるあまり、身近にいて、喋りかけているオウムには耳を傾けようとしない人間の姿だとマッコネルは指摘しています。先述したように、ラトゥールは、地球に再び降り立って、大地で営まれているテレストリアルの活動に目を向けてみるべきだと述べています。その論点を踏まえてマッコネルは、「絶滅」をテーマとしてチャンの作品を読み解いたのです。
箭内:地質学、まさに地球史というものを考えると、絶滅というものは、頻繁に起こっていることでもあります。大量絶滅というのは何度も起きており、それこそ、巨大火山の噴火とも関連していたりするのですが、インドネシアのトバ火山の大噴火が7万年くらい前にあったと推定されていますが、大規模な噴火だったと考えられ、この噴火と同じ頃に人類の人口が非常に減ってしまっていたことが遺伝学的観点も含めて議論されています。それは数百人にまで減ってしまったとも言われています。そこから現在の人類は、もう一度、増えてきたと考えられているのです。そういう意味では、これまでも激しい変化というものがあったわけです。
だからどうでもいいということでは全くないのですが、地質学的年代自体は非常に深い年代があることを前提にすると、「人新世」というものは非常に浅い年代に過ぎないわけです。そのような角度から考えると、種の絶滅だけではなくて、新しい種が誕生し、広がっていくことについても考える必要があるのではないかとも思います。人間は絶滅して終わりかもしれませんが、他の種が出てくる可能性もある。その両方を考えなくてはならない。
石の話に戻りますが、ロバート・ヘイゼンというアメリカの鉱物学者がいますが、日本でもブルーバックスのシリーズに翻訳が収録されています(『地球進化 46億年の物語』講談社)。彼は、「鉱物進化(mineral evolution)」という概念を提唱しています。地球上の鉱物が、他の惑星に比べても非常に種類が豊富なのはなぜかというと、最も大きな理由は生命が生まれたからだとされます。特に光合成する微生物が誕生すると、酸素ができ、岩石などの鉱物が酸化してしまう。それによって、さまざまな新しい鉱物が次々に出てくることで、自然選択ではないけれども、進化してきて鉱物ができていく。生命と地球の相互作用の中で進化が起きてくる。これを鉱物進化と呼ぶわけです。そのように見てくると、「鉱物種」というものも、リンネは単にそれを分類していただけなのですが、よりダイナミックなものとして考えることができる。
存続していくものとしての種と、天変地異か何かで絶滅していく種の両者から考えていくことが、やはり重要だろうと思います。
インフラストラクチャーとしてのマルチスピーシーズ
近藤:今回の鼎談では、マルチスピーシーズ人類学の根幹が大きく揺り動かされていると感じています。繰り返しになりますが、私自身は動物への関心から研究に入っていったため、多種というとどうしても動物がたくさんいるというイメージを持ってしまう。民俗生物学の研究が盛んな内陸アラスカで調査していることもあり、どうしても動物がたくさんいる中に先住民がいるようなイメージで語ってしまうところがあります。
生命と地球の相互作用の中で、鉱物進化が起きていくというお話がありました。そのような進化の果てに生まれた地下資源を使うのが現代の人間の文明や社会であるわけです。このことを絡まり合いと呼んでよいのかわかりませんが、少なくとも動物・植物・鉱物が含まれた「種」がたくさん存在する中で相互作用が起きており、それがさまざまな「種」に結実し一定の間は続いたかと思ったら、ある時突然に途切れてしまったり、溶け出してしまったりすることもある。今日の鼎談でのお話をもとに考えていくと、地球上および地球内部で繁栄し死滅し蓄積し溶解していく「種」の生命/生活をこのように非常にダイナミックなイメージで捉えることができることに気づき、興奮を覚えました。絡まり合いを考える際に、ついつい人間と動物の絡まり合いという狭い範囲で想像しがちなところを、そうではなくて、土地であったり、ひいてはもっと下にあるもの――鉱物というようなものについても考えていく必要がある。
これは、通常の文化人類学的な調査では見ないところですね。どうしても人類学者の目線というのは、そこにいる人間たちをちゃんと見ようと思って、人間がいる地面の上の世界を見ることに終始しています。それに対して、この大地の下にものすごい世界が眠っている。火山があり、岩や鉱物がある。これらも十分に考慮に入れなくてはいけないと思いました。
鉱物自体は一般的な意味では人間が作ったものだとは考えられないわけですが、今日の議論の中では人間を含む生命の歴史と地球の歴史とが交差するところに鉱物進化を位置付けるという試みがなされました。その考え方に基づけば、諸々の石や鉱物、土壌を含む大地は、人間を含む多種がつくりだし、多種の繁栄を支える「インフラストラクチャー」だとさえ言えるかもしれません。今回の特集に収録された奥野さんの論考(「人間以上にリメイクされる自然――『マツタケ』以後のアナ・チン、フェラルなものの人類学」)や内藤直樹さんの論考(「埒外の生態学にむけて――寄生と依存が生み出す社会」)では、人間の制作したものであるインフラストラクチャーが、多種によって領有されて、野生化し、フェラルなものになっていくことが議論されていました。この興味深い分析に、地質学的な時間を生きる鉱物や大地の流動的な存在様式という新しい要素を加えて分析していくと、どのような結果が出てくるのか、ということも気になります。
マルチスピーシーズ民族誌に関する有名なレビュー論文では、動植物、菌類、ウイルスなどを念頭に置きながら、「生命の創発」に焦点化してマルチスピーシーズ研究を説明していました。しかし、鉱物のことをより本格的に研究に取り入れていくならば、そもそも「生命」自体をより根本的に考え直さなければならないように思います。このことに取り組み始めた時、『思想』の特集で企図したように、隣接分野からの知恵を借りながらマルチスピーシーズ人類学を発展させる、もしくは発展的に乗り越えていくような視界が開けるのではないか、というのが今日私が学んだことでした。
マルチスピーシーズ的希望に向かって
奥野:「絶滅」に関しては、これからの時代を生きていく若い人たちのほうがやはり敏感なのではないかなと思います。マルチスピーシーズに関して、それが何をもたらしてくれるのかという点では、「社会実装」の面が今後のマルチスピーシーズ研究=実践の重要な柱になるだろうと思います。
先ほど、マルチスピーシーズを3つのカテゴリーに振り分けてお話ししました。繰り返しですが、アカデミックな研究である「マルチスピーシーズ民族誌/人類学」、「アートやパフォーマンス」と連携した形で行われるようなマルチスピーシーズ、そして最後にマルチスピーシーズの「社会実装」としての実践です。
2番目と3番目の境界は実は曖昧ですが、今回の『思想』の「マルチスピーシーズ人類学」特集の最後に掲載されている川地真史さんの論考「マルチスピーシーズとの協働デザインとケア」でも述べられているように、この3つの境界がより曖昧なものになっていくことが理想的なかたちなのでしょう。
マルチスピーシーズには、未来に向けて、希望が語られるようになってきている点に最後に触れておきたいと思います。具体的には、ソニーグループのクリエイティブセンターがまとめた「DESIGN VISION」で、「2050年に向けてどんな社会変化が起こるのか」を分析して、「HOMO DIVIDUAL(ホモ・ディヴィデュアル)」「CONVIVIAL AI(コンヴィヴィアルAI)」「WELLBEING-WITH(ウェルビーイング・ウィズ)」「MULTISPECIES(マルチスピーシーズ)」という4つの柱を立てています(https://wired.jp/branded/special/2022/design-vision-on-going-6/)。4つめの柱として、マルチスピーシーズ的な社会を作り上げることを2050年の目標しているわけです。これは、マルチスピーシーズの社会運動的な側面とでも言うべきものです。
私たちがこれまで、人間を中心に位置づけて、人間本位に世界を築いてきた結果、今日、気候危機や海洋汚染をはじめ、さまざまな問題が山積しています。問題を乗り越えるために、ラトゥール的に述べれば、依存的・分散的で、発生システム的なマルチスピーシーズ的社会を自ら生み出していこうとする気運が、若い世代を中心に出てきているように思えます。デザイン人類学という新しいジャンルとも連動しながら。
そういう発想自体が、そもそも人間中心主義的だということは簡単ですが、その批判もまた乗り越えていかなければならないので、なかなか先行きは大変なのかもしれませんが。
例えば、前述のソニーのクリエイティブセンターではリサーチを進めながら、マルチスピーシーズの「社会実装」にはどういうことが必要なのかを見極めるために、ラボラトリーで、さまざまな実験を行っているようです。アートやパフォーマンスの実践にも関わる過程で、何らかの気づきが必要であり、その気づきを実際に実践したり実験したりしながら得ていこうという流れがあるようです。
こういうのがマルチスピーシーズの「社会実装」ですが、次のような試みもまたあります。かつて1980年代に、インターネットが形成するサイバー空間によって管理された、退廃的な未来社会を描くSF小説は、「サイバーパンク」と呼ばれました。近年、それを真似て、「ソーラーパンク」という言葉が作られました。それは、太陽光などを用いて、マルチスピーシーズ的に調和のとれた未来社会を描くフィクションのジャンルのことです。
Multispecies Cities: Solarpunk Urban Futuresというアンソロジーが刊行されました(2021、World Weaver Press)。その中に、SF作家である藤井太洋さんが作品を寄せています。人が火星に移住する未来の話です。火星には気温が低すぎて、人間が住むことができないのですが、反対に地球は二酸化炭素を放出し、地球温暖化がどんどん進んでいます。地球の二酸化炭素を火星に移動させて温暖化して住むことができることが、その物語のモチーフになっています。
こうした文学作品においても、マルチスピーシーズ的な社会の未来に向けて、スペキュレイティヴ(思弁的)な試みが行われているとみることができるでしょう。「社会実装」するための手がかりが描かれているとも言えるのです。こうしたことが、マルチスピーシーズ民族誌/人類学以外に、マルチスピーシーズの文脈で行われてきています。
それらに影響を受けながら、今後、マルチスピーシーズ民族誌/人類学自体がどう変容していくのかという点もまた、興味深いポイントです。ラトゥールは、よく知られているように、展覧会実践やワークショップを重んじていましたし(https://zkm.de/en/zkm.de/en/ausstellung/2020/05/critical-zones/bruno-latour-on-critical-zones)、マルチスピーシーズ民族誌/人類学をこれまで牽引してきたアナ・チンも2020年代に入ってから、研究だけでなく、アートとパフォーマンスと連携し、社会実践までをも模索する「フェラル・アトラス」というインターネットを足場とするデジタル・プロジェクトを立ち上げています(https://feralatlas.org/)。
箭内:地球温暖化などの問題によって、世の中の人たちの意識が変わっており、やはりその中でこそ、2010年前後というかなり最近出てきたマルチスピーシーズ人類学というものが、これだけ一気に広く注目を浴びてきたのだと思います。
奥野さんがおっしゃった社会的な広がりということも非常に大事なことだと思いますし、他方でもっと自由に、パースペクティヴの広がりを持って考えることも重要だろうと思います。一方向的にだけ物事を考えがちな私たちの世界の中で、地球温暖化という問題は非常に差し迫ったものとして突きつけられている。その中で、さまざまなことを全く新たに考えていかなければならない。
そこでさまざま可能性を考えること、物事を感じるその仕方をもっと多様にしていくというようなことが重要となるでしょう。動物にせよ、植物にせよ、鉱物にせよ、さまざまなものとの付き合い方があり、多様性というか、さまざまな可能性の広がり、感じ方の広がりがある。そこを考えていくのに、マルチスピーシーズ人類学というのは大変、大事だと思うのです。それは、ある種のチャンスでもあります。一方向にしか考えられなかったものを新たに見直していく、その中でマルチスピーシーズ人類学というものが、それ自体でも多様化しつつ、非常に重要な役割を果たしうるのではないでしょうか。
(了)
プロフィール
奥野克巳(おくの・かつみ)
文化人類学。以文社より共著、共編著として『今日のアニミズム』(2021年)、『マンガ版マルチスピーシーズ人類学』(2021年)、 『モア・ザン・ヒューマン』(2021年)、 『Lexicon 現代人類学』(2018年)を刊行している。
近藤祉秋(こんどう・しあき)
文化人類学。以文社より共著、共編著として、『マンガ版マルチスピーシーズ人類学』(2021年)、 『モア・ザン・ヒューマン』(2021年)、 『Lexicon 現代人類学』(2018年)を刊行している。
箭内 匡(やない・ただし)
文化人類学。著書として『イメージの人類学』(2018年、せりか書房)、共編著として『アフェクトゥス』(2020年、京都大学学術出版会)などを刊行している。


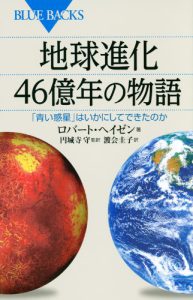
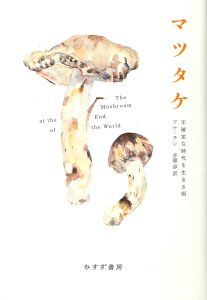
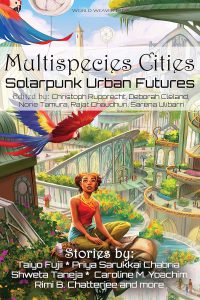


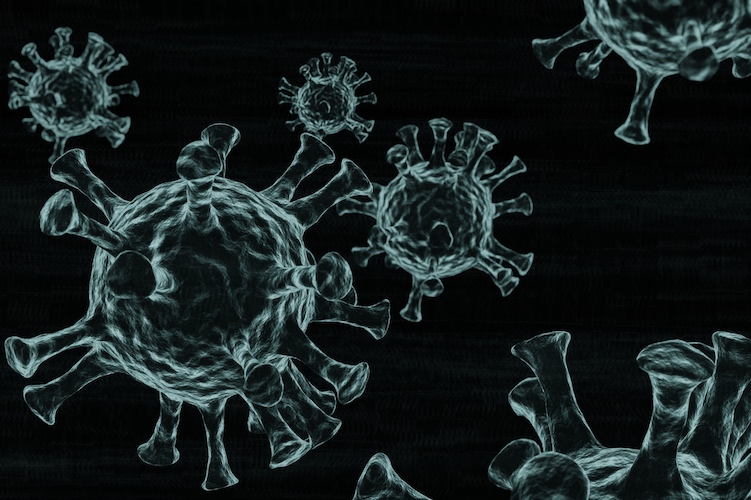
![Read more about the article 誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[番外編]/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2019/09/editorial01_photo_2.jpg)

