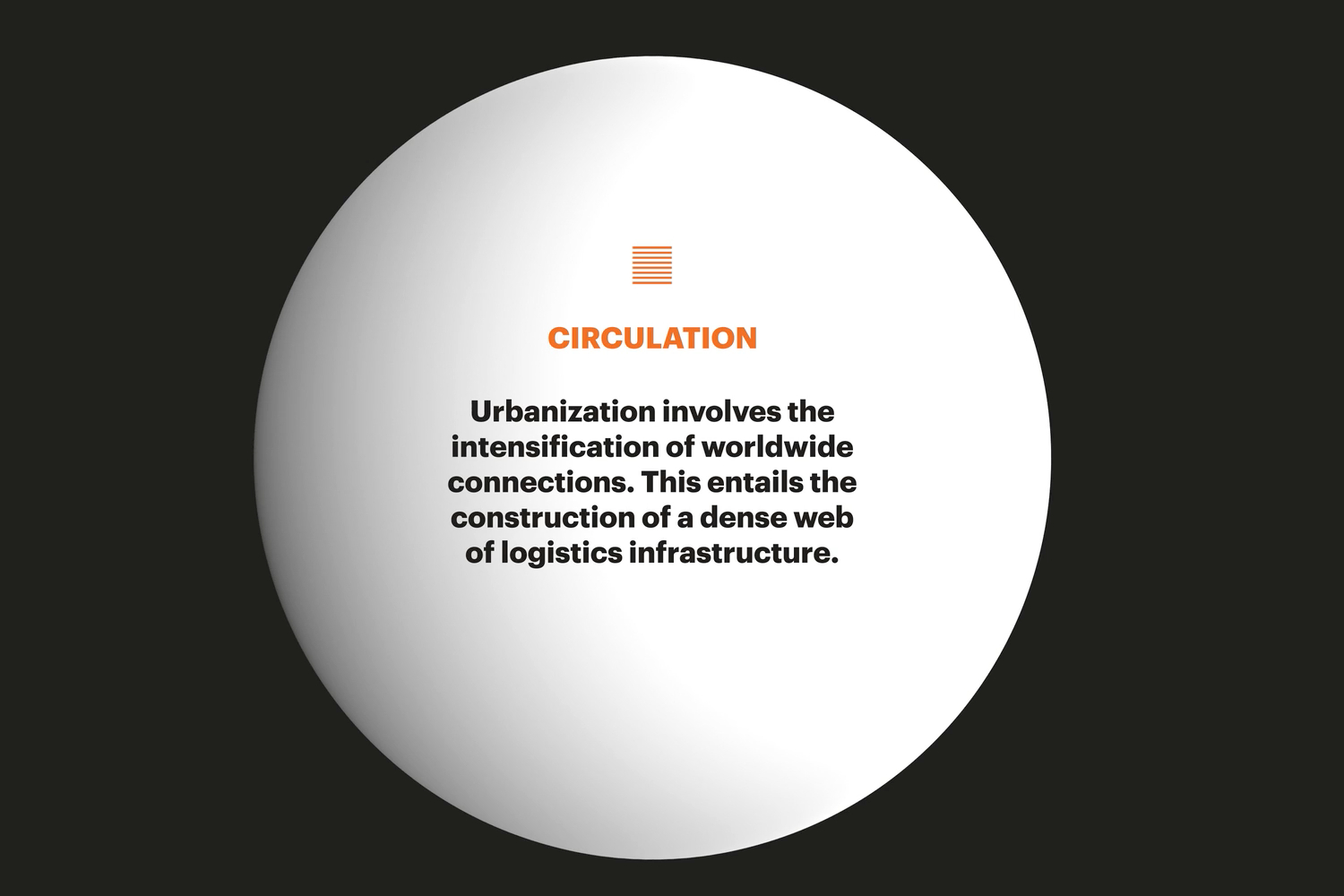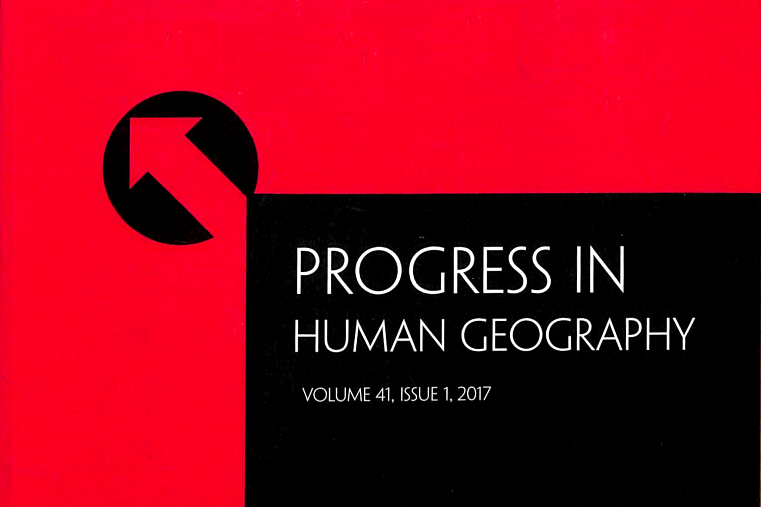人間狩り・奴隷制・国家なき社会
──シャマユー、ミシェル、そしてクラストル
酒井隆史 × 中村隆之 × 平田周
第2回
「オレリア・ミシェル/奴隷制とレイシズム」
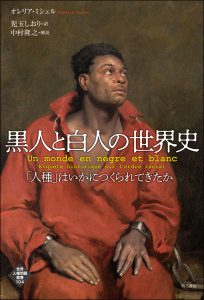
中村 それでは、次にオレリア・ミシェルの『黒人と白人の世界史』(児玉しおり訳、明石書店、2021年)へ移りたいと思います。
オレリア・ミシェルは1975年生まれ、シャマユーは1976年生まれなので、二人はほぼ同世代になるわけですが、シャマユーの場合はすでに訳書も数冊出ていますが、ミシェルの場合は訳書のみならず、原著としてもこの本が初めての単著、ということになります。原著は2020年の2月頃に出ていますが、広く読者に届けたいという意図から、フランスでは最初から文庫本のかたちで出版されました。
原著が出版されたあと、フランスの有名なル・モンド紙などでも取り上げられ、多くの読者を獲得します。翻訳をされた児玉しおりさんはフランス在住の方で、実際に読んで大変に面白いということで、原著が出版されてからわずか1年足らずで日本語にしてくださいました(私は「解説」の方で少しお手伝いさせていただいています)。ル・モンド紙は「まるで小説のように読める」と本書を評したわけですが、実際にそのような本ですね。
この本の出発点がどこにあるかというと、レイシズムの問題です。さきほど平田さんから、『黒人と白人の世界史』がユネスコの宣言から始まるという話をしてくださいましたが、このユネスコの宣言は、第二次世界大戦、とりわけホロコースト・反ユダヤ主義に対する反省からレイシズムの科学的根拠をはく奪しようとするものでした。こうした宣言があったにもかかわらず、実社会にはずっと人種主義的な言説が残っている。レヴィ=ストロースの『人種と歴史』(『人種と歴史/人種と文化』渡辺公三ほか訳、みすず書房、2019年)は、ユネスコの宣言の流れのなかから出た非常に有名な本です。近年のブラック・ライブズ・マター運動でも、いわゆる白人は、自身の「白人性」にこれまで無自覚だったという論点が出てきたことは記憶に新しいところです。
われわれがヨーロッパや欧米に行くときには、明らかに自分の人種のこと(人種という言葉をあえて使うとすれば)を意識せざるを得ないわけですが、「白人性」というとき、それ自体が問いに付されることは長らくなかったのですね。
『黒人と白人の世界史』の画期的なところは、自分は白人の歴史家、さらに女性の歴史家であると自分の属性を分節化した視点から書いているところです。そうしたときに、人種の問題、特に現在でも差別用語として「ニグロ」という言葉があります。フランス語だと「ネーグル」という発音になりますが、いまそんな言葉を公衆の面前で話したらとんでもないことになるでしょう。そんなことも本書のなかに書かれています。
では、そもそもどうして「黒人」と「白人」というような関係性が生じてきたのか。そのことを歴史家として辿っていくのがこの本の趣旨になります。いくつかキーワードが出てきますが、そのなかで「ニグロの虚構」という言葉があります。「ニグロは非人間なのだ」「ニグロは奴隷なのだ」といった虚構が、ある時期からつくられてきたわけです。それはいつからかというと、大西洋奴隷貿易以降です。これは先ほど酒井さんが紹介してくださったC・L・R・ジェームズの『ブラック・ジャコバン』にもつながる話ですね。
『黒人と白人の世界史』の特徴的なところを理論的骨子としてまとめてみると、以下のように言えるかと思います。
論理的骨子
・奴隷制の人類学的アプローチ(C・メイヤスー『奴隷制の人類学』に依拠)により、大西洋の奴隷貿易・奴隷制の特殊性を提示。
・この奴隷貿易・奴隷制の時代を通じて「ニグロの虚構」と「白人の虚構」が形成される。
・奴隷制廃止後の他者支配の論拠として「人種」と「人種主義」が科学的に持ち出される。
・第二次世界大戦とホロコーストの教訓からユネスコによる「人種」概念の科学的失効宣言(レヴィ=ストロース『人種と歴史』)
・問題の根底としての親族/奴隷制理論(白人男性原理)
まずは「奴隷制の人類学的アプローチ」についてです。クロード・メイヤスーというフランスの経済人類学者がいます。日本でも『家族制共同体の理論』(絶版、川田順造、原口武彦訳、1977年、筑摩書房)というタイトルで彼の著作は翻訳されています。その『家族制共同体の理論』のあとに書いたのが、『奴隷制の人類学(Anthropologie de l’esclavage)』という本になりますが、ミシェルは、この『奴隷制の人類学』に依拠し人類学的に見た奴隷制の特徴を3つに分けて述べています。
「脱人間化」、「脱市民化」、「脱性化」(訳書では「非性化」)です。この3つの特徴は、メイヤスーが抽出したものですが、奴隷制は、例えばアラブ文化圏にもあったし、日本にも当然あった。ではなぜ「ニグロ=奴隷」という見方が定着していったのか。それは、奴隷貿易そして奴隷制の時代を通じてつくられていく。ですから、最初からヨーロッパ人が差別主義者だったわけではなく、この歴史的プロセスを通じて差別主義者になっていったのだ、ということが大きな骨子になっています。
そしてこの本の中で強調されているのが「奴隷制からレイシズム」へという、いわばパラダイムシフトです。奴隷貿易、奴隷制の時代は白人とニグロという主人/奴隷の関係だったのですが、これが奴隷制の廃止で崩れていきます。そして、それが崩れたときに、他者を支配するための新たな論拠としてせりあがってきたのがレイシズムというわけです。ですから、レイシズムは、奴隷制の廃止以後に他者支配の常套句として、白人が頂点におりその下にはさまざまな人種が置かれてグラデーションを形成するわけですが、そのなかで最下層に置かれるのが黒人なのです。このヒエラルキーを正当化するために「科学的な」人種主義言説が持ち出されていく。
こうした流れがあり、先ほども確認したようにレイシズムはずっと残り続けるわけですが、ではレイシズムが残り続けているときに、いま一度メイヤスーの奴隷制理論に戻って考えると、もっともポイントになるのが白人の男性原理なのだ、と彼女は指摘するのですね。
国民であるという観点が、血統によってつくられていき、その血統は家父長的であり、基本的に男子を優先していく系譜の家族モデルがある、と。その家族モデルが、ヨーロッパの根底にもあるのだといいます。だから同胞として他者をなかなか受け入れられない。特にフランスはたいへん大規模な移民社会なのですが、その反動として、周期的に排外主義的な風潮に流れがちです。そろそろ大統領選ということで、エリック・ゼムールという危険な人が注目されていますが(笑)【編集部注・フランス大統領選はマクロンとルペンの決選投票となり(結果マクロンの勝利)、ゼムールは第1回目投票の結果7.1%の支持にとどまった】、『黒人と白人の世界史』はそうした排外主義を考える上でも実に示唆的です。
最後に読みどころとして、この本はここまで述べたような理論面も面白いのですが、何よりもたくさんの歴史資料が扱われており、資料集としても貴重です。これらの資料は、フランス語で書かれているものが多く、日本語からではアクセスするのが難しいような、フランス領の奴隷制社会の奴隷主の発言や、どこかの植民地の長官の発言、そうしたものが豊富に読める。
また、先ほどから暴力の話が話題になっていますが、やはり奴隷制社会における暴力は、これがまた異常なのですね。暴力がエスカレートしていくことももちろんあります。女主人が女奴隷に対して拷問をしていくとか。一方で、暴力が自分自身に跳ね返ってくるというわけではなく、抵抗のために奴隷自身が自分を傷つけるのですね。自分を傷つけるというのは手や足を切断したりだとか、身体を棄損していくレベルから最終的には自殺です。これが抵抗の手段になっていたということが、あったりします。
いまのわれわれの身近な社会からだと想像力が及ばないところかもしれませんが、奴隷制社会では非常に極端な暴力が常態化している。暴力の行使によって、とにかく人間性を否定しようとする。奴隷が人間であることを否定しようとする。そうしたことが頻繁に行なわれていたのだ、と。
平田 奴隷制の具体的な暴力の場面は、これまでも映像(化)などを通して、あるいは歴史書でも描かれてきたと思いますが、メイヤスーの定義を通して「奴隷制」を見たとき、「再生産を認めない」という考え方がすごく圧倒的な力を持っていますよね。これは「脱人間化」、「脱市民化」、「脱性化」という3つを貫く考え方だと思います。
普通の社会であれば、親が子供に(あるいは逆もしかりですが)、なにか自分が生産したものを与えるのが普通です。それは、あらゆる社会で見られる行為です。しかし、奴隷にはそれを認めない。生産物すべてを収奪するのだ、と。その部分は、インパクトがありますよね。再生産の領域を壊すことが、奴隷を供給している地域や国の文化、社会を壊すポイントとしても目指されているところが圧倒的に怖いところです。ここには、知的な認識を刷新させてくれるものがあると思います。それがまさに「奴隷制の暴力性」です。
再生産を認めないということは、もちろん親族として認めないということと結びつくわけですが、まさにフランス革命やアメリカ独立革命以後の、国民として認めない、生まれを共通のものとして認めない、結果として共同体の一員としては認めない、という問題に繋がる。
中村 少し捕捉すると、言語学者のエミール・バンヴェニストが、「自由」という単語は「一緒に生まれて一緒に育つ」ことに語源があることを確認しています。要するに、自由は、親族に認められているものなのだ、と。
多くの社会は、家族を中心につくられています。家族のなかで家族内生産をしています。その生産には、なにかを耕してつくる農業、そして狩猟のほかに、もうひとつ、家族内の再生産として労働力にもなる「子」が位置付けられています。奴隷の場合には、この親族のロジックのなかに入らないところが重要です。
これはメイヤスーが言っていることですが、奴隷は、労働力を増やすためのリプロダクションという意味で機能していると捉えられがちだけど、必ずしもそうではないのだと。
たとえば、アフリカで奴隷の女性が重宝されるのは、多様な仕事を男性よりもうまくできるから労働力としての価値があると認められていたからだとメイヤスーは言います。子供をつくるのは、むしろ自由な人間のすることで、奴隷の女性が子をつくり、親になることに価値は置かれていなかった、と。
さきほど平田さんがおしゃってくれたように、奴隷がリプロダクションというサイクルから外されることによって、生まれてくる子供は、すべて奴隷制内、隷属の中で機能していくわけなので、そのような切り離しがあるのですね。その根幹になるのが親族性です。自分の親族であるのかどうか。その部分で常に白人性を担保し、それが男性原理として機能することで国民の話が出てきた。
平田 いま、中村さんがお話ししてくださったヨーロッパで生まれた男性原理としての国民と、どこかで結びつく話をすると、あらためて本書の前半のミシェルの議論を読み返して面白いと思ったのは、世界史的に奴隷制自体はどこでもあった、しかし、大西洋世界の奴隷制が特殊なのは、そこから人種の概念が生まれたところなのだ、と。
歴史的に遡っても、世界中どこでも奴隷制はあったのですが、キリスト教徒やイスラム教、ユダヤ教が争っている時代には、それぞれの信徒間では絶対に奴隷を生み出さないわけですね。こうした各々の宗教共同体間のルールが、結果として奴隷にするための人間を遠くに求めるようになった。
また、ヨーロッパ自体がすごく特殊な国家の形成をしているのだ、と。つまり13世紀から15世紀に入るまでは地中海すら自分たちの領土にはできていませんでした。常にイスラム圏の支配にあり、そのなかでキリスト教は、9世紀頃から教会と王国が特殊な結びつき方をしてきた。
その特徴として、歴史的にはレコンキスタや十字軍の運動がある。その特徴として挙げられているのが、一つは「無主地(テラ・ヌリウス)」ですね。キリスト教が治めていない国は、自由に侵攻していいのだという考え方です。そこで、ある種の聖戦論が確立する。戦争や暴力の正当化の中で、捕虜にした者を奴隷にしてよいという奴隷制が、まず地中海の覇権をめぐるなかで出てきた。その後、大航海時代に、だんだん外に伝播していった。カール・シュミットも『大地のノモス』で似たようなことを言っていた気がしますが、ここまで歴史的に整理はできていなかったように思います。
そこからまた産業化の時代とともに、奴隷制のあり方が変容しながら存続していきます。奴隷が解放されたあとにも、植民地主義が存続する話は、歴史的にもダイナミックです。ともすると、シャマユーの『人間狩り』は、エッセイ調のよさがもちろんありますが、地域や時代が飛び交って論じられて「自由すぎない?」と思ってしまう面もあるのですが、『黒人と白人の世界史』は、もう少しがっちりとした歴史的な読み物として濃密でありながらすごく読みやすい本ですよね。ですので、2つの本を絡めて読むことの意味はすごくあるではないか、と思います。
酒井 『人間狩り』と『黒人と白人の世界史』は、交錯する部分がとても多いですよね。実際、「奴隷」というのは「狩り」の帰結なのです。いま平田さんが言われたように、奴隷制の独自性とは、人間の再生産にコストをかけずに労働力として「狩れる」という点ですよね。
普通の社会は、人間の再生産、つまり人間を育てることに意を注ぎますし、実際そこに膨大なコストをかける。奴隷制というのは、そのコストを削減できるわけです。それがなぜ可能になるかというと、「暴力」つまり「狩り」があるわけですね。これが近代そして資本主義の初発にあるわけです。そして、これはマルクスが「本源的蓄積」や「資本主義の原罪」と表現したものでもある。奴隷貿易から始まる資本主義、あるいは植民地主義から始まる資本主義というものは、いつも暴力を基盤としているわけですが、それが不可視化されていく。
『黒人と白人の世界史』は、おそらく今の人文社会科学の動向を集約しているような本だと思います。さきほど、人文社会科学の地殻変動の中心のひとつに「レイス(人種)」の問題があると言いましたが、いまレイシズム論になにが起きているか、近代史の認識に何が起きているのか、いまの人文知がどれほどの達成をなしつつあるのかは、この本を読むとかなり見えてくると思います。
この本で言われていることは、奴隷制がレイシズムに先立つということです。「人種(レイス)」という概念にも先立っている。レイス概念は、それこそフーコーも講義で扱っていますが、もともと社会の内的分裂と闘争を表現する概念として使われて、階級間の争いにも使用されていました。この系譜が19世紀に階級闘争の概念にも流れ込んでいきますが、一方で、生物学化されてナチスの反ユダヤ主義で頂点に達する近代的レイシズムを構成していきます。
この社会の分断をめぐるアンビヴァレントは重要です。バーバラ・フィールズのような歴史家たちは、「レイシズムはヴァージニアから生まれた」という視点を強調します。植民者たちはタバコなどの貿易で儲けることに気がついて、最初に採用したのは、年季奉公人というかたちでした。年季期間内の奉公人の扱いは奴隷に近いもので、これも当然、うまくいきませんでした。ここで初めてアフリカ人を引っぱってくる方法が採られます。ただこれも、当初から奴隷として使用するというまとまった発想があったわけではありません。だからアフリカ人といっても、さまざまな立場がありました。自由人であるアフリカ人もいましたし、白人の子どもを養子にするアフリカ人もいました。
決定的な転換点が、1676年のベイコンの叛乱であると言われています。年季奉公人と奴隷たちが、白人と黒人も混然となって植民地支配者に対して蜂起します。つまりそれは、階級闘争的色彩の強い叛乱だったのです。これに危機感をもったプランターたちは分断を謀り始めます。白人か黒人かによって法権利を区別するわけです。
このような契機が、レイスという観念に結晶していく。そして、注目すべきは、このヴァージニアにおける「レイシズムの誕生」には階級闘争が先立って、レイシズムそれ自体がこの階級闘争の「ずらし」として生成しているということです。さらに、ここで重要なことは、この過程がレイシズム、つまり内的な劣等性に必然的に結びついていたわけではないということです。劣等であると見なされているから奴隷化されたわけではなく、奴隷化されてから劣等と見なされ始めたのです。
アメリカ大陸でアフリカ系黒人とヨーロッパ貧民が連携して蜂起を起こした。それに対する危機感から分断策をとるのです。ある意味では、階級闘争を抑えるために、レイシズムやニグロという概念が発明されてきたわけです。
『黒人と白人の世界史』のキー概念は、中村さんが言われたように、「ニグロの虚構と白人の虚構」というものです。「ニグロ」と「白人」が虚構として徐々に成立していったということ。アフリカ大陸は多様ですから、そこには民族がたくさんあって、実際はものすごく細分化されている。
これは余談ですが、リチャード・プライヤーというアメリカの伝説的な黒人スタンドアップコメディアンがいて、1960年代のブラックパワー以降にすごく人気がありました。「神様えらい」という、彼の有名なギャグがあります。「神様えらいね、アフリカ大陸では「俺が◯◯族だ、◯◯族だ」とワーワーと混乱しまくって、とんでもなかった。神様、あるとき怒って「お前らは喧嘩ばっかりして!」。神様偉かったね。こうやってまとめてくれたんだ。「お前らみんなニガー!」。
「アフリカ」と言ってもものすごく多様な民族がいるのですが、その民族間の抗争をヨーロッパの人々が利用し、奴隷制度を先にアフリカでつくるわけですよね。ヨーロッパはそのエージェントと化していくわけです。そしてニグロ化という虚構が始まっていく。その反射概念として、白人という人種も形成されていった。
みすず書房から出ているマーカス・レディカーという歴史学者の『奴隷船の歴史』(上野直子訳、2016年)という本があります。そこに、とても印象深い記述があります。
それがなにかというと、奴隷船という現場における権力関係は非常に危ういものなのだ、と。つまり、奴隷船のなかでは奴隷のほうが圧倒的に数が多いわけです。そして奴隷を管理する水夫は貧民であり、奴隷船の上でも搾取されている存在です。だから、しょっちゅう反乱が起きる。それで、船長と幹部はものすごく横暴な管理をしようとする。そうしないと、収まらないほどに頻繁に反乱や蜂起が起きる。アミスタッド号の反乱が成功例として有名ですが、それはほんの氷山の一角です。いずれにせよ、奴隷船内は、いつもものすごい暴力空間になっていた。
とくに海岸が近づいてくると反乱が起きやすい。海の中だと逃げ場がないですから、陸地になんとかたどり着き逃げられるくらいに陸が近くなると、奴隷と水夫 vs 船長と幹部という図式の対立が激化しはじめる。
しかし、陸にそのまま着いてしまうと、今度は水夫が船長側に寝返るわけです。水夫はそこで仕事はおしまいなわけで、はやく奴隷を売って報酬を得たい。こうしてアフリカ人は「ニグロ」として売られていく。このように階級対立がレイスによってむきだしにズラされていく力学が見事に描かれています。
こうした奴隷船における反乱を鎮圧してきた経験が、資本制のプランテーションのひな型になり、さらには工場労働のひな型になった、という議論も強力になっていますが、このモデルがその後の数百年を支配していく。実際に、いまだに階級対立はレイスによって分断されていますよね。おそらく資本主義は、どんどん人手を必要としなくなりますから、レイシズムはより活発化していく、というか、近年よくいわれる「レイスなきレイシズム」もより増殖していくのではないでしょうか。
ここで、少し『人間狩り』の方に戻りますが、この本に感動的なところがいくつかありまして、ひとつは、19世紀にヨーロッパで労働者たちが外国人労働者を「狩る」事件がありました。その後の労働運動の対応が素晴らしい。「万国の労働者は友愛のもとに連帯しなければならない」という声明を出すのです。これがマルクスらの『共産党宣言』とも呼応している。労働者というのは、生まれではなく、境遇や経験によって一体なのだと。それによって外国人排除を抑えていくエピソードです。
もうひとつは、16世紀のスペインの宣教師・ラス・カサスの言葉を使って、シャマユーがカール・シュミットの批判をする箇所です。シュミットは、自身が全体主義者にもかかわらず、ヒューマニズムが全体主義を生み出す、などと嘯き、ヒューマニズムを批判するわけですね。日本でも腐るほど見る浅薄な論法です。それに対して、ラス・カサスはこういっています。人類を分断し、排除する者こそ非人間なのだ、と。「人類は普遍的だから、普遍的人類から劣っている人間は排除していいのだ」というのがレイシズム的ヒューマニズムだとしたら、「人間をそうやって序列化するものこそ人間主義(ヒューマニズム)を理解していない」と批判します。これも感動的ですね。ラス・カサスが絡む話はだいたい感動的ですが…。
そういう意味でも読みどころがたくさんある2冊の本です。
中村 ありがとうございます。最後はラス・カサスの話まで。私もラス・カサスを読んでいるといつも泣けてきます。本当に素晴らしい人だなと。
(第3回へ続く)
著者紹介
酒井隆史
1965年生まれ。大阪府立大学教授。専門は社会思想、都市史。著書に、『ブルシット・ジョブの謎』(講談社現代新書)、『通天閣』(青土社)、『暴力の哲学』『完全版 自由論 現在性の系譜学』(ともに河出文庫)など。訳書に、デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ』(共訳、岩波書店)、『官僚制のユートピア』(以文社)、『負債論』(共訳、以文社)、ピエール・クラストル『国家をもたぬよう社会は努めてきた』(洛北出版)など。
中村隆之
1975年生まれ。早稲田大学准教授。フランス語を主言語とする環大西洋文学、広域アフリカ文化研究。著書に『エドゥアール・グリッサン』(岩波書店)、『野蛮の言説』(春陽堂書店)など。訳書に、アラン・マバンク『アフリカ文学講義』(共訳、みすず書房)、エメ・セゼール、フランソワーズ・ヴェルジェス『ニグロとして生きる』(共訳、法政大学出版局)、エドゥアール・グリッサン『フォークナー、ミシシッピ』(インスクリプト)など。
平田 周
1981年生まれ。南山大学准教授。思想史。共編著に『惑星都市理論』(以文社)など。共著に、『コロナ禍をどう読むか』(亜紀書房)、共訳書に、グレゴワール・シャマユー『人間狩り』(明石書店)、クリスティン・ロス『もっと速く、もっときれいに』(人文書院)など。