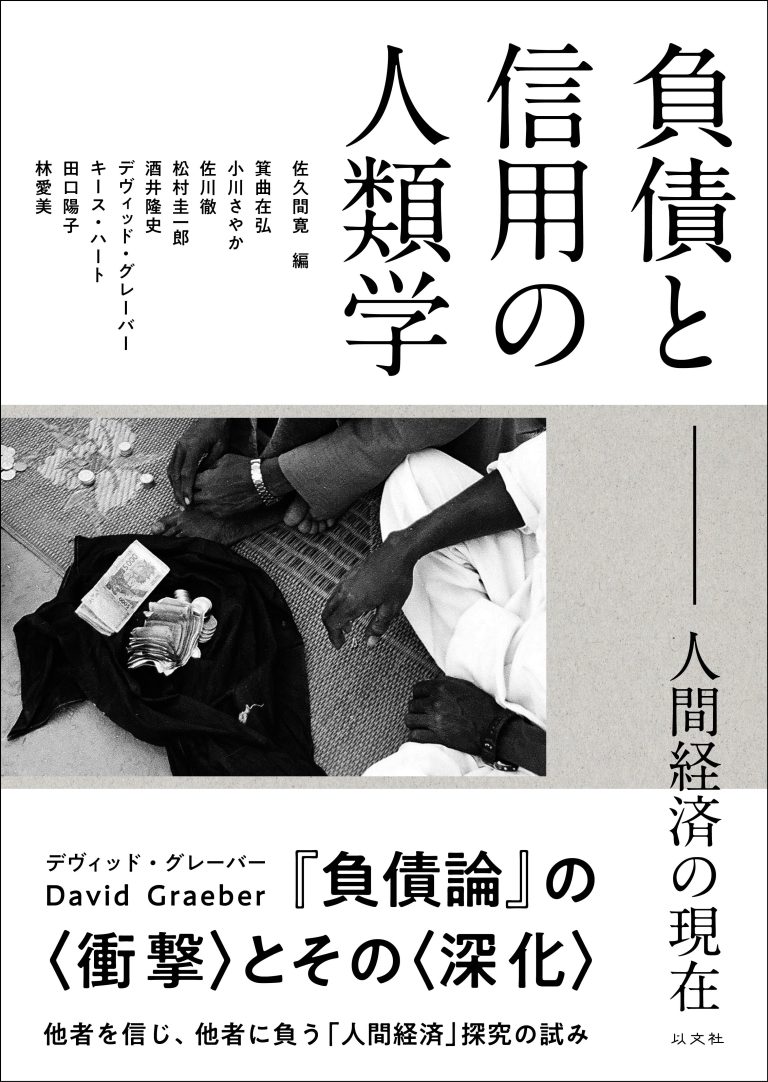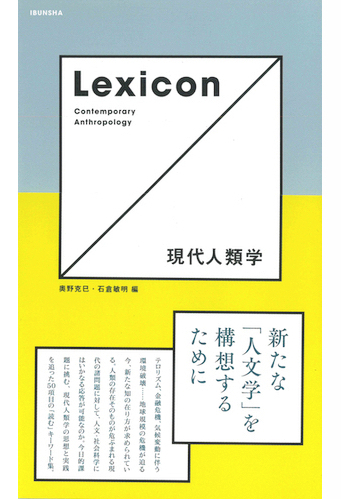祖父の時代のはしか
━━ブラジル先住民とCOVID-19
カルロス・ファウスト,パウロ・ブル
(近藤 宏 訳)
 Photo by Carlos Fausto/Arquivo Pessoal
Photo by Carlos Fausto/Arquivo Pessoal
訳者まえがき(解説)
ここに訳出したのは、ブラジル出身の人類学者カルロス・ファウスト(国立博物館社会人類学大学院教授)が、2020年のCOVID-19の流行を受けて、オンラインジャーナルサイトNexoに不定期に発表した一連のエッセイである(三番目のエッセイは、ファウストの所属する大学院で学ぶ院生のパウロ・ブルとの共著となっている)。
ファウストは、ヴィヴェイロス・デ・カストロを指導教官に、パラカーニャというアマゾニア先住民についての人類学的研究で学位をえると、その後には、クイクロという先住民の下でおもに儀礼と芸術に関わるリサーチプロジェクトに着手している。ほかにも、アマゾニア地域の考古学者と共同で、先史時代や植民地期の過去と現在を貫くアマゾニアの社会論理の分析をするなど、研究者として精力的な活動を展開している。ブラジルやアマゾニア地域に限らず、人類学というアカデミアにおける先進的な研究をけん引する研究者のひとりで、今回の一連のエッセイにはそうした学術的成果が節々に反映されている。
2020年の4月から7月までの異なる日付が付された三つのエッセイには、それぞれの時点における懸念が記されている。まず、COVID-19がクイクロの下に到着する前には、「パンデミックとは何であるのかを、その身体をもって覚えねばならなった」クイクロの人びとの、過去のパンデミックの記憶やブラジルの先住民を襲ったパンデミックの歴史が、これから起こりかねないことの予示として語られる。
なかでも強い印象を残すのは、ひとつの感染症は別の感染症と連なることでその致死性を増すという点だろう。4月には確認されていた先住民ヤノマミの下での最初の死者の場合も、COVID-19の症状が顕在化したのは、マラリアの発作に襲われた後のことだった(注1)。COVID-19も後遺症の可能性が様々に指摘されているが、パンデミックの危険性を単一の感染症そのものの致死性に帰することなく、別の疾病との複合によって生じる危険性を考古学的調査にも基づく歴史的教訓としてファウストが引き出していることは、注目すべきではないか。そのようにイメージされる危険性が前提になれば、広範かつ持続的なケアの体制を確立することが求められる。
そこで問題になるのが、統治である。二つ目のエッセイでは、ブラジルの現ボルソナーロ政権について、その名を出すことなく痛烈な批判がなされている。現代の失政とほぼ同じかたちをした植民地期の失政を掘り起こすことで、いかに統治者たちが歴史、すなわち人間社会の現実に疎いのかを浮かびあがらせている。その失政とは、天然痘患者を新大陸にもたらすことになった船の船長に対する人々の応答で、その船長は「感染者を立ち入るに任せて、狡猾にも、多くの人びとに対する破滅を運び込」み、「無秩序の推進者」になったのだった。
そして第三のエッセイでは、現政権下で展開される先住民に対する失政が、より直接的なかたちで問われている。よく知られるように、ボルソナーロは、先住民に対する攻撃的態度を前面に出し、大統領の座に就くことに成功した。それを助けたのは、先住民の生活領域を経済フロンティアに変えることを望む勢力である。
彼の就任後、COVID-19の流行以前から、現政権は先住民の諸権利を事実上形骸化するための行政改革や法整備を進めている。その一例は、先住民政策について中心的な役割を担うFUNAI(国立インディオ財団)の人材配置転換で、2019年には反先住民、アグリビジネス寄りの立場で知られる人物が代表を務めている。
第三のエッセイの冒頭で言及されるイバマの環境保全局長の罷免と同型の人材配置である。また、先住民領土画定についても、現政権下では先住民側の権利申請は認可されず、反対に、先住民領土としての認可を待つ土地における農業従事者の占有権取得数が従来の政権にはない規模で増えている(注2)。パラカーニャの人びとが直面する問題と同型の帰結は、別の先住民に対しても生じている。
現政権の統治の様子を描く第三のエッセイは、「牛の群れを通過」させるというある行政官のことばを引用した一文で閉じられている。だたしファウストは、「deixar」という動詞を追加しながら引用することで、「牛の群れが通過するに任せる(deixar)わけにはいかない」と、自らの意思を率直に語っている。このdeixarという動詞は、第二のエッセイで、船長のふるまいを叙述するためにクロニスタによって用いられたのと同じもので、任せるとも放置するとも訳される。異なる時代における失政のありようを記すのに、同一の動詞が用いられていることになる。
実のところ、このdeixarという動詞は、統治性の記述に用いられていることもあり、よく知られたフーコーの生権力の定式、「生きさせ死ぬに任せる(fazer viver e deixar morrer)」を思わせる。生権力の「死ぬに任せる」という否定的な働きについて、市野川は、死が不作為の帰結であるかのように現象すると述べているが(注3)、ファウストが問題化している事態は、死そのものではないにせよ、先住民に対して負の状況が不作為の帰結であるかのように現象するような条件であることが、三つのエッセイから浮かび上がってくる。
第二のエッセイでは、負の状況が生じるに任せる統治をファウストは端的に失政と形容するが、その失政とはただ何もしないだけではないということが、第三のエッセイで示されている。彼らによる統治は、著しく法規範に反するものとなっているのだ。「パンデミックに付け込み」なされているのは、法規範と統治、行政執行が著しく対立し、執行が法規範から解き放たれる状況、「例外状態」に通じる道筋を創出することである(注4)。
法規範に対する執行の優勢は、特定の目的に適うこととして行政執行が正当化されるために生じる。現代のブラジルにおける統治上の目的とは先住民の生活領域を経済フロンティアに変えることで、そのために「1954年のはしか」以降に獲得されてきた先住民の諸権利が、ないがしろにされている。
それとは正反対の統治のイメージを、ファウストはクイクロの指導者たちのふるまいに見出していた。指導者たちが行なっていたのは、単に困難に立ち向かうことだけではない。クイクロに限らず南米低地先住民のあいだでは、人びとのあいだの良い関係性はあいさつや訪問を継続することによって維持される。ロックダウンは、こうしたモラルに基づくと、「とても難しくつらい」ことになる。そしてそれにもかかわらずロックダウンするという統治上の判断には、困難に立ち向かうにあたり、従来のモラルに基づく価値判断を放棄し、別の方向へと人びとを導くことまでが含まれている。
ファウストも想像していなかったような、法的に破綻した考え方に基づく判断に歯止めがかかるとは限らない状況が、現在のブラジルにはある。それを受けてなお記された「われわれは、牛の群れを通過するに任せるわけにはいかない」という表現には、強い決意が込められているだろう。
そこに賭けられていることのひとつは、クイクロの人たちが体現するような統治を、どれだけそうした社会において広められるのか、ということにあるのではないか。ファウストがアマゾニアの先住民に見出したもののひとつは、多数の上に立つ一者の絶対的権力を想像させない支配のイメージである(注5)。
そのイメージに従えば、ブラジル社会において統治者だと思われている一派だけが統治をする者である、と考える必要はなくなる。危機を放置する失政者を批判するだけでなく、「荒海に立ち向かう」統治を引き受ける者になることが、問われているのではないだろうか。
ファウストは、COVID-19がシングー川上流に到着するころからクイクロの指導者たちと連携し、行政が準備をしないであろうCOVID-19対策を自前で準備するクラウドファンディングプロジェクトを成功させている(注6)
(1)Bruce Albert “Covid-19: Lessons From the Yanomami” New York Times 2020.04.27.
(2)Illegal farms on indigenous lands get whitewashed under Bolsonaro administration”Monogaby 2020.06.23
(3)市野川容弘 (2000)『身体/生命』岩波書店、五六―七頁
(4)大竹弘二(2018)『公開性の根源――秘密政治の系譜学』太田出版、第四章。
(5)Cozta, Luis & Carlos Fausto 2019 “The Enemy, the Unwilling Guest and the Jaguar Host: An Amazonian History”. L’homme 231-232: 195-226.
(6)Covid-19 Crisis in Amazonia Kuikuro Initiative. https://www.flipcause.com/secure/cause_pdetails/ODQ0ODE=
「祖父の時代のはしか」疫病の時代におけるエスノサイドの記憶(2020/4/25)
2週間前、カナリ・クイクロが、妻と子どもたちと暮らしているシングーの先住民領土(Terra indígena)の小さな町カナラナから、わたしに電話をかけてきた。
カナリ「やあ、パム(イトコ)、わたしたちは恐れている。村に戻ろうと思うんだ。もう少ししたら全部閉まってしまうし」
カルロス「パム、無理をしないで。隔離を行ないたければ、きみたちは戻ればいいだけだ。これは深刻な病気だから」
カナリ「まったくだよ、パム。わたしの祖父アガチパの時代のはしかみたいだ」
わたしがアガチパと出会ったときは既にだいぶ年を召していたが、頭の回転も良く、まなざしもしっかりとしていた。優れた、神話と記憶の語り手だった。長寿だったからである。彼は、20世紀にシングー川上流の住民たちを襲った、疫病の流行を何度も生き延びた。
1954年のはしかの流行は、なかでも最も記憶されている。あっという間に広がり家族全体を襲ったので、死者をきちんと埋葬する時間もなかった。全員が病気を患っているから、食べ物を準備できる者は誰もいなかった。遺体を扱う者など、もってのほかだった。ハゲタカたちが集まり、人間は離散し、病気を別のところへと運んでしまう。そんな時代だった。
先住民たちは、この歴史物語をよく知っている。入植のはじまりから、パンデミックとは何であるのかを、その身体をもって覚えねばならなった。天然痘、はしか、水痘、インフルエンザ。多くの場合、ある病気に続けて別の病気がはやり、ひとつの病気を生き延びたとしても、健康を取り戻す時間がなかった。
アンシェッタによれば、1562年、ある疫病が、バイーアドス・オス・サントスのトゥピ系先住民を3万人、死に追いやった。翌年、天然痘が生存者の多くを苦しめ、飢餓が残りの住人を滅ぼすことになった。こうしてバイーアは無人になった。1580年にアンシェッタは次のように記している。「20年のあいだにこの場所の人びとが失われてしまったことは、(中略)とても信じられないことのように思われる。これほど多くの人が消えてしまうことはなかったし、ましてやあれほど短期間でそうなることなど、誰もこれまで想像したことなどなかった」。
これと同じ歴史は、今日ではブラジルの一部となるさまざまな場所で、何度も繰り返されてきた。その一部は、文字によって記憶されている。たとえば、ジョアン・ベテンドルフ神父は、1695年にパラーで広まった「痘瘡」(天然痘)についてわれわれに伝えているが、それによって別の病気も発生したという。「痘瘡が完全になくなった後には重度の風邪が広がり、それによって多くのインディオが死んだ。さらに続けて、はしかのようなものが到来し、何カ月も続いて、多くを殺した」。
こうした健康をめぐる危機の多くは、宣教師、植民地行政官と旅行者の眼とペンの届かないところで生じてきた。今日、クイクロやほかの先住民族が暮らすシングー川上流の考古学的遺跡を調べると、17世紀の始まりにある断絶が発生していたことがわかる。そこに存在していた村々の規模と数に明らかな減少がある。その地域の先住民の人口はおそらく、現在のものよりも10倍から20倍、合計5万から10万人ほどだった。だが、17世紀初頭に何かが起こり、大きな村々が放棄された。一連のパンデミック――なかでも天然痘が突出していた――が引き起こした人口学的難局というのが、ありうる仮説である。天然痘ウィルスの致死性が極めて高いだけでなくその「感染経路」が広いということも、その理由になる。まだ発症していない患者が、感染者のいる村での死から逃れて、彼とともに、記録者たちの叙述に倣えば、「ペスト性の悪」をさらなる奥地へと運び込んだ。そういうわけで、天然痘がシングー川上流に到着したのは、最初の先住民奴隷が登場した時期——すでに18世紀だった――よりも、何十年も早かったはずである。
この最初の疫病に続いてほかの疫病も起き、それらの多くは今日のシングーの人びとの語りによって、半分歴史的に半分神話的に叙述されるが、決まってそれは悲劇となる。だが、1954年のはしかの叙述は、疑いようもなく、1954年のはしかそのもののことである。シングーの人びとは何が起きたのかをよく知っている。とりわけ、もし医療的援助、そしてなによりも、食糧の援助がもっと早く到着していれば、より多くの生命は守られただろうということをよく知っている。だが資源は不足し、コミュニケーションは脆弱で、さらに多くの困難があった。そして今日のように、ワクチンはない。
1970年からワクチン接種のプログラムが行なわれ、先住民の子孫たちの人口曲線は反対の方向に進んだ。大きな人口喪失から四半世紀の後に、わずかに増加し始めた。増加のカギになったのは、ワクチン接種、医療サービス、領土の保全という三つ組である。この生命のための闘いにおいて基礎となる枠組が、1988年の憲法に続く領土画定と、1999年の先住民特別衛星地域(DESI) 〔全国規模の衛生行政機構かつ地域区分〕の設置である。
今日では、これらの全てが危機に瀕している。それは、この新たなウィルスに対するワクチンや治療法だけではなく、この危機に立ち向かう用意のある政府もまた、われわれは手にしていないからでもある。ブラジル政権は死に夢中になっていて、誰の眼にも明らかな事実を感じ取ることがないように思われる。「祖父の時代のはしかのようである」。街路にある埋葬前の遺体、村々での尽きることの無い死。緊急の公衆衛生対策は、先住民と彼らの土地を守るようにして、なされる必要がある。われわれは、新たなジェノサイドを引き受けるわけにはいかない。
シングー川上流の歌い手のひとりで、われわれが撮影した映画「ハイパー・ムリェール(As hiper Mulheres)」の主役であるカヌがわたしにオーディオメッセージを送ってきた「わたしたちは怖いけれど、大丈夫。病気はここまではたどり着かないから」。まだ、息をつける日である。だが、いつまでだろうか。
 Photo by Carlos Fausto/Divulgação
Photo by Carlos Fausto/Divulgação
「村でロックダウンをしようじゃないか」失政と先住民による統治(2020/6/12)
土曜の午前中、イトコであるカナリ・クイクロがわたしに何度も電話をしてきた。わたしは、市場にいた。土曜日は、必需品を揃えるために、家から出る日にしていた。家に戻り、携帯電話のスクリーンを見ると、何度かの着信履歴があった。さらなる知らせかもしれなかった。確かにそうだった。COVID-19が、ついに、シングー川上流にたどり着いたのだった。
30分ほど話をしたが、彼の祖父の時代のはしかについてさらに話し込むことはなかった。とうとう、われわれの時代がきた。疫病は、この世代のものになった。クイクロのリーダーたちの集まるWhatsAppグループに参加し、情報を確認することにした。現グアチャ・ド・ノルチ市会議員であるムトゥアは落ち着いた声で、公式発表を待つように求めた。その知らせは、午後に、シングーのDSEIの専門家による通牒として届いた。セパザル村のカシーケとその息子がSRAG(重度急性呼吸症候群)の症状を呈したまま、その地域から隔離された。COVID-19の検査は陽性で、クイアーバへと移送された。確認されてはいないが、ほかの集落のひとつが位置しているシングー先住民公園の境界部でも別の事例がいくつかあるという知らせもあった。
260万ヘクタールに及ぶシングー先住民公園には、今日、16の先住民族からなる7000に及ぶ人々が暮らし、そこでは、多民族・多言語的で生き生きとした体系がかたちづくられ、極めて稠密な社会・儀礼的生活が送られている。孤立した集団が分散した無人の緑地というアマゾニアのイメージは忘れてほしい。わたしが述べているのは反対のことである。そこには、数十もの村々がつながるネットワーク状の地域的な体系があり、情報も、人も、物品も、不幸なことにウィルスも、そうした環境で流通する。
このネットワークは、植民者のもたらした疫病――ウィルスが数百、数千キロの奥地まで人から人へと運ばれた――によって、急速につくられた。皆が死にゆくとき、まだ生きているものは別の村へと逃げようと試みて、網状組織を活用した。こうして、病気は一人ひとりからより多くの者たちへと運ばれたのだった。まさしく、これこそが、今日シングーに到来しないかと恐れていることなのである。だからこそ、迅速かつ勤勉に動かなければならない。
過去の疫病には、現代においても学ぶべきところがある。前回の記事〔前節の記事のこと〕でもあつかった1695年のマラニョンやパラーにおける破壊的な天然痘の流行に戻ろう。ベッテンドルフ司祭によれば、サンルイスにある奴隷船が到着した時に「疱瘡を患う者が一人」いた。船は街の港に停泊することは禁じられた。だがその用心も、奴隷の労働力を求める居住者の強欲と損失と被害について市を相手に訴訟を起こすと脅迫をする船長の利害のために、緩められてしまった。その帰結は? 死に次ぐ死、だった。数カ月のあいだに、疱瘡はマラニョンからパラーまで広まった。そのキリスト者が鋭く結論するように「みずからの[強欲の]援助をするように思えた者が、自らの恐ろしい破滅を支持していた」。もちろん、もっとも大きな勘定を支払ったのが先住民だったことは明らかである。「多くが、斃れ死んでいった。ときには、生きている者のケアをして死者を埋葬する者がいなくなることもあった」。
迅速さと勤勉さは、パンデミックを前にした行政活動にまさしく欠けているものである。そのことは認めなければならない。われわれの前にあるのは、失政である。住民の暮らしと福祉とを助け推進するべき者が、ベッテンドルフの叙述にある船長のように、まさしく無秩序の推進者となっている。彼は感染者を「立ち入るに任せて」、狡猾にも、多くの人びとに対する破滅を運び込んだ(だがご存知の通り、その破滅はけっしてあらゆるものに等しく破滅的であることなどなかった)。
COVID-19は飛行機に乗った旅行者によって、ブラジルに入り込んだ。そもそもの始まりは金持ちの病気だったが、ブラジルの不平等のトポロジーに従い感染拡大した。社会的隔離は、自家用車を持ち、デリバリーで買い物ができ、ホーム・オフィス用のブロードバンドインターネットなどの資源がある、一世帯住居では相対的に容易に行うことができる。自己隔離というものは、何らかの行政支援がなければ、多くの住人の手には届かないぜいたくなのである。とりわけ人口の1%に国民所得の1/3が、その半分が人口の10%に集中するような国では。このような状況では、失政はわれわれ皆を同じような仕方で脅かすことなどない。この要件からすれば、先住民は最貧困層となる。そして、最貧困層のあいだで、感染者数の上でも死亡率の上でも高い数値が確認さえている。
先住民のジェノサイドを避けるために国際的・国内的な圧力が高まっており、それを受け、歩みは遅いとはいえ、統治機構も動き始めている。だが、今のところ、DSEIからの報告をまとめると、期待することはできない。何よりも、都市部にある先住民保健センターでも先住民地区でも、保健所員が感染の媒介者となった事例もあった。また最近のニュースによれば、ツムクマアケの先住民公園へのウィルス侵入の責任は軍に帰される可能性がある。これらの事実は、いかにトップレベルでの失政が末端の役人たちにも行き届いているのかを、示している。保健政策は、医者の扱う事柄である。疫学者や感染症学者を防衛大臣に任命するはずなどないだろう。
この3月から研究者と先住民が参加するグループを結成し、シングー国立公園の大部分に住むカリブ語系の四民族のひとつで、20年ほど私が付き合ってきたクイクロのあいだでのCOVID-19のモニタリングと予防のための活動を始めた。まずパイロットプロジェクトをはじめ、シングー全体をカバーする、より大きなプロジェクトの導入につながることを期待している。われわれの世代にとっての挑戦とは、COVID-19に相対することであり、1954年のはしかに相対することではない。だからこそ、皆が一緒に事を為すのが欠かせない。行政機構、現地先住民組織、研究機関、NGO、そしてこの地域で55年にわたり活動してきたサンパウロ連邦大学のシングープロジェクトの技術的支援も、いつものように当てにしている。先住民の健康を守るのに効果的である統治を確立するために、力を合わせる時なのである。
夜遅くまで、クイクロのリーダーたちとWhatsAppでメッセージを交換していた。保健所の先住民職員であるカウティクがある提案を投稿した。「村でロックダウンをしようじゃないか」。翌日、この文章を書いているあいだに、クイクロたちはどうやって別の村からの親族や友人の訪問を禁じるかを議論していた。これは、関係があることこそが良い暮らしの本質であるという先住民のコンテクストを踏まえると、普通のことなどではないし、とても難しくつらいことである。だが、統治とはこういうことだ。まだ何も起きていないなどと偽ることなく、舵を取り、荒海に立ち向かうことなのだ。
 Photo by Carlos Fausto/Acervo Pessoal
Photo by Carlos Fausto/Acervo Pessoal
牛の群れを通過するように、先住民領土の門戸を開く(2020/7/26)
よく知られるように、偶然とは重なるものである。明るい展望のあるものもあれば、ぞっとさせるものもある。不幸なことに、われわれが語る用意のあるものは、第二のタイプのものである。
4月14日、イバマ(Ibama、Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis)〔環境省の管轄下にある機構、ブラジル環境・更新不可自然資源院の略称〕の環境保全局長が自らの職務を果たしたがために、罷免された。同月、その機関はパラー南部の先住民領土から違法な伐採業者とガリンペイロたちを追い出すために、大作戦を実施した。そうした地域のひとつで、おそらく最も影響を受けていたのが、アピテレワ先住民領土である。そこには、トゥピグアラニ語系のひとつで、1980年代初頭に、〔ブラジル国民社会と〕接触をしたパラカーニャが暮らす。
解雇からひと月ほどした5月22日、環境省の「細かな」提案を耳にしてわれわれはぞっとした。それは、4月22日の省内会議におけることで、連邦政府がパンデミックに付け込み、環境保全の法的基礎となる門戸〔porteira:農園の扉を指すことが多いことば〕を開こうという提案だった。「牛の群れを通過」させると。
4日後、サンフェリクス・ド・シングー市から請願された権利保障令という枠組で、連保最高裁判所判事ジルマール・メンデスがその門戸を開け放った。判事は、この司法行為により、先住民領土の侵入者たちとそこに暮らす先住民との未遂の調停を確定した。その時には、「妥当な調停のために、この出来事について係争中の当事者〔非先住民〕による事前利用を示すだろう公的地図が存在する」ことに、よくわからないかたちで、言及した。偶然にも、問題になっている土地はまさしく、パラー州の南部にあるアピテレワ先住民領土だった。
その裁定で、判事は良識の問題であるかのようにしてその判断を正当化した。「農業従事者と先住民のあいだのコンフリクトに結び付く訴訟の多くは、友好的な解決の可能性を探る事前の対話が、ほとんどの場合、不在であることに由来することがわかった。ウニオン〔連邦政府〕に、サンフェリクス・ド・シングー市によって提案された和解の未遂に対する関与を命ずる」。珍妙な提案である。というのも、1988年からこの問題への解決は探られているし、その解決にはすでに、その先住民領土が一割弱、縮小されることまでが含まれている。いまさらになって、侵入者たちは、残された領土の七割ほどを「友好的に」欲しがっているのである。
さらに珍妙なことがある。認可され登録された、境界確定済みの先住民の領土が先住民と非先住民の交渉の対象になるという解釈である。これは、解釈される案件ではない。問題になっているのは、先住民の権利をその土地にあると特徴づけるわれわれの憲法に従った、基本的権利に由来する十全な法令なのである。さらには、1986年の本源的民事裁判〔諸権利を守るための民事訴訟〕362号に示された歴史的論争は自らが記したものなのだから、判事もよく知っていることだが、先住民の領土は、連邦政府の所有地であり、まさにそうした形式のために、先住民が彼らの土地について交渉し、譲渡し、与えるか貸与することを望もうとも、そんなことはできないのである。
連邦憲法231条の基本的規則に背き、かくも法的根拠に欠けているということから、われわれは、判事の裁定が認められることはないと思い描いていた。しかしながら、6月25日、アウグスト・アラス検事長は、利害関係者と政府全機構からなる公開法廷の招集を決定した。COVID-19によるパンデミックのただなかで、パラカーニャたちは感染を避けるために自己隔離しようと努めていたところで、司法は、侵入者と交渉をするという目的のもと、感染リスクに彼らが曝されることを決めたのである。さらに、互いに交渉がもとめられていることには、交渉可能性など全くないのである。
パラカーニャの民を代表する団体、アソシアソン・タトッアは、パブリックメッセージにおいて、判事による裁定の拒否を表明し、「和解の行為」は「減少の行為」であることを明示し、非先住民の利害関係者だけが対応され、その人物たちが「われわれの領土において、不法に森林伐採や金を採」っていることが許されていると述べる。さらにこの文書が思い出させるのは、「政府はすでに、われわれの土地を10万ヘクタール以上減少させたが、それにもかかわらず、占有者たちはわれわれの領土を侵害し続けている。政府はわれわれに対して、われわれの土地にいる全ての非先住民の退去と追放という仕事をするという負い目がある」ということである。
われわれ筆者はこの侵略のプロセスの証言者であるが、森林伐採、不法採金、アピテレワ先住民領土の土地の不当な占有には、30年以上の歴史がある。1995年1775号令の下に、あらゆる境界確定のプロセスが、行政的対審に開かれ、詳細に調べられたが、ここで問題になっている土地の事例では、瑕疵は一切見つからなかった。1980年代中頃から始まった、マホガニーを輸出する複数の大企業から資本提供を受けた、侵入のプロセスもあった。92年のリオサミットとアピテレワ先住民領土の境界画定令へのサインと同時期には、それら企業は、パラカーニャとアラウェテの領土を横切る道路を建設し、牛の群れの飼育をもっぱら行なう農園主に加えて、小規模・中規模農家の進出の流れを刺激するようになった。こうして、社会的コンフリクトの舞台が作られると、それによって先住民の土地の境界画定とその防衛とが阻まれるようになった。
年月が過ぎ、金鉱、牧草地、違法道路によって裂かれたその土地で、パラカーニャは今日、彼らの領土の用益権の保証を求めている。だが、侵入者たちが現前するために、恐れることなく土地を歩き回るというささやかな権利すら持てずにいる。1990年代から引き続く終わりのない司法的妨害に対して求められるのは、共和国憲法の保障に従い、パラカーニャとその伝統的な生活様式の保護を目的とした、即効性を備えたかたちでの管轄権設定の実施/履行である。
だが、簡素な裁定によって、ジルマール・メンデスは新たな問題を創りだし、友好的な和解という覆いのもとに自分の決定が持つ暴力を隠した。カネターダ〔法定上複雑になる諸問題を、行政的に「解決」したかのようにするために、略式の手続きでできる政令等で済ませること〕によって、歴史を抹消した。さらに悪いことに、これによって、ほかの法定手続き上十全である先住民領土までも脅威が及ぶ。われわれは、さらなる牛の群れが通過するに任せるわけにはいかないのである。