ふたたび都市を争点とするために
「惑星都市理論」についての注解
第2回
北川眞也 × 平田周 × 仙波希望
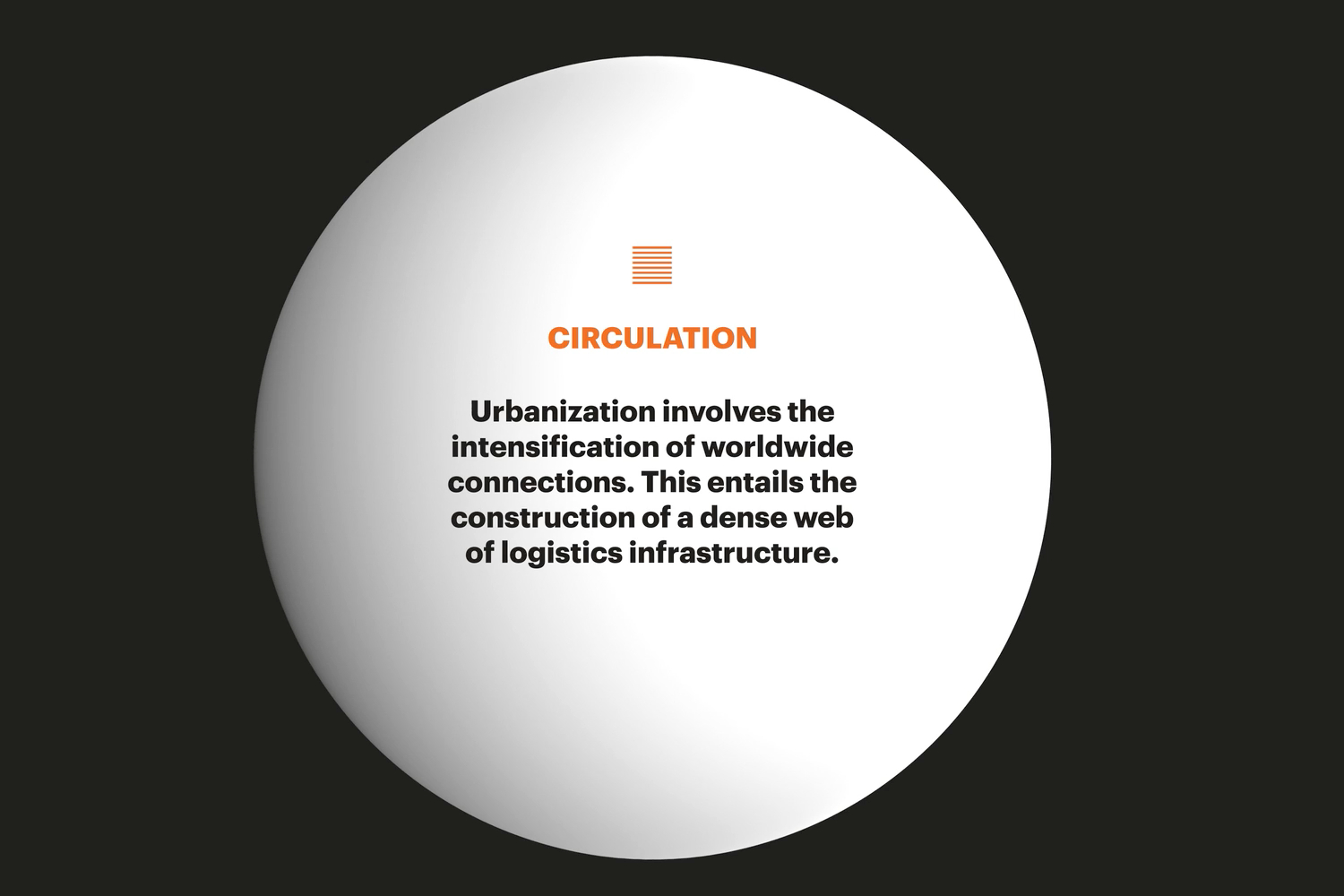
「広範囲の都市化」から見えてくるもの──ヨーロッパ「境界」研究の視座から
仙波 さてここで、本書にもご寄稿くださった三重大学の北川眞也さんにゲストとしてご登場いただき、「惑星都市理論」そして「プラネタリー・アーバニゼーション」について、また別の切り口からのお話をお願いできれば、と思います。
北川 こんにちは。北川です。今日はこうしてお話をする機会をいただきまして大変嬉しく思っております。
先ほどお二人から、領域的に閉じられた都市論、都市をまるで点のように捉えそこで起きていることを論じていくだけではもはや都市を理解できない、ましてや現代において都市を切り取って語ること自体が現実から乖離しているのではないか、といったお話があったと思うのですが、その議論を踏まえた上で、ここは敢えて自分の研究を簡単に振り返るようなかたちでお話をさせていただけないか、と。
これまでの私の研究にとって「プラネタリー・アーバニゼーション」がどういった意味を持ったのか。自己紹介的になってしまい恐縮ですが、こうすることがお二人の問題提起に応答する近道になるような気がします。「惑星都市理論」あるいは「プラネタリー・アバニゼーション」というイメージしにくさもあるこの概念をいくらかクリアにできれば、さらにその先の面白さやアクチュアリティまでをお伝えできればなと思います。
*
私は地理学という分野を専門にしています。研究フィールドはおもにイタリアなのですが、問題意識としてはイタリア以外にもヨーロッパの言わば「境界」についての研究をしてきました。
最近興味を持ってずっと調べていたのが、イタリアにある――イタリアだけでなくヨーロッパの一番南に位置する――ランペドゥーザ島という小さな島についてです。アフリカ大陸のすぐ近くにある20㎢ぐらい、長さは9kmほどありますが幅は狭いところで1.5kmぐらいしかない本当に小さな島で、そこに足を運んでいろいろな話を聞いたりしていました。
私がランペドゥーザ島に注目したきっかけは、この20年、いや、もう30年近く、アフリカやアジア(特にリビアやチュニジアなど)から移民が船に乗ってヨーロッパに漂着しており、われわれもそうしたニュースを幾度となく目にしてきたわけですが、そのヨーロッパへの越境を試みた人びとの多くが最初にたどり着く場所の一つがランペドゥーザ島だったからです。海上で救助された移民もまずランペドゥーザ島へ連れていかれることが多い。一方で、ヨーロッパまでたどり着けないまま地中海に沈んで亡くなってしまう人も大勢いて(ヨーロッパ側の意図的な救助の拒否もあり)、恐ろしいことに、この30年弱のあいだに分かっているだけでも3万5000以上の人たちが犠牲になっています。

そういった島なので、ランペドゥーザ島は「ヨーロッパの玄関」などとも言われているわけですが、ヨーロッパ大陸はもとよりシチリア島からも遠く離れた離島であることを忘れてはなりません。離島性を表す事柄はいろいろありますが、何より病院がなく診療所しかない場所であって、救急の場合、シチリアまでヘリコプターで運ばれます(夏は観光地となり人も相当に増えるのですが)。
ということで、こうした離島の研究を中心にしていた私が「都市について一緒に考えましょうよ」というお誘いを受けても、いやいや私は都市の研究なんてたいしてやっていませんから、みたいな反応に最初はどうしてもなってしまうわけですね。まさに都市と田舎、この場合なら、都市と離島という対立的図式ですね。
私は1979年生まれですが、私の世代の地理学研究者にとって都市論という領域は中心的なものとしてそこにありました。大学院生のときには「空間論的転回」と呼ばれる動きがすでに盛り上がっており(第3回参照)、そこでは平田さんが研究を進めてきたアンリ・ルフェーヴル、ほかにもデヴィッド・ハーヴェイのような地理学の大家と言われる人の著作がとても重要でした。
こうした著名な研究者は、資本と空間の関係を問うなかでだいたいは都市空間、都市論を重視しているわけです。その影響のもとで都市の社会的不平等などを問題化している身近な研究者を横目で見ながらうらやましく思いつつも(笑)、私は北部同盟(現、同盟)というイタリアからの自治や独立を訴えていた地域主義かつ排外主義政党の研究や、イタリアにある移民を閉じ込めている収容所の研究(最近日本でも入国管理センターの暴力が問題になっていますが、イタリアの収容施設も同じくそうした問題を抱えています)、といった都市とは直接的な関係のないテーマに強い興味を持ち、政治地理学、特に批判地政学と呼ばれる潮流の理論や方法論を学んでいました。
そういうなかで『惑星都市理論』のもとになった共同研究へのお誘いをいただき、少々場違いな思いも抱きつつ参加したわけですが、結論から先に言いますと、ブレナーたちのプラネタリー・アーバニゼーションという考えを知ったことで、なんと言いますか、自分がこれまでやってきた研究の断片がつながっていくような感覚があったわけです。
私が唯一都市をフィールドとして少し調査したのが、ミラノの「社会センター」という運動でした。これは空き家や未使用建造物などを占拠し、そこを社会的、文化的、政治的な自主管理スペースに改変しようとする運動です。調査を通じて、ミラノの北西近郊にあるロー(Rho)という町の社会センターにたどり着いたのですが、当時そこの人たちは見本市や万博の問題に取り組んでいました。
みなさんローという町の名前は聞いたことがないかもしれませんが、2000年代前半、その町にミラノにあった有名な見本市会場がより広い土地を求めてドンッとやって来たのです。そして2015年のミラノ万博の会場もそのすぐ隣にできました。
するとどうなるかというと、大規模イベントのためだけのインフラがそこに次々とできていくわけですね。世界中からさまざまなモノや人が集まってきますから、それをスムーズに運ぶための高速道路や鉄道が敷かれ、見本市会場にミラノからスムーズに行くための地下鉄の新駅ができ……後背地だった場所が巨大なインフラ網に接続されていくということが、2000年代に入ってからどんどん起こり始めます。しかも一見すると、昔からあるローの町からはまるで切り離されているかのような新たな空間でありインフラなのです。

ローからずーっと鉄道などで西に行くとイタリア北部のもう一つの大都市・トリノにたどり着きます。そのさらに西、フランスの国境近くまで行くと30年以上も高速鉄道の建設をめぐって争われているスーザという山のなかの町があります。
地元民が中心になりつつ、さまざまな運動体も関与して激しい抗議、直接行動を続けているわけですが、この運動はNoTAV(ノータブ)という名前で知られています。要するに、イタリアの高速鉄道列車がTAV(タブ)という名前なのですが、それ用の線路を通すなってことですね。これはトリノとフランスのリヨン間に高速鉄道を走らせる計画なのですが、最終的にはヨーロッパを東西に貫こうとする大規模な話でもあるわけです。
そうした反対運動があるにもかかわらず、それでも進められようとする鉄道の工事現場は、物々しくフェンスで囲まれ検問所もあり、挙げ句は軍人までいる。まるで武装地帯のような光景になっています。

この光景がなにに似ているかというと、思い起こされたのは、1980年代から多国籍企業や国際金融機関がアフリカで進めてきた資源開発の現場、さきほど平田さんから「Extractivism(採掘主義)」のお話がありましたが(第1回参照)、アフリカの採掘の現場は、住民が追いやられ、民兵や警備員そして壁の建設によって防御され区切られた、地元からすれば「飛び地」のような、採掘のためだけの一つの町みたいになっている。採掘アーバニズムという言い方もありますが、その採掘のためだけにつくられた町はまさに「グローバル経済」というものを通して世界とつながっている。グローバル経済の視点に立てば、この町は「飛び地」ではなく「ハブ」として考えられるわけです。
こうして採掘のためにアフリカ大陸のなかで排除された人びとは、もちろんすべてとかそんな話ではありませんが、アフリカ大陸を転々としたあと北上し地中海を渡り、まさにランペドゥーザ島にたどり着く、といったこともあるでしょう。
そして、ランペドゥーザ島の収容所、次はイタリアの、つまりヨーロッパ大陸の収容施設に移され、そのまま収容施設から「はい、自分で帰ってください」と放り出されることも多く、その後はインフォーマルな労働市場に入り込んだり、たとえばUberEatsで知られるようなライダーの労働(いま世界中でその搾取性、労働の環境の問題、権利のなさなどへの抗議がさまざまに起こっていますが)や物流倉庫の労働などを、移民あるいは難民申請者が担ったりといったことも頻繁に起こっています。
このように私が個別に関わってきた研究テーマが、先ほどお二人が整理してくれたブレナーの「広範囲の都市化」の概念を通して見直すことでつながっていったわけです。
しかし、それはある意味では現実が先行している、現実がそのようなつながりをもって構成されていると言うべきでしょう。それは数々のインフラの建造を通してのことであり、また数々の軋轢を引き起こしながらのことです。こうしたつながりをたどっていったときに、私の研究にとってロジスティクスという概念がとても重要になってきました。それは兵站や商品流通に関わると同時に、それ以上のもの、つまり惑星都市化の空間を生産する一つの主要な原理としてのことです。
いずれにせよ「プラネタリー・アーバニゼーション」——私は「概念」というよりも「発想」というイメージで受け取っています——は、個別の研究テーマを超えるなにかを問う必要があるのかもという思いが自分のなかにも強く芽生えてきたこともあるのですが、重要なヒントを与えてくれるものでした。
平田 北川さんが研究をしてこられたローという町やいまお話のあったアフリカの問題などを捉えるとき、やはりまず不均等発展の問題を考えなければならないわけですが、それが地理に現れたかたちを表現するキーワードとして、ブレナーらによる「まだら状の地理(variegated geographies)」というものがありますね。
その「まだら状の地理」の対極にある世界のイメージや表象が、トーマス・フリードマンが言ったような「フラット化する世界」、要するにICTのようなもので世界各地が結ばれ、均質な世界が生まれるといった見方です。急速な世界各地のインフラの整備とともにそうした世界像が思い描かれているわけですが、にもかかわらず、そこではかならず境界線が作られ管理されていたり、インフラの設備それ自体が分断として機能したりすることで、まさに「まだら状の地理」が生み出されているわけですね。
イスラエル出身で(反シオニストの)建築学者・エイヤル・ヴァイツマンという人がいて、北川さんも今回の論文で触れられていますが、彼がヨルダン川西岸のイスラエルによる占領地域について、そこに敷かれるインフラ網そのものがパレスチナの人びとの移動性を奪い、都市を分断することで彼らの空間的な一体性を困難にしている、と分析します。現在、世界各地でインフラやロジスティクスが整備される一方で、ある種の「閉じ込め」――北川さんの表現ではよりはっきりと「監獄(化)」――が進行しています。
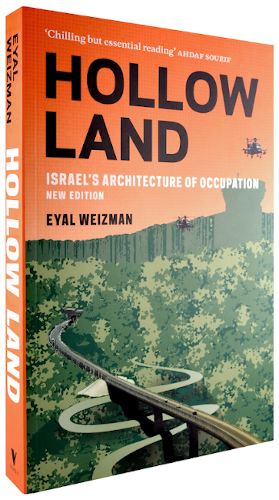
都市をいかに捉え直すか──「高密度の都市化」と「惑星」をめぐって
北川 ここまでお話させていただいた問題をまた別の角度から考えてみたいのですが、「広範囲の都市化」や「まだら状の地理」についてはなんとなく理解していただけたとして、「でも都市ってなんですかね?」という問いがやはりまた出てくると思うのです。いわば「高密度の都市化」は、これを踏まえたときにどうなるのか? と。
先ほども言いましたが、私は都市論や都市研究を正面切ってやってきた人間ではないわけですが、少し思ったことがあったので、それについて少しお話させてください。
いま、ヨーロッパ各地で起こっていることのほんの一例ですが、ローマで――ローマでもいくつもあるわけですが――地中海を渡り難民申請をしていた人たちが、自分たちの居場所がなかったため、使われていない建物をスクワットしそこを生活の場として使っていました。2017年にその場所が排除されてしまったため、またすぐに別の建物を占拠していたのですが、ローマの観光地の近い場所ということもあってか、それもまたすぐに警察がものすごい暴力的に排除した。広範囲のつながりが増えれば増えるほど、ある種の検問所というか境界も増えるわけです。
このような都市のただなかでの暴力を目の当たりにしたときに強く思ったのは、これって地中海で救助もされず船と一緒に移民や難民が沈められる状況――ビザも取れず真っ当な移動手段へのアクセス権を奪われた人たちが溺れ死んでいく状況――と通底しているのではないか、ということだったのです。
都市研究と境界研究とでは用いる用語や理論が異なるために、おそらく「プラネタリー・アーバニゼーション」を知る前だと切り離して考えていたかもしれません。当然、地理的・社会的に隔たった両者がまるで同じというわけではありませんし、追放される当事者からすれば当然のことかもしれませんが、ここには響きあうものがたくさんある。もっと言えば、両者を現実的、理論的にも重ね合わせる、ぶつけあうことで、惑星的広がりのある地理(学)へと接近できる気がしてくるわけです。
こうした人の移動と都市、海と都市との想像上でも現実的でもある連関から考えると、次のように言えるかなと思ったりします。
フランスにカレー(Calais)という都市がありまして、ドーバー海峡を挟んでイギリスと向かい合っている港町ですが、イギリスに行きたい移民や難民の人たちが各地からやってきて、そのカレーという都市のはずれに滞留するわけです。そこを拠点として、そしてドーバー海峡をトラックの下などに隠れて渡る機会を窺う。いきなりは渡れないので、情報を集めたり移動手段を探っているあいだに、カレーのはずれの町が一つの都市みたいになっていく。
どこかでその写真を見せたら「これもう都市だよ」って言われたのがすごく印象に残っていて、そこにはいろいろな場所からきた人たちが、流動的とはいえだいたい数千いて、散髪屋やレストラン、祈りの場もある。この場所にさまざまな運動体や支援団体も引きつけられ、集まってくる。非常に不安定な環境ですし、単純に美化はできませんが、その土地には人びとが「住んでいる」わけです。

またアフリカやアジアに難民キャンプが多くありますが、難民キャンプと聞くと迫害され居場所を失った人たちのかりそめの場所みたいなイメージを浮かべますし、そうした圧倒的に厳しい現実が多々あるため決して一般化はできませんが、最近の議論では難民キャンプ自体が一つの都市だと言われることもあるようです。近隣都市とのつながりのなかで考えられるようにもなっている。それぐらいの規模で人びとが日々暮らして、もうそこで何世代にもわたり生活するよりほかにないわけですね。
カレーの周辺の自然発生的にできた場所は「ジャングル」と呼ばれるんですが――この呼び名は人種主義的で問題ありですが――その「ジャングル」や難民キャンプを通して見たときに、私たちがこれまで都市としては見ていなかった場所も都市として考えていかなければならないのではないか。
これはマイク・デイヴィスが言うような、(労働力としてもはや産業資本には包摂されない人たちによる)スラムやインフォーマルな居住形態が惑星規模に拡大していく動きとも関係するでしょうが(『スラムの惑星』酒井隆史監訳、明石書店、2010年)、より一時的な意味合いが強いはずの、より例外的なニュアンスの強いはずの「キャンプ」が、都市のなかに出現し、都市を構成する。ちなみに、先ほど言及した移民を拘留する国家の収容所もキャンプと呼ばれ、ジョルジョ・アガンベンの主権権力と収容所論を踏まえた研究が多くなされてきました。カレーの自然発生的キャンプはすでに排除されてしまいましたが、集団化し可視的になると排除し、分散させて不安定な移動状態に置いておくの繰り返しです。
こうしたことは、たとえば野宿者の生活に対してもされてきたように思います。実際、野宿者は都市にキャンプを形成してきたとも言えるわけですが、カレーのような状況から照射してみると、そこに内在する政治性、対抗的なインフラとしての拠点性が見えてくるわけです。
ちなみに、釜ヶ崎での日雇い労働者の炊き出しやテント村を「難民キャンプ」としてかつて形容した船本洲治の一文を読んだとき(『[新版]黙って野たれ死ぬな』共和国、2018年参照)、とても印象深かったのですが、こうした(「第三世界」とつながるような)国境横断的な地理的想像力は、キャンプ化の拠点性をすでに踏まえたものだったように思えますし、難民キャンプの拠点可能性すら示唆していたというのは言い過ぎでしょうか。
今日、私が前半に話したことが「広範囲の都市化」であったとするなら、いまの「ジャングル」や難民キャンプの話はどちらかというと「高密度の都市化」の方で、どれほどの密度かはさておき、既存の都市の見方を問い直すようなイメージとしてこの概念区分を私は考えたいなと思っています。もちろん明らかなように、「広範囲の都市化」と「高密度の都市化」は対立し合うというよりも、相互関係にあるものです。しかし、このようなつながりと集まり、広範囲化と高密度化は、つねに争われる場であり、資本主義的なつながりを遮断する民衆的な集まりもあれば、予期せぬ自律的なつながりの創出もある。
仙波 2011年のオキュパイ・ウォール・ストリートのウォール街占拠や道路の封鎖、あるいは黄色いベスト運動などもそうだと思いますが、何かしらの公共のインフラや資本主義的な流通にくさびを打ち込むことが、近年起きている世界中の抗議行動においてさらに重要な意味を帯び始めている。
難民や移民の人びとのように、そこで都市空間を形成するまでには至らないにしても、たとえば黄色いベスト運動がガソリン税の引き上げへの抗議が発端となっていることを見ても、都市のインフラをこれまでにように利用していくことから振り落されることへの不安が、彼らを突き動かしているとも言えますよね。
そういう意味でも、北川さんがおっしゃるように「広範囲の都市化」に対置される「高密度の都市化」をもう一度いかに捉え直していくかということは非常に重要だと思います。私もこの論集のなかの各論(「ポストコロニアル都市理論は可能か?」)で、アナーニャ・ロイなどのポストコロニアル都市理論の潮流のなかで進められている議論に着目することで、ブレナーらとは違った観点からそれを試みたつもりですが、いずれにしても、私たちにとっての今後の大きな課題であることは間違いありませんね。
北川 私はプラネタリー(惑星)という言葉は重要だなと感じていて、先ほどお二人が「なぜ惑星か」というお話を少ししてくれましたが、では、なぜグローバルではダメでプラネタリーなのか。
まず都市論の文脈でグローバルと言うと「グローバル・シティ論」など、すでにある議論が連想されてしまうということもありますが、ルフェーヴルの言う「都市的なものの地球化」を引き継ぐプラネタリー・アーバニゼーションをさらに引き伸ばせば、近年の人新世や資本新世の議論とも関連してくるからなんですね。惑星都市化は、ある都市自体のグローバル性を主に問うたグローバル・シティ論とは出発点のベクトルが逆かもしれません(グローバルという言葉自体がそもそもは地球を表すわけですが)。
先ほど仙波さんが「惑星という地図」とおっしゃいました(第1回参照)。それは、地球という球体、惑星である限り、地表に特化した平面的な地図ではなく、単純に言っても、海や空、地下や上空など、深さもあれば高さもある地図になるでしょう。
深さというのは資源を採掘したり海底ケーブルを設ける動きだったり地質だったり、高さは飛行機はもとより、ドローンや衛星技術、タワマンなんかもそうかな? ブレナー自身は、惑星都市化は「地表、地下、流域、大洋、大気圏といった空間を含む地球全体の操作との連関で探求されなければならない」と述べていますが、この「操作」や「連関」の空間を追うには、ロジスティクスであったり、イギリスの地理学者スティーブン・グラハムが論じるような垂直性の議論へと接続することが求められるわけですね。
あと個人的にそうしたいことでもあるのですが、こうした研究はここでとどまらずに、人間が平面化、地図化、あるいは領土化しきれない「大地」と人間の関係、地球と人間の関係を根底から考え直すプロセスと連動させていく必要があるように思っています。
これは、アナキストの地理学者エリゼ・ルクリュなどを渉猟しながら高祖岩三郎さんが以前に述べていたように(『新しいアナキズムの系譜学』河出書房新社、2009年)、大地、地球を環境問題や気候変動にのみ切り縮めずに、すべての生命にとっての宿命的な共棲状態を強いる共通なるものとみなしていくプロセスです。大地——身体も——は資本によって「無償労働」させられ、国家によって囲い込まれ、惑星都市化によって裁断されてきたわけですが、大地、地球は、予想外だったり不可視だったりする自律的な地理的つながりを多数多様に、無数に創出してきた場でもあり、地図的な平面や地表よりもはるかに過剰な潜在的なるものでもあるのです。
ただ繰り返しになりますが、地球とか惑星といっても単純にすべてを飲み込むような均質的で超越的なスケールではありません。今日は各地の話を簡単に述べさせていただきましたが、それはこうした都市化やロジスティクスが織り成す不平等な「まだら状の地理」であると思います。
ともすれば人新世の議論は具体的な場、空間というものを少しイメージしにくい嫌いがあると思うのですが、そういう意味でも、都市論という文脈を人新世の議論のなかに入れていく必要があるでしょう。気候変動は都市化という現象、資本主義的都市化、そして惑星都市化と当然大きく関わっています。グローバルという言葉では伝わりきれないものを、プラネタリー(惑星)とひとまず言い直すことで、いまの資本主義的な都市化、空間の問題、それのみならず労働や生、争いや拒否、そして自律的な空間や生活についてより深く考えていけるのではないかなと思っています。
(第3回に続く)


