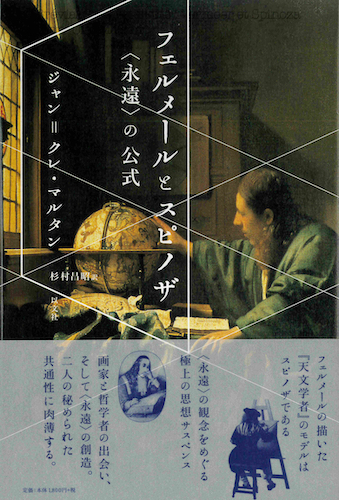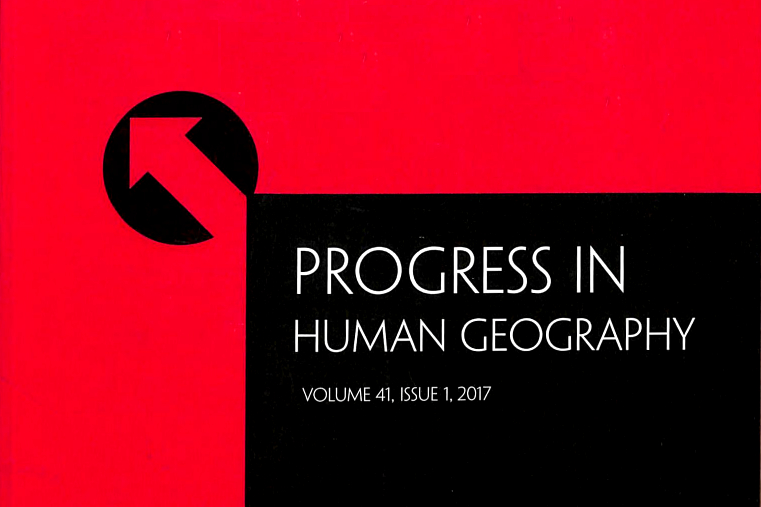2つの訳書──『戦争と資本』と『フューチャビリティー』
8月から9月にかけて訳書を2冊刊行した。
エリック・アリエズとマウリツィオ・ラッツァラートの共著『戦争と資本』(作品社)とフランコ・ベラルディの『フューチャビリティー』(法政大学出版局)である。
前者は信友建志との共訳、後者は私が単独で翻訳した。原著者の3人はみなフェリックス・ガタリを介してつながった私の友人たちである。
『戦争と資本──統合された世界資本主義とグローバルな内戦』(作品社)

マルクス、フーコー、ドゥルーズ/ガタリの思想をふまえた「唯物論的歴史哲学」の書としての『戦争と資本』の要諦は、この場合、戦争という言葉が──戦争と聞いて一般に思い浮かべるような国家間の戦争だけを指しているのではなく──、一国内あるいは国境を超えた「内戦」を指しているという点にある。
この「内戦」は、新自由主義グローバリゼーションの進展に伴い、国境を横断するかたちで、いわばグローバル資本と国家権力が複雑に絡み合った世界的社会構成のなかで起きている。訳書の背帯に記した「世界内戦論としての戦争論」とはそういう意味である。
「階級的内戦」「宗教的内戦」「民族的内戦」「文明的内戦」「性やジェンダーをめぐる内戦」、そしてなによりも「主体性の内戦」。資本主義は国家間戦争にもまして、こうした様々な内戦を活用して増殖し生き延びてきた。資本主義とは、言ってみれば、「資本が民衆に対して永久戦争を仕掛ける体制運動」なのである。
したがってわれわれは、「戦争と平和」という二元論ではなく、「戦争と資本」の融合という一元論に向かって認識論的転回を行わなければならない。戦争に「平和運動」を対置しても戦争はなくならない。資本が戦争を必要不可欠とするかぎり、資本主義機械を止めるために有効に機能する「戦争機械」(社会的闘争機械)を構築して対抗する以外に戦争をなくす方法はない。
資本主義は国家間戦争のみならず、社会のなかに多様な内戦を生み出し、それに勝利することで生き延びてきたし、今後も生き延び続けるだろう。この多様な「内戦」に民衆の側からいかなる「主体的」戦略を打ち立てて対抗することができるか、これが21世紀の「革命運動」の課題であるということだ。
思えば、「1968年」の「世界的反乱」以降、社会変革運動は資本(主義)との戦争に絶えず負け続けてきた。しかもその「敗北」の総括もまともになされないまま、なし崩し的に忘却され、元の木阿弥になりつつある。今一度、あらゆる次元でこの半世紀の「内戦」の分析を行わなくてはならない。これが著者たちの思いであり、私もそれに共感し、「訳者あとがき」の末尾に次のような文章を付け加えた。
「本書を読みながら、わたしは数年前に翻訳刊行したエリック・アザンの『パリ大全』(以文社)のなかで、この革命史家が、19世紀の「諸革命」に言及しながら記した一節を思い起こした。すなわち「“敗北”という概念の周囲を探索してみるなら、そこには真実という巨大な結果が残されている。敗北は実現されなかったことを明るみに出す。幻想──共和主義的友愛、法と権利の中立性、人間解放を約束する普通選挙といったような──が君臨する場所において、敗北は、突然,真の性質を知らしめ、合意を一掃し、支配のイデオロギー的欺瞞を明らかにする。いかなる政治的分析、いかなる報道キャンペーン、いかなる選挙闘争も、街路で銃殺された人々の亡霊ほど明瞭なメッセージを担ってはいないのである」。さらにアザンは言う。「敗北のなかに未来への思想的遺産がある」と。エリックとマウリツィオが共同で仕上げた本書の結論は、アザンのこのネガティブ=ポジティブの歴史的思考とも共鳴する」。
『フューチャビリティー──不能の時代と可能性の地平』(法政大学出版局)

『フューチャビリティー』は、前著『大量殺人の“ダークヒーロー”』(作品社)で現代資本主義社会の暗部から発現する個人的反逆としてのヒロイックなテロリズムを徹底分析したフランコ・ベラルディが、そのペシミスティックな世界観をあえて振り切って、この「不能」(インポテンツ)の時代に「21世紀革命」の可能性を探ろうとした思想実験的野心作である。
電子テクノロジーの発達による社会生活の「自動化」が人々の「主体性」を奪っているところに、現代文明の最大の問題があると考えるフランコは、先端テクノロジーに携わる認知労働者の「反乱」を期待する。この場合、認知労働者というカテゴリーをどう理解するかが問題となるが、単にIT関連労働者ではなくて、「機械的労働」以外の何らかの創意工夫が求められる知的労働すべてを包含するカテゴリーとして理解したほうが生産的である。
フランコが引き合いに出しているマルクスの「一般知性」もそう理解すべきである。すなわち、資本テクノロジーの推進する社会生活の自動化作用に対抗する「主体性」の奪還こそが、未来を切り開く力になるということである。そしてそのためにフランコは人間の潜在的能力に期待する。
本書のもうひとつの魅力は、フランコのラディカルな政治詩人的感性の閃きが紡ぎだした名言がちりばめられていることである。
以下にいくつかを引用しておこう。
「民主主義のための条件は(少なくとも)二つある。すなわち、政治的意志決定の自由と有効性。この二つがともに解体されたのだ。言葉が技術の規則に従属し、技術言語的自動化が社会的諸関係を制度化して以来、自由は空っぽの言葉となり、政治的行動は有効性や重要性を失うことになった」。
「平和運動はわれわれの不能の兆候であり尺度である。実のところ、ひとえに国際主義だけが平和を友好的に追求する条件である。しかし国際主義は心の持ち方でもなければ、平和への意志でも戦争の拒否でもない。国際主義は何かもっと深くて、もっと具体的なものである。それは世界的規模で人々が同じ関心と同じ動機を持つという意識の問題である。国際主義とは、労働者が自らの国家や人種や宗教を気にかけずに連帯することである」。
「コンピューター化できないものの力を重視しなくてはならない。コンピューター化できないものは人間の進化を主導する力である。そうであるがゆえに、われわれの歴史は人間的なのである」。
「私は絶望と喜びは両立不可能ではないと考えている。なぜなら、絶望は知的精神状態であるが、喜びは身体化された精神状態だからである。友愛は絶望を喜びに変える力である」。
「資本主義はもう死んでいる。われわれはその死骸のなかで生きていて、その腐敗した体からの脱出口を必死で見つけようとしているが見つからない」。
「私はミシェル・フーコーは一番重要な本を書かなかったのではないかと思うことがある。つまり近代における賃金労働の系譜である。人間が延命するために賃金という脅迫を受け入れ,今もこれに耐えているという事態は、どうして起きたのか? 人は労働や自然の産物を享受する権利と引き換えに自分の時間を貸し出さなくてはならないという広く行き渡った確信は自明のことではないし、自然的必然性に基づいていることでもない」。
「左翼の政治的力ではなくて、社会が資本主義から文化的に自立することこそが、世界的規模で起きている労働者の疲弊と力の喪失を逆転させることができる潜在的力を持っているのである」。
フランコのこのような現代社会の行き詰まりに対する分析的名言を本書のいたるところに見いだすことができ、それらを数珠つなぎにしていけば、読者にとって世界を明晰に見るためのもうもうひとつの窓が得られるだろう。
こうして、この2つの書は、社会的実践を通した「個人的・集合的主体性」の再構築というフェリックス・ガタリが晩年熱烈に提起した路線を継承しているという共通点を持ち、それぞれの仕方で現代革命の喫緊の課題に取り組んでいると考えることができる。是非ご一読いただきたい。