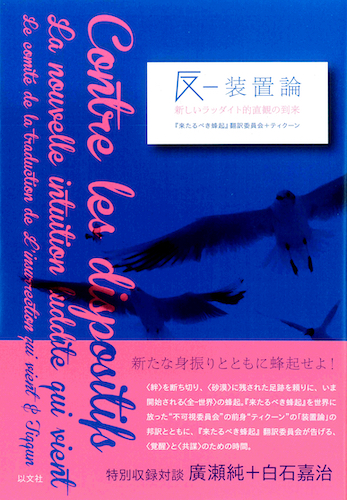理想と現実の狭間で
キルケゴール、現代、仏教
佐々木閑 × 須藤孝也
2021年8月、小社からキルケゴール哲学の研究を専門とする気鋭の哲学者・須藤孝也氏の単著『人間になるということ:キルケゴールから現代へ』を刊行した。キリスト教を信仰しながら思索したキルケゴールの哲学において、宗教の問題は外すことのできないテーマである。また同書はキルケゴールの哲学と思想を探究することから大きく踏み出し、現代社会、現代日本に関する著者自身の批評が展開されている。宗教と社会、宗教と現代を考えるうえで、本書の刊行記念として、仏教と現代社会についてさまざまな書物を通じて思索を実践されている花園大学の佐々木閑氏との対談を企画させていただいた(以文社編集部)。
神を信仰しない人のためのキルケゴール論
――差し支えなければ、佐々木先生から須藤先生の著書『人間になるということ』を読まれた感想をまず伺えればと思いますが、いかがでしょうか。
佐々木 それが一番難しいですね。まずは仏教と、キルケゴールの信仰や哲学はどこが違うのか、という視点で読ませていただきました。言うまでもなく、それは「神」の存在です。絶対的な神の存在を前提として全ての論理性を組み立てていくというのがキルケゴールの考え方なわけですから、論理的には非常にしっかりとした骨組みとなっていますね。キルケゴールというのは、あまり曖昧な、ぼんやりとした概念は入れないように自分でも意識していたのではないでしょうか。それは仏教の論理の性格とも似ています。しかし、その前提となる、数学でいうならば「公理」がキルケゴールの場合はいわゆる「神」なんですね。一方、仏教の公理は、神はいるけれども、それは我々を統括するような存在ではない。「統括者はどこにもいない」というのが仏教の公理になります。そのように共通点と相違点を感じながら読ませていただきました。つまり、キルケゴールは「あやしい」感じがしない。
須藤 今のお話を聞いてまず思い当たるのは、この本の書き手である「私」の存在です。私自身は神を信じていません。キルケゴールは神を信じていて、統括者としての絶対神がいる。他方で、仏教にはそういう神がいない。そして私にもいない。
佐々木 いないのですか。
須藤 そうですね。キルケゴールと神、そして私という三者の関係で言うと、そうなります。
佐々木 それは仏教に来たほうがいい(笑)。私にも神はおりません。釈迦の信者ですから。だた、問題なのは、釈迦は信頼するけれども、釈迦の世界観は受け入れられないのです。なぜかというと、それは2500年前のインドの世界観だからです。その当時の人としては、自明の理として「輪廻」や「業」といった世界観がある。これはやはり釈迦の公理です。輪廻や業があるという世界観でどうやって自分の煩悩を消すか、ということを考えたわけですから。2500年前のインドにあった釈迦の世界観を共有しない時代の私が、それでも釈迦の信者になれるのか。その場合、釈迦の世界観を除外してその後に何が残るのだろうか、ということを汲み取らなければならなくなります。それが現代的に釈迦の思想で生きるということの意味だと私は考えています。
ですから、キルケゴールから現代を考える、現代を生きるとなると、現代人のほとんどはキルケゴールが信仰している神を同じように信仰することはできないでしょう。それならば、キルケゴールの思想から神を抜いたうえで、キルケゴール独自の思想というのは成り立ち得るのかという問題提起になるわけです。仮にそれができるならば、キルケゴールは現代においても意味を持つだろうと思うのですが、その点はいかがでしょうか。
須藤 その点については、まず、私は本書のタイトルを「人間になるということ」としており、「人間であること」としていない、というところがミソになっていると思います。
人間はこういうものだという人間の本質、人間である以上誰もがもっているだろう、その中身や内容を、哲学者たちは代々語り明かそうとしてきたのだろうと思うのですが、現代において誰もが持っているはずの本質のようなものを言明することが果たしてできるのだろうか、私は少し疑っています。
そうではなく、人間として何か足りていない、欠けている、欠損のようなものがあるという感覚を、現代の多くの人がもっているのではないか。そんな話を京都に来る新幹線のなかで(編集担当の大野さんと)話してきました。キルケゴールの思想では中心に神がいて、それゆえに人間は永遠性を持っている、というような話になっていますが、そういった本質論なしに人間を語るということをしなければならないのではないか。私はそう考えています。
佐々木 時代的にもせざるを得なくなってきたのですね。
須藤 今の佐々木先生からの宿題に答えるならば、人間の「中身」は名指せないけれども、人間の「働き」というのは語れるのではないか。そういうふうにキルケゴールの人間論を止揚して、キルケゴールが語った人間論を、働きの次元に持っていって読み替えるということがもしできるならば、普遍性といいますか、現代性のようなものが語れるのではないかなと思っています。
佐々木 わかります。まさにそれは正論だと思います。つまり、「実在」としての実態ではなくて、「作用」としての実態というものを想定した場合に、その「作用」という意味での「私の実在」というものを確信できるであろうというわけですね。ただ、その場合に、それで確信できるのは「私」ですけれども、「他者なる存在」である「神」というものを、その「作用としての私」とどう関係づけるかということが今度は難しくなりますね。その場合の神は、どのように設定できるでしょうか。
須藤 キルケゴールの場合、という意味でしょうか。
佐々木 いえ、今もしわれわれが神というものを何らかの形で想定せよと言われたときに、私自身を作用として考えるとするならば、動いている今、働いている時間軸上の私が私なのであって、時間が止まってもそこに私がいるとは言えないということですよね。作用ですから。そういう私がいて、そしてその外部に神がいるとすると、その神というのはどういう概念で設定できるかということが、やはり気になってきます。これはキルケゴールだけではなく、おそらく現在のキリスト教、イスラム教、全ての一神教の人たちに対する問いになるでしょうね。
須藤 いきなり話の専門性がぐぐっと上がってしまいましたが(笑)、キルケゴールは、その他のキリスト教徒に比べると、神を弁証しないと言いますか、神の存在を証明するといったようなことはしません。トマス・アクィナスなどとは違って、神の存在そのものについては、少し曖昧にしておく、人間にはわからないところがあるというようにしておく。そういうところがありまして、論証で詰めていって「神はこういう存在だ」「そのような神が存在する」といった議論は展開していません。
それでは神はまったく人間にとって不可知な存在かというと、キルケゴールの場合、やはり啓示といいますか、イエス・キリストの存在が大きいのだと思います。神は見えないけれども、イエス・キリストは、聖書に書いてあるとおり、何かをやったり言ったりしたのではないか、あれはただの人間ではなくて、やはり神の現れなのだと信じている。キルケゴールは、神といきなり論理で対決するというのではなく、(トマス・アクィナスと私たちの)中間のあたりにいるような感じではないかと思います。
佐々木 ヘーゲル嫌いだったそうですね。ああ、そうかと思って納得しました。キルケゴールのなかには、体験としての神が存在しているわけですね。それはよくわかります。現代においてそういう人は存在し得ないかというと、そうではなく、宗教体験を通じてなんらかの絶対者、他者を確信している人は非常に多い。「我々は神を信じられないのだ」と言う現代人は、ごく一部のそういう世界にいる人たちの傲慢なのでしょう。私は現代においても、そういうことを無条件で信じていますという人をたくさん知っています。
そういう意味では、キルケゴールが別に古いわけでも何でもない。違う部類なのですね。キルケゴールを何らかの意味のある存在として現代でも受け入れるということは、私は十分あり得ると思います。
自己反省のための外部性のあり方
須藤 そういう神であれ、何か違う存在であれ、超越的・超自然的な存在とともに生きるといいますか、そういう生き方をしている人も現代にいるでしょう。もちろん、していない人もいるでしょう。キルケゴールを研究していると、キルケゴールには何かそういった存在がいて、彼はその存在とともに生きているのだなと思えてきます。
そういうふうに何かとともに生きていると、その何かと「まなざし」を交換しますよね。この存在から私はどう見えているのだろうか、この存在から今の時代はどう見えているのだろうか、と自分がいるところで自分がもっている「まなざし」ではなく、そういった想定される他者の立場に立ったつもりになって、そこから見えているだろう世界を想像して、世界を俯瞰することができる。
この場に4人いれば、佐々木先生から私はどう見えているのかなとか、想像しながら私は話していますが、お互いにそういうことをしている。やはり1人でいるのとは違う意識状態になっており、リフレクションと言いますか反省性が立ち上がってきて、自分のなかで「こんな話し方で伝わっているのだろうか」とか、「リアクションを見ている限り、何か伝わっているみたいだな」とか、反省することができる。人間的な他者でももちろんいいのですが、そうでなくても、そういう人間的他者ではない「他者」、宗教が相手にするような「他者」を持つことによって、人間の世界がより重層的になるのだろうと思います。
佐々木 それはそのとおりだと思います。それは間違いない。正直に言うと、実は私もそういう人間なのです。滅多に話したりはしないのですが、本を書いたり論文を書いたりしていますと、バリバリの合理主義者で「神がいるなんて佐々木さんは信じているはずがない」とみんな思っているのでしょうが、私自身は「私を守っているものはある」と思っています。それは信じている。ただ、その感覚を人と共有はできないので言わないのです。共有できると思った場合には、人に勧めるという気持ちが出てくる。一緒に、仲間になって同じその絶対者を信じる友達になりましょうという気になるのでしょうけれども、その絶対者が私1人の絶対者であって、他の人と一切共有できない。
須藤 何か、名前はあるのですか。
佐々木 名前もないのです。しかし、感じているのです。そのものは、日常的に私を応援してくれるわけでもないし、何かせよと言うわけでもないのだけれども、私が何か決断したり人生の岐路で考えたりしていくときに、必ず正しい方向を示してくれる。お告げも啓示もありませんが、自分で選ぶと「それでいい」と言ってくれるのです。だから、私は人生のさまざまな決断をするときにたとえうまくいかなくても、いつも安心していられる。それは「うまくいかないほうがゆくゆくは正しい道だから」というふうに選ばせてくれているものだからです。一時、それがうまくいかなくて失敗したように見えても、最終的にはいい方向に向かっているのだから間違いないという意識がいつもある。ですから、そういう意味では、常に2人連れなのです。そのことをキルケゴールが書いたかどうかはわかりませんが、そういう感覚でいると、宗教的な絶対者の感覚を信じながらも合理的な生き方を貫くことはできるという思いはあります。
須藤 ソクラテスのダイモニオンみたいですね。
佐々木 なるほど。
須藤 何か悪いことをしようとすると、ピピっと「やめろ!」と、指令なのか何なのか分かりませんが、「聞こえて」くる。ソクラテスの場合は、そのダイモニオンとともに生きていますから、ダイモニオンに禁止されずになした自分の行為は間違っていないという確信がある。間違ったことをしようとすると、ピピーっと笛が鳴るはずなのに、鳴らなかったんですから、それは間違っていないはずだと。
佐々木 まさにそういう感覚ですね。ソクラテスは別に一神教信者ではありません。けれども、よく似た感覚、神を信じる感覚になっているわけですね。ですから現代的にどうか、という話になってくると、そういうあり方は現代においても十分にあり得る。納得できると思います。やはり、いちばんつらいのは、「全てに見放されている」という思いでしょう。何ひとつ私を支えてくれるものはないという絶対的な絶望感というのが、現代においてはいちばんつらいものであると思います。
「外部」から見放された「ネット社会」から脱するためには
佐々木 現代のネット社会のことを考えているのですが、ネットという情報世界が急激に広がって、遥か彼方までありとあらゆる情報を入手できるという感じがしてくる。ただ、実際にネットのなかに入って情報を集め始めると、情報と情報がリンクしてくっついてきますので、1つの情報を手にすると、それと類似した情報が周りにくっついてきて、やがてそれが自分の周りの情報の壁になるのです。ですから、広い視野でいるつもりなのに、実は同じ種類の情報だけに囲まれて、狭い部屋のなかに閉じ込められた状態になってしまっているというわけです。そうした隔離された空間でそのなかだけの情報を吸収していくならば、当然のことながらこれは洗脳になります。どんどん洗脳されていく。今私たちは広い情報世界のなかにいながら、非常に強い洗脳の作用を受けて、ある特定の狭い視野の人間になりつつあるのではという危機感があるのです。
そんなときに、たとえば今お話しした「神」のような概念が重要になる。私が掴み取ったものが世界だというのではなく、私の外側には私を超えた存在がある。そのように考えることで、その壁の向こうを見渡す力が出てくるのです。壁の内側に閉じ込められやすい現代において、そういう意味での信仰の力は必要なのではないかと思っています。
また逆に、壁の内側、狭い部屋のなかに閉じ込められた状態で、自分が見ていることだけを信じている人たちは、小さな宗教をたくさん作り始めている。どうしてそのように思うかというと、新型コロナ・ウイルスが流行し、そのためのワクチン接種が推奨されるようになってワクチン陰謀説なんかが登場してきたことが典型的な例だからです。合理的な情報がこれだけ拡散されているわけですから、プラスの面でもマイナスの面でも情報はいくらでも手に入る。そうした情報を客観的に判断する機会はいくらでもあるのに、いったんその陰謀説のなかに入ってしまうと、周囲はその情報の壁で固められてしまって、陰謀説を否定する情報は一切入ってこなくなってしまう。知らぬ間に洗脳が進んでいく。この現象は、現代における宗教的な部分のマイナスの側面を表しているように思います。
須藤 悪い意味での宗教、ですね。
佐々木 そういうことです。その悪い意味での宗教が今、非常に大きな力を持ちつつあるというのが、私の危機感なのです。ネット社会のなかで、またオウム真理教のようなものが出てくる可能性があると感じています。ですから、物事を正しく判断していくうえで、今言ったような「神」というわけではないけれども、自分以外に自分を見ている、観察している存在を持つということが、非常に重要なのではないかと思います。そのような存在によって、自己批判というのか、自己反省というのか、自分は決して絶対的に正しい人間ではないという自制がいつも働きますから。
須藤 自分の外部にある存在と関わる宗教性と、現代ネット宗教のような内部にある悪しき宗教性というような、外部性で内部性という対比ができてきますね。
佐々木 ええ。私はそこが大事だと思います。
須藤 外部性は宗教になりうるけれども、内部で一貫しているというものも悪い意味での宗教になってしまう。
佐々木 そうだと思います。複数の人が同じ絶対的な真理、つまり人為的な真理でも社会的な真理でもなく絶対的な真理として信じ込む。それに従って自分の生き方を徹底していく組織があれば、みな宗教ですから。内部的な宗教とは要するに自分たちが信じていることは果たして本当に正しいのだろうかという自己反省の心を持たない宗教です。
須藤 そうなると、やはり自己反省というものが非常に重要になってくるように思います。自己反省すると、時には自分を否定的に評価しないといけなくなります。間違いは間違いだと認めないといけません。しかし、内部性の人たちはそうした自己反省が苦手で、自分の間違いを認めたがらない。自分の間違いを見たくない。ずっと自分たちが正しいと「うっとり」としていたい。
佐々木 そうです。お互いにお互いの正しさを支持し合うわけだから、その確信はいよいよ強くなっていくわけですね。どんどん強化されていく。そして、それに反対する者に対しては一切、耳を貸さないという状態になっていきます。
須藤 そのような状態に陥ってしまうほどに、現代人というのは批判される、否定される、駄目出しされるということを非常に怖がっている。それを恐れるから、あまり人に本音を言いません。表面的なところで褒め合っていることが多いように見えます。
佐々木 ええ。それがネットのなかだと一挙に解放されてしまう。だから悪口雑言、罵詈雑言の世界になっていく。それは裏返しなのでしょうね。須藤さんがおっしゃるように、人間の対面関係においては、穏やかさを繕わなければいけないという思いなのでしょう。コンプライアンスが非常に発達してきて、自由気ままにやるということが次第に制限されていくからこそ、その裏返しとして、ネットのなかで他者を批判する快感と、仲間内でお互いに褒め合って、相互に自信過剰になっていく現象というのは一連のもので、全てつながっているように思います。他者に対する気兼ねというものを非常に強くせざるを得なくなり、そのぶんどこかでそのストレスの発散の場所を求めている。それがネットに向けられているのでしょう。
ですから、ネットのなかでは極端な付き合い方になります。褒めるか、貶すか。仲良くなるか、無視するか。「どうでもいいけれども付き合っている」というのはあまりできなくなるのでしょうね。でも、実際に生きていると、どうでもいい付き合いの人がたくさんいるのもとてもいいものだと思いますよ。

Photo by David Calhoun
淡い光としての仏教の救い
須藤 キリスト教のポジティビティというのは、強烈な光のイメージですが、仏教の光というのはもっと弱い、淡い光であるように思います。音についても同じようなことがあるかもしれません。たとえば、佐々木先生のお名前の「閑」というのは、無音という意味ではありませんよね。
佐々木 はい、「閑」という言葉は、サイレントの意味ではありません。
須藤 ええ。サイレントではない。音はしているのですが、うるさくはない。
佐々木 そう。みんなには「お前はうるさい。名前の字と全然違う」なんて言われますけど(笑)。
須藤 沈黙や無音ではないけども、静かな感じですね。仏教の力、救いというものはそれと同じように全く無力というわけではありませんが、非常に穏やかというか、強力なものではない。直接的ではなく、奥ゆかしい。そんなことを最近考えます。キルケゴールの本を書いた人間が仏教の人に会うということは、佐々木先生が冒頭でおっしゃられたように、キリスト教と仏教の間でいったい何が違うのかということがトピックになってくると思いますが、それに答えるならば、光の強度が全然違うのではないかと思います。
佐々木 それについては、須藤さんの本を読んで、すぐ感じました。やはり、キルケゴールの信仰、キルケゴールの神というのは、どこかギラギラしていますね。他方で、私は仏教をいつも病院にたとえています。病院が表立って、社会のなかでメインの産業になるはずがありません。病院は病気があるから存在している。病気がなくなればいらないわけです。しかし、人類のうち何パーセントかは必ず病気になるわけで、その何パーセントかの人々のために仏教はある。これが仏教の自覚です。人類100パーセントを救うためにあるなんて、最初から思っていない。
また、病人を救うためにあるわけですから、元気で健康な一般の人たちのところまで出かけていくことも考えない。つまり、布教をしない。仏教にとって大切なのは、継続することであって、広げることではありません。そういう考えが基本になっている点を、須藤さんのように「奥ゆかしい」と感じてもらえると、ありがたいですね。
しかし、キリスト教の場合、やはり神というのはキリスト者だけでなく万人にとっての神ですから、万人がその神の存在と慈悲の気持ちを受け入れねばならないという前提が最初からある。当然、布教を重視し、強く主張することが善となってくるのでしょう。
仏教の場合は、伝えるべき意思のある主体がいないわけです。神がいないわけですから。神の言葉なんてないわけですから、命懸けで守るものもない。だから、釈迦は「どうせ仏教は滅びます」、なんて言っている。仏教の教えだって諸行無常の現象のひとつですから、いつまでも続くわけがない。いずれ滅びるという末法思想が最初からある。
須藤 筏の例がありますね。
佐々木 あれも面白いですね。たとえ話ですが、川の向こう側が彼岸であり、そこは悟りの境地です。悟りを開くためには、その川を渡らなくてはならない。此岸、つまりこちら岸で一生懸命に木を切って、筏を作り、川を渡って彼岸へと辿り着いた。しかし、彼岸についても目的地はその先にあるからさらに歩いて行かなければならない。そのとき、自分が乗ってきた筏はどうするべきか。頭に担いでいけば、筏が重荷になり、やがて道半ばで倒れて、目的地に行き着くことはできない。だから、正解はその筏を捨てることなのです。
その筏が何を表しているかというと、釈迦の教えなのです。釈迦の教えによって、自分がその境地まで到達したら、今まで大切にしてきた教えは捨ててもいいということです。次の道は、次の手段で行けという意味なのです。だから、釈迦の教えが絶対というわけでもない。そうなると、仏教の世界では絶対的に、最後の最後まで守らなければならないものなんてないということになる。これは面白いですね。病院でいうなら薬です。病気が治るまでは薬は大事ですが、健康になったらもういらなくなる。
日本人がキルケゴールを理解することの困難
須藤 そうした対比で考えますと、やはりキリスト教は、いつまでも忘れずに覚えていなければならない教えや概念があるということになりますね。キリスト教というのはヨーロッパでは中世くらいまでは、布教を通じてキリスト教徒ではない人たちにキリスト教の正しさを教え信者にしていったのですが、キルケゴールが生きた時代になると、ヨーロッパの人々はみんなキリスト教徒になっていて、もうすでにキリスト教世界ができあがっているような社会でした。少なくともデンマーク人はみんな国家にキリスト教徒として登録されているような状態です。そうした世界のなかでキルケゴールは仕事をしているわけです。
キルケゴールはそのことをこの上なく明確に自覚していました。そのような時代の文脈がキルケゴールらしさを構成しているとも言えます。キルケゴールは異教徒を相手にしていない。今、目の前に存在する現実のキリスト教徒たちを、もっと「まっとう」な、ある種「理想的」なキリスト教徒にしたいというのがキルケゴールの課題でした。
先ほど、佐々木先生は釈迦とその世界観を共有しないとおっしゃいました。それは私にとっても同様で、私もキルケゴールと世界観を共有していないのです。キリスト教徒しかいない「キリスト教界」ヨーロッパ、デンマークの社会のなかだけにいて、何がわかるというのか。もっと世界は広いのではないか。いろんな人間に出会って一緒に生活し語り合ってみなければ、「人間とはなんぞや」などということは語れないでだろう、と21世紀の日本に生きる私は考えている。ですから、19世紀のデンマークの枠内でだけ考え著述活動を行ったキルケゴールは、非常に内向的に見えます。
佐々木 須藤さんが本書のなかで書かれている通り、当時もそんなふうにキルケゴールのことを批判的に見ている人もいたのですね。
須藤 はい。すでに大航海時代をヨーロッパは経験していたわけですし、フランス人やスペイン人、ポルトガル人なんかは、世界にはキリスト教徒ではない非ヨーロッパの人々がたくさんいることを知っていました。しかし19世紀のデンマークの状況は少し違うのです。あまり対外的なことを考えない時代だった。ナポレオン戦争によってデンマークという国自体が弱体化し、領土も取られて、外には活路は見いだせない、そんな状況をどう生きるのかが当時のデンマークの人々の多くにとっての問題だったようです。
佐々木 なるほど。そうした時代の哲学者であるキルケゴールが、現代において生きてくるというのは、いったいどういう理由があると思いますか。
須藤 ひとつは、20世紀に実存思想がブームになったとき、ヤスパースやハイデガー、サルトルといった哲学者たちがみな、キルケゴールに一定の評価をしたという流れがあります。その後、20世紀も後半に入ると構造主義やいわゆる「現代思想」が流行します。そうすると実存思想はアウト・オブ・デイトというか時代遅れになってくる。そうしてヒューマニズムも廃れてきて、「人間の終焉」ということが言われるようになってきた。ジル・ドゥルーズやジャック・デリダなど一部の現代思想の哲学者・思想家たちがキルケゴールの思想に部分的に注目することはありました。しかしキルケゴールの人気自体が回復しているとか、現代において再度注目されているというわけではないと思います。ただ、西洋哲学を研究するうえで、ハイデガーにしろ、アドルノやデリダにしろ、さまざまな哲学者・思想家に影響を与えていますから、キルケゴールは知っておいたほうがいい、ということはあるでしょう。
佐々木 実存主義の人からすると、キルケゴールは神と一体化して生きるという典型的な例です。もっと言えば、「極端」な生き方の一例としてやはり重要なのでしょうか。構造主義以降、実存主義は否定されたように、キルケゴールの生き方からはもっと離れていくことになるでしょう。だからこそ、逆に価値が出てくるのではないかとも思います。今現在、キルケゴールのような実存とは真逆の方向で極端なところまで針が触れてしまっているからです。自分の外部にある絶対的な存在を信じる生き方と手を切るという方向では、これ以上はもう無理でしょう。ですからやがて揺り戻しがくると私は考えています。我々は何者かとともに生きているという感覚を持った人間こそが、実は幸福な道へと進めるのだという発想が、また出てくるのではないか。その感覚が悪く働くと、先ほども述べました視野の狭い宗教に陥ってしまうこともあるでしょうけれども、そんな時代に、キルケゴールのあり方を正しく世に伝えるという仕事は大事になるのではないかと思います。
須藤 私自身、キルケゴールは理解するのが難しい人だと考えています。なかなかわからない。正直に言えば、キリスト教徒が人口の1パーセントほどで、その文脈を共有していない日本人が、キルケゴールをそのまま読んで理解できる、なんていうことはありえないのではないかとすら私は思っています。やはり研究をきちんとしないとキルケゴールが何者だったのかということはわかってこない。誤解するのは簡単ですけれども、正確に理解するというのは非常に難しい対象です。
キルケゴールは、カントやヘーゲルのように、難解ではあるけれども考えたことを明示的に論理的に書いてくれる哲学者たちとは決定的に異なります。『イロニーの概念』という著作もありますが、彼自身がイロニーの使い手なのです。そうなってくると、テクストを読んでキルケゴールの「本心」を掴むというのがなかなか難しい。
それにもかかわらず、彼の言葉は読む人にとってとても刺激的で、詩を読むように響く人には響くらしい。わかった気になりやすいのです。本書のなかでも書きましたが、たとえばキルケゴール思想には内面性というキーワードがあります。日本人がこれを読むと、この言葉は私たちが言う「心」に近いのではないか、キルケゴールは「心」のことを語っているのではないか、と解釈できてしまう。世にあるキルケゴール論の多くは、そうした誤解の歴史のように思えます。とりわけ日本ではそうです。
佐々木 なるほど。合理的には掴めないキルケゴールの実態を正しく語るためには、むしろ、合理的に語らなくてはならない。これはとても大切なことだと思います。今の話を聞いていて、私は鈴木大拙だと思いました。鈴木大拙もまた「霊性」という言葉を使っています。今の「内面性」と「心」の話と同じで、大拙の「霊性」は形式として読んだ人が自分勝手に解釈できてしまう。だから人気が出るわけです。大拙を読んだ人は、私は大拙と一緒だと勘違いしやすい。そういう読みでは、大拙そのものを掴むことはできない。
須藤 そうですね。よくキルケゴールは親鸞と似ているというか、近いというようなことが言われますが、私は全然伝統が違うのに、本質的に同じことを言っているなんていうことがありうるのだろうかと疑問に思っています。しかし、そうなってくると、キルケゴールが言っていることは、文脈を共有していない日本人にとって、本当はあまり面白くないものなのかもしれません。
佐々木 日本人にはいわゆる西洋崇拝的な気持ちがありますから、自分たちの意見や考えが「西洋の誰それという人と同じことなんだよ」と言われたときに気持ちがいいのでしょう。
須藤 伝統的な比較研究では、AとBという2つを並べて同じところがあるのではないかと見当を付けて観察し、類似点を探すということがなされたのでしょうけれども、宗教学研究の成果に照らしていくと、現代においては全ての宗教を貫く何か本質のようなものがあると考える宗教本質論はやはりやりづらいのではないかと思います。
佐々木 なにしろ、創造性がない。どうしても比較だけで終わってしまうから。比較して、類似性や差異がわかったところで、その先については何も出てこない。今まで知らなかったもの、珍しいものを紹介して、似ているでしょう、とか、違うでしょう、とか言うだけの話ですから。
歴史的な対象としてのキルケゴールと釈迦
佐々木 私はやはり歴史が重要だと思っています。知的営みの基本は全て歴史なのではないかと思うのです。歴史観をベースにした探索がなければ、それはもう学問として成立しない。意味がないのではないか。時間軸を無視して同じ次元だけで並べて見せれば、当然そこには錯誤、間違いがたくさん入ってきます。そうした錯誤は自分にとって都合の良いように見えるものですから、結局、自分の感想を述べているだけの話になる。歴史はそういうものを否定します。歴史を検証していけば、間違いを間違いとして正しく指摘できる。やはり、歴史観というもののない学問は意味がないと思います。
須藤 いろいろ思い当たります。若いときはやはり私も「哲学脳」でしたので、時空を超越して永遠に正しいと言えるものがあるのではないかと思っていました。しかし、勉強していけばいくほど、歴史を知らないと、哲学も何もお話にならないということがわかってきました。
佐々木 そのとおりですね。
須藤 ですからキルケゴールも私からすれば歴史的な対象になります。キルケゴールの19世紀らしさというものに、私は注視しようとしています。21世紀の人間からしたら、19世紀らしさというのはもう価値のないものなのかもしれませんから、そうしたものはもし見つけたとしても、結局は捨ててしまうかもしれません。しかし、それをきちんと見て、理解しないことには、「捨てる」ということもできません。
佐々木 そうですね。私が釈迦の世界観を共有しないにもかかわらず、釈迦を信奉しているのは、歴史観を持っているからなのです。歴史観なくして21世紀の今、釈迦の教えが成り立つでしょうか。やはり釈迦の時代の社会と現代社会では大きなズレがあります。そのズレがわかれば、そのぶん修正することができる。そのズレを理解するには歴史を知ることが重要です。歴史を知れば、今の私にとっての真実と、歴史性のなかでは真実性を失っている部分とが明確に区別できるようになってきます。このように歴史観がないと、何ひとつ正しいものを掴めなくなってしまう。
私が歴史や歴史観が大事だと思ったきっかけは、物理学におけるビッグバン理論でした。ビッグバンが提唱される以前の物理学では、宇宙は静止した定常的なもので、そのなかで法則性を見つけていくことが物理学の仕事だとされていました。ニュートンもアインシュタインも基本的にはそういう考えです。しかし、ビッグバン理論が出てきた瞬間に、宇宙は時間軸上に変容していくということになった。そうすると、宇宙法則さえも時間的に変化するだろうということになる。物理学が歴史学になってしまったのです。そうなったら、後はすべて歴史ですね。かろうじて数学が残っていますが、数学における概念も時代とともに変わっていきますから、実際の話、時間を超越した数学的真理などないでしょう。そうなると、極端に言えば、時間性すなわち歴史性のない思考というのはほとんど意味のない思考だということになってしまう。
ですから、キルケゴールをきちんと19世紀の人として捉えることが大事なのであって、そうすることで初めて、21世紀から見たキルケゴールの、正しい見方というものが成り立つのだと思います。
理想と現実、出家と俗世
須藤 学問をやっている人間からすれば、歴史的認識というのは外せないものだと思いますが、学問に関わっていない人間、つまり一般の人の場合、あまり歴史を追っているわけにはいかないという人もいますよね。
佐々木 一挙に掴んでしまいたいと願う人たちですね。すぐに確信を掴みたいと願う人がたくさんいます。
須藤 そのとき、思い出すのは出家という文化です。出家していない人の知のあり方と、出家して修行している人の知のあり方は、当然ながら異質ですよね。
佐々木 それは異質です。
須藤 そしてブッダ(釈迦)は異質でいいんだと言っている。
佐々木 そうです。仏教では、この世に生まれてきた生き物のことをまとめて衆生(しゅじょう)と言いますが、衆生は、そもそも無知です。ですから全ての煩悩を持っている。つまり全ての生き物はまず煩悩を持った生き物としてあり、そのような煩悩の海で溺れている。そのなかで煩悩を消そうという意欲を持った人だけが、煩悩を消すための道に入っていき、そういう人たちで1つの島を作る。仏教は海のなかに浮かぶ1つの島なのです。煩悩の海としての一般社会、すなわち俗世があるというのが前提です。それを認めなければ、そのなかの島社会である仏教も消滅してしまいますから、そのような俗世があることは否定しません。そのなかで仏教は、特殊な、病院としての世界を作っていくという自覚がある。ですから、2種類の異なる世界観を持った人たちが、異なる価値観で生きる二重世界の存在を当然のこととして仏教は認めているわけです。
輪廻のなかで善い行いをして、幸せなところに生まれましょう、というような、欲望の充足を幸せと考える人たちの世界と、それ自体を否定して欲望を持たない人間になろうと努力する出家の世界という、善悪の構造も違う2種類の世界を最初から想定し、その両者があるから両者が成立するというシステムで考えているわけです。
須藤 欲望を満たしたいと思って頑張っている人がたくさんいるのだと思いますが、それは苦しみの世界の原因でもあるのですね。
佐々木 そうです。それが苦しみの世界なのです。ただ、苦しみの世界ではあるけれども、それを苦しみと感じるかどうかはその人の状況によります。苦しみでないと感じている人もたくさんいます。それに対して仏教は一切、縁を持たない。触れない。つまり先ほどもお話ししたように布教をしない。それはそれで良いと考えるのです。苦しみを感じていて、そこから抜け出したいと願う人だけを受け入れるのです。
須藤 なるほど。そこが仏教らしいところですね。普通は「君、間違っているよ」と言いたくなるところですよね。
佐々木 「君、間違っているよ」と言いたくなるのですが、釈迦はそれを「間違っている」とは思わないのです。それが自然だと思う。それが普通なんだと言う。ただ、気がつくとそのままではいられなくなります。そこから抜け出したくなってくる。だから抜け出したい人には抜け出す道を教えますというだけの話です。善し悪しではないのです。
須藤 その気づきのきっかけというのは、与えなくとも勝手に起こってくるものなのですか?
佐々木 そうです。その人自身の人生のさまざまな出来事や状況によって、そうなる人もいるし、ならない人もいる。それに関していっさい仏教の側からは働きかけはしない。
須藤 そうすると、やはりキルケゴールはお節介ですよね。気づかせるために、この本を読みなさいと言う。これを読むと気づくよ、というわけですから。
佐々木 やはり「君、間違ってるよ」派ですよね(笑)。キリスト教世界のなかでそういう「君、間違ってるよ」派ではない人はいないのでしょうか。来る人は拒まず、縁なき人とは触れ合わずというような姿勢の人。そのような人はおそらくいたとしても、名もなく消えてしまったのでしょうね。仏教だって下手すれば何もなく消えていったはずなのです。たまたまアショーカ王が信者になり国家的に広まったため、ここまで残ったのでしょう。そうでなければ、誰も知らないまま消えていった可能性は大いにあります。
須藤 実際に、ヒンズーによって取り込まれてしまった歴史もありますね。
佐々木 ええ、おっしゃる通り、仏教も一時期は勢力を拡大しましたが、やがてヒンズーの勢力が増して次第に衰えていきました。ですから、こんなに力のない宗教が、よくここまで頑張って残ってきたなとも思います。
須藤 私自身がそうなのですが、キリスト教の信仰を持っていない人間からすると、やはり、キリスト教のポジティビティにすんなりと乗っかることができない。見るべきところはあるとしても、です。しかし、そこで話を終わりにしていいかというと、もっと考えていかなければいけないところもあるだろうと考えています。そんなときに仏教の否定性、ネガティビティというか、先ほどの淡い光としての仏教のように、違う論法のものも踏まえていかなければいけないと思っていました。ある種、キリスト教のポジティビティとのバランスを取るためには仏教のネガティビティを知っておかなければならないのではないか。私にはそんな問題意識がありました。
佐々木 全くおっしゃる通りだと思います。私なんかも仏教、仏教と言っていますが、釈迦そのものを丸ごと信仰しているわけではありません。私はいつも「信仰」ではなく「信頼」だと言っています。信仰はしない、信頼しているだけだ、と。SONYの製品は信頼するけれどもSONYを信仰しているわけではない、というのと同じですね。ですから、そういう人間にとっては釈迦の教え1本で生きていくなんていうことはとても考えられない。それを修正するためのさまざまな手がかりを他の世界に求めていかなくてはならない。そうした探究を土台にして、釈迦のどこが正しく、どこが私には受け入れらないのかを決定しなければならない。

Photo by panoglobe
宗教と政治の関わり方
須藤 私自身、本来は政治的な問題への関心はあまりないほうだったのですが、本書の担当編集である大野さんとの長い付き合いを経て、社会的な不条理や政治的な問題についてだんだんと関心を持つようになってきました。ですから本書の後半もかなり政治的な話に寄っておりますが、佐々木先生のお話を聞いていますと、仏教はあまり世直しをするような集団ではないわけですよね。
そしてそれはキルケゴールの場合についても同じで、キルケゴールを論じる人のなかで、政治を語る人は従来はあまりいませんでした。やはりキルケゴールは政治の空間ではなく宗教の空間で働く人というふうに据える研究者が多かったのです。しかしキリスト教ヨーロッパの統治の伝統を見ると、明らかに宗教と政治はリンクし絡まっています。キルケゴールだけを除外する必要はないだろうと思いますし、政治の文脈でキルケゴールを読むとやはり見えてくるものもある。
と同時に、そう考えたときに、日本人には政治に積極的にコミットしない人が多いですが、そこにはきっと何か理由があり、その理由もおぼろげながら見えてくるのではないかと思うのです。
佐々木 やはり、神が見ているという意識が、そこには作用しているのだろうと思いますね。その神というのは善と悪を峻別できる目のことです。そのような存在がいつも自分を見ているという感覚です。そのような存在にいつも見られているからこそ、社会的な正しさをいつも認識して活動しなければならない。ところが、日本人の多くはそういう神のようなものを持たない。誰からも見られてないので、好きなことをしていればいい。好きなことをしろと言えば、みんな必ずサボりますね。だから、活動しない。これが、日本人があまり政治に向かわないことの理由ではないかと思います。
須藤 日本の状況を考えたときに、こういう問いの立て方をするのはナンセンスかも知れませんが、キリスト教は役に立つのかとか、キルケゴールは役に立つのかとか、あるいは仏教は役に立つのかといった問いが一方であるのだと思います。その際、どういう距離感で、宗教と政治というのを考えればいいのか。私はこれまでキルケゴールの研究を続けてきて、キリスト教のほうは徐々に見当がついてきたように思いますが、仏教のほうは長い歴史もありますし、政治性の強い宗派もあれば弱い宗派もある。政治と結びついた時代もあればそうではない時代もある。仏教と政治の関係というのも多岐にわたるのだろうと思いますが、佐々木先生としてはどういうふうに仏教と政治の関係を考えておられるのでしょうか。
佐々木 やはり役に立つというのはいったい誰にとって、どう役に立つのかということからこの問いを始めなくてはなりません。「役に立つ」ということを普通に考えれば、それは利便性が高くなり、より快適な生活が実現する、つまり欲求が充足するということが役に立つということになるでしょう。政治というものが目的とするのはまさにその一点なので、より快適で安全な生活を実現するために役に立つということですね。
ところが、そういう意味での「役に立つ」ということが仏教の概念には入らないのです。仏教においては、自分の煩悩が消えて、欲望の充足を目指さない人間になることが目的ですから、「役に立つ」というのはそういう人間になるために役に立つことを意味します。そうなると、政治における目的と仏教における目的は全く相反します。欲望の充足に向かう活動としての政治や経済という者は、仏教の目的に反する道です。そこに身を置くこと自体が反することになっている。ですから、仏教における「役に立つ」道というのは、政治や経済から身を離す場所に自分を置くことが一番正しいということになってしまいます。
しかし、これは社会全体からすれば、反社会的な活動あるいは非社会的な活動ですから、褒められることではない。褒められないということを自覚しながらその道に行くわけですから、逆に承認欲求の強い人、つまりみんなから褒められたいと思う人は、政治や経済に身を投じたらよろしいということになります。これはもう違う道の選択です。それが仏教の、政治や社会との関わりのあり方です。
須藤 上座仏教において修行しているお坊さんたちはサンガに属している。その姿を見せて、こういう人間たちがいる、出家したいと思えばあなたもできるんだよという現実を一般人に対して見せるということが、仏教ができる救いの実践だと佐々木先生もご著書で書かれていたと思います。
佐々木 そうです。それが僧侶としての社会に対する活動です。
須藤 アジールと言ってもいいのでしょうか。
佐々木 ええ、一種のアジールになりますね。
「理想」があるからこそ、「現実」を生きられる
須藤 「来ていいよ」という感じですね。そうなると、キリスト教はお節介にもわざわざ自分たちから出て行って、「助けてあげますよ」という。全然違いますね。
佐々木 違いますね。ただ、そのような仏教も、あくまでも過去の歴史を調べた結果として、私が獲得している「理想としての仏教」なのであって、現実はそうかというとそうではありません。今もスリランカ、あるいは東南アジアの国々とは、そういうアジールがある世界なのですかと問われると、素直に「はい」とも言えない。僧団のなかにも欲望まみれの人はたくさんいるわけで、そうした人たちは仏教僧団を社会的な勢力として確立したいという思いを持っている。政治的に非常に強く動いている仏教集団は今もたくさんあります。それはやはり現実と理想は違うということです。ですから社会や政治に関わっていくというのは、理念として見た場合に限って、釈迦の教えとは全く反するということです。
須藤 理想と現実という意味では、たとえば中村元先生の本を読みますと、中村先生の仏教は整いすぎていると言いますか、誤解を恐れずに言うと「きれいごと」しか書いていないようにも思えます。それに対しキルケゴールでは、理想に辿りつけない自分、理想を持っているのだけれども、理想にまで到達できない歪な自分、もがいている自分が強烈に出てきます。そんなものばかり読んでいる私からすると、中村先生の本を読むと、あまりにも整いすぎているように感じます。
本書のなかで、私は「真理感覚」の重要性を書きました。ですから自分の書いたことと矛盾するようですけれども、理想ばかり書いていると、息苦しく感じることがあります。理想のほうへ行けない人もたくさんいるわけですよね。私も含めて。そういう人にも届くためには、違う書き方、アプローチの仕方もあるのではないかと考えます。私はよく「きれいごと」と「きれいなこと」は違うと言うのですが。
佐々木 私も同じようなことを感じます。それはね、やはりエリート中のエリートの言葉なんです。しかし、一方で須藤さんが書いておられる「真理感覚」、つまり理想というものも持っていないといけない。私は理想に適う生活を送るというのは、ある面ではとても自由な暮らし方だと思っています。たとえるならば、道路を歩くときの信号機のようなものです。信号機が設置されて「赤信号は止まれ、青信号は進め」というルールが社会全体で共有され守られているなら、私たちは道路を安心して歩くことができます。常に安全かどうか、渡ってもよいか渡ってはならないかを、意識しながら歩く必要はありません。道を歩きながらでも、風景を眺めたり、考えごとをしたりすることができます。
しかし、これが全く信号を守らず、交通ルールを守らないような社会だったらどうでしょう。道を歩くのに常に気を配りながら歩かなければなりません。他のことに頭を使う余裕などないはずです。理想に叶った生き方というのは、つまらない煩いがない世界のことです。つまらない煩いがなければ、そのぶん、自由に物事を考えることができる。やりたいことに集中することができるのです。ですから、須藤さんが自著でおっしゃるような、「真理感覚」というような「理想」を持つということは、現実を生きるためにも、大変大事なことだと私も思います。
(了)
1956年、福井県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。花園大学教授。『宗教の本性 誰が「私」を救うのか』(NHK出版新書、2021年)、『NHK「100分de名著」ブックス ブッダ 真理のことば』『(同)般若心経』『(同)ブッダ 最期のことば』(NHK出版、2012、2014、2016年)、『科学するブッダ 犀の角たち』(角川ソフィア文庫、2013年)など著書多数。
須藤孝也
1974年、青森県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。現在、一橋大学、立教大学、法政大学などで非常勤講師を務める。著書に『キルケゴールと「キリスト教界」』(創文社、2014年)、訳書にマーク・C・テイラー『神の後に』上下(ぷねうま舎、2015年)等がある。